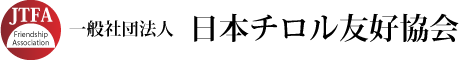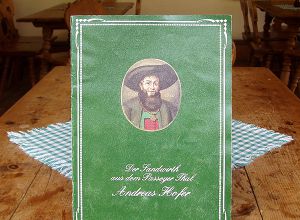チローラーの紹介
アンドレアス・ホーファー〈Andreas Hofer〉
| <チロルの男>の初回を飾るのに相応しい人物は、この英雄を他においていない。チロル人ならば誰もが知っており、チロルの民の心に深く刻まれている人物である。彼の人生の一端を振り返ってみれば、以下のようである。
アンドレアス・ホーファーは、1767年10月2日、パッサイアー・タールの旅籠ザント・ホーフ経営者ヨセフ、母マリアの長男として生まれた。姉が三人おり、ホーファーが三歳のとき、母親が死亡。父親は再婚したが七歳のとき、彼も死亡した。ホーファーは継母に育てられたが、十分な愛情を注がれなかった由で、このことが逆に若くして独立心に富む性格を築いたと言われている。 |

|
|---|
ホーファーは、22歳になった1789年、旅籠ザント・ホーフを正式に相続し、この年に二歳年上のアンナと結婚。二人の間には一男六女がもうけられた。ホーファーは旅籠経営の他、馬やワイン、ブランデーなどの取引を営み、チロル地域に広く売り歩いたことから顔が知られまた、誠実な取引により地域住民の信頼を勝ち得ていた。
1790年、パッサイアー地区選出のラント・チロルの代議員となり、インスブルックへも度々、出かけるようになった。1789年、フランスでは革命が勃発し、その末期にナポレオンが台頭して瞬く間にヨーロッパ諸国を蹂躙した。1805年には、アウステルリッツで戦われたフランス対オーストリア、ロシアの所謂三帝会戦においても勝利をおさめた。ナポレオンと同盟したバイエルンはこの時、チロルに侵攻した。
戦いの後始末のプレスブルク条約が締結され、チロルは、オーストリアからフランスの同盟国バイエルンに割譲されることになった。因みに、バイエルンは、ナポレオンとの同盟の諠により、公国から王国に格上げされた。
当時のバイエルンの首相モンジュラは、フランスの影響を受けた啓蒙思想家で、近代的な国家体制の確立を目指していたが、その政策は、バイエルンのみならずチロルにも押しつけられた。元来、保守的であるチロルの住民にとっては、僧院の廃止とかカトリックの祭日廃止とかの宗教政策は、急進的であって受け入れがたいものであった。また、モンジュラは、兵士を集めるために徴兵制を敷き、これをチロルにも適用して、弱体なバイエルン軍の強化を図った。このため、チロルでは労働の担い手である若者を取られ、チロル経済は衰退し、バイエルン占領軍による略奪や婦女子への狼藉などが重なって住民の不満が鬱積した。
チロルは、密かに皇帝の弟ヨハン大公と連絡を取り合い、反撃の機会を窺った。ホーファー自身もヴィーンに赴き、ヨハン大公と作戦を打ち合わせた。1809年4月10日、カール大公が率いるオーストリア主力軍がバイエルンに侵攻すると同時に、ホーファー率いるチロル農民軍が立ち上がり、第一次ベルク・イーゼルの戦いが勃発した。農民軍はこの闘いに勝利し、占領軍をインスブルックから追い出した。
5月になり、バイエルンの援護に駆けつけたフランス軍とチロル農民軍との間で第二次ベルク・イーゼルの戦いが行われた。ホーファーは、チロル軍最高司令官として戦いを指揮し、侵略軍を撃退した。更に8月。またもや侵略してきたフランスとバイエルン連合軍との間で第三次ベルク・イーゼルの戦闘が戦われ、これに勝利をおさめたホーファーは、チロル執政官としてホーホ・ブルクに入城した。この時、彼が執務した部屋は現在「ホーファーの間」とも呼ばれている。
チロル地域ではチロル農民軍が攻勢であったが、オーストリア主力軍は敗退に敗退を重ね、1809年10月14日、フランスとの間でシェーンブルン条約を締結することを余儀なくされ、北チロルはバイエルンに割譲されて南バイエルンと呼称されることになり、南チロルはイタリア王国(国王はナポレオンであり、実質的にはフランスの一部。国土は現在の北イタリア)に編入されることとなった。
このような結末は到底、チロル住民に受け入れられるものではなく、1809年11月、チロルは単独で第四次ベルク・イーゼルの戦いに突入した。しかし、オーストリア正規軍の援護はなく、孤軍奮闘の様相は免れず、圧倒的な敵兵力の前に結果は惨憺たるものであり、チロル軍は、フランス及びバイエルン連合軍に打ちのめされて撤退した。その後の敗残兵狩りは凄まじく、ホーファーは妻子とともにパッサイアー・タールから山奥に入ったプファンドラー・アルムに逃亡した。
この隠れ家は一部の者にしか知らされていなかった。しかし、後に「チロルのユダ」と呼ばれる裏切り者、農夫フランツ・ラッフルに密告されたため、1810年1月28日の早朝、百人のイタリア兵に急襲され、ホーファーは、妻及び息子とともに逮捕された。妻子は翌29日、ボーツェンにて釈放されたが、ホーファーは、ザンクト・アフラ収容所に収容され2月5日、マントゥア(イタリア名-マントゥヴァ)に移送された。
その頃、フランス皇帝ナポレオンは、オーストリアとの関係改善を図っており、オーストリア皇帝フランツ一世の長女マリー・ルイーズを妃に迎える話が進んでいた。ホーファーには既に処刑の命令が下されていたが、オーストリアは彼の助命を嘆願し、何度か交信のやり取りがなされた。しかし、1809年2月20日、ホーファーはナポレオンの命により、マントゥアにて銃殺刑に処せられた。
1810年3月17日、フランツ・ゲオルク・メッテルニッヒ(クレメンス・メッテルニッヒの父親)は、皇帝フランツに、ホーファーの未亡人及び子供たちに対して然るべき援助が与えられるよう要請し、許しを得て未亡人の元に金銭を届けさせた。
1810年4月4日、オーストリアの駐仏大使クレメンス・メッテルニッヒ(後に外相としてヴィーン会議を主宰、その後オーストリア首相=1773-1859)は、フランス皇帝ナポレオンと会談した際、ホーファーの件でナポレオンが、「ホーファーの死はまことに嫌悪すべきことで、私の意思に反することであった。彼は、私の知る限りにおいても、チロルを解放するために戦った勇敢な男であった。フランツ皇帝に私の遺憾の意を伝えて欲しい」と語ったと本国に報告した。ちなみに、同年4月2日、ナポレオンは、マリー・ルイーズと結婚した。ナポレオン41歳、マリー・ルイーズは18歳であった。
博物館のショールームには、遺族から寄贈されたサーベル、銃、彼が着ていた服などが展示されている。処刑を前にして、友人に宛てた彼の最後の手紙もある。とても死を目前に控えた人間のものとは思えないほど、冷静な文面である。曰く、「親愛なる友よ。神の意志により、私はここマントゥアでこの世に永遠の別れを告げる。しかしながら、執行の時刻が迫った今、神の御許にまかり参るのは、そんなに苦ではないように思われる。これも、神のご加護のお陰だろう。神は、恩恵を授けて下さった。この最後の瞬間に至るまで、私の魂が多くの選ばれた人々と永久に喜びを分かち合えることを・・・私が神の御許で、全ての人たちに祈りを捧げられることを・・・とりわけ、私が償いをしなければならない人たちのために・・・君と君の奥方に感謝する。書物や物品を差し入れてくれたことを・・・友たちに願う。私が煉獄の炎の中で償いをしなければならないときは、灼熱の炎から私を救ってくれるように・・・私がここに所持している金銭は、貧しき人たちに分け与えた。残っている金品があったら、それは君が受け取って同じように貧しき人たちに分け与えて欲しい。それでもって、私の償いができるとは思えないが・・・この世の全ての人々の幸せを祈る。我々がまた、天国で再会できる日まで・・・パッサイアーの人々、私の知人たち。祈りを捧げるときは私を思い出して欲しい。さようなら、私の小さな世界よ。死に際しても、私は涙を流さないだろう。早朝五時に記する。私は九時に、神のご加護を受けて天国へ行く。1810年2月20日。マントゥアで」
このほか、妻に宛てた手紙が一通あるということだが、司書員ユーディット・シュヴァルツ女史の話では、遺族の宝となっていて公表されていないとか。ちなみに、未亡人となったホーファーの妻アンナは、1836年12月6日の亡くなる日までザント・ホーフに住み、その間、オーストリア政府からは年金が支給され続けたとういうことである。
博物館内には、アンドレアス・ホーファーにちなんだ土産物も売られている。マグカップからホーファーを称えるCD歌集まである。博物館の隣の建物が、アンドレアス・ホーファーの生家であるザント・ホーフ。二階建ての豪農風の建物は、当時としてはかなり裕福な造りである。外壁は塗り直されたが、切り妻は同時のままの木造である。
ザント・ホーフは、1816年、ハプスブルク家に買い取られ、1838年、ホーファーの娘に下賜されて娘夫婦が旅籠の経営を再開したが、この夫婦に子供がなく再び、ハプスブルク家の所有となり1890年、インスブルックの貴族マトリケル・シュティフトゥングに払い下げられて現在に至っている。中は、レストランになっている。メニューの表紙は勿論、アンドレアス・ホーファー。壁にも彼にちなんだ絵が掲げられている。アンドレアス・ホーファーの生家までは、メラーン駅から110番のバスが三十分に一本の割合で運行されている。
ホーファーが逮捕されたプファンドラ・アルム(1320m)には、彼が妻子と隠れ住んだ小屋が当時のままに保存されている。二月の雪深い厳寒の季節には、すきま風が至るところから入る粗末な山小屋である。ザンクト・マルティンのバス停からは約2時間強のハイキング・コースであるが、訪れる人は多い。麓からの標高差は700m弱ある。
ホーファーが銃殺されたマントゥアのポルタ・グィリアには、今でも当時のままの門が残っている。その入り口左手にちょっとした公園があり、その中に入っていくと正面に追悼碑が建っている。解説はイタリア語とドイツ語とで書かれ、「チロルの解放闘士であるアンドレアス・ホーファーは、この地で銃殺された」と記されている。
不撓不屈の岳人ラインホルト・メスナー(Reinhold Messner)
世界には8,000m以上の頂を有する山は、14座あるが、その全てを初めて登頂した岳人は、南チロル出身のラインホルト・メスナーである。その中の幾つかは、メスナーが初登頂を記録した。また、メスナーは、1978年、世界最高峰のチョモランマ(エヴェレスト)を初めて酸素吸入マスクを利用することなしに登頂に成功した。彼は更に、世界七大陸の最高峰を全て登頂した登山家としても著名であり、世界が生んだ最高の岳人と評しても過言ではない。メスナーはまた、南極大陸、グリーンランド、チベット、ゴビ砂漠、タクラマフン砂漠等を単独で横断した冒険家としても世界的に著名な存在である。
メスナーは、南チロルで生まれ、すでに5才にして父親とともに故郷南チロルの3,000m級の雄峰を登頂し、以来故郷の山々、またヨーロッパ・アルプスの高峰を重装備で駆け回り、雪と氷に覆われた垂直の岩壁を攀じ登り、一人の岳人として大きく成長した。不撓不屈、信念を曲げないメスナーは南チロル人の典型であり、また自身南チロル人であることを大きな誇りにしている。メスナーいわく、自分は国籍こそイタリア人であるが、、それは偶々イタリアが第一次世界大戦中にうまく立ち回って、勝者側に乗って、それまでオーストリア領であった南チロルを、大戦後の1919年に併合した結果、そうなったに過ぎない。自分は骨の髄まで南チロル人であり、オーストリア人でもないし、ドイツ語を母国語とするからと言ってドイツ人でもない。自分は、あくまで南チロル人であり、またヨーロッパ人でもある。メスナーによれば、南チロルは今やEUの中でも最も繁栄している地域の一つであり、南チロル人はそのような発展に大きな誇りを持っている由である。
1944年9月17日生まれのメスナーは、さすがに氷雪と岩壁に覆われた8,000メートル級の過酷な登山に対する挑戦は控えているが、彼の山と山に暮らす人々の生活と歴史・文化に対する愛情と興味は尽きることを知らず、南チロル(5つ)とドロミテ(1つ)に6つのメスナー山岳博物館(MMM=Messner Mountain Museum)を設営し、また運営し、同好の士の訪問を待ち望んでいる。MMMは世界で始めての山岳博物館であり、全ての登山愛好家と山を愛する人々に出会いの場と、山と登山に関する豊富で正確な情報と知識を提供している。以下、6つのMMMを簡単に記す。チロルを訪れた際には全部とは言わないが、その中の1つでもご覧になることを是非ともお勧めしたい。いずれも一見の価値あることを保証したい。
1.MMM Firmian(フィルミアン)-「魔法にかかった山の頂き」-この博物館のテーマは、「美術に表現された山岳風景と登山の歴史」である。ボーツェン近在にあるジグムンズクロン城内(Schloss Sigmundskron)にある。
2.MMM Juval(ユーファル)南チロルのフィンシュガウ(Vinschgau)にあるユーファル城(Schloss Juval)内にある。ここでは「山の神秘」をテーマに、メスナーが収集した世界各地の山岳民の制作による手工芸品・民芸品、特にチベット民族による素晴らしいコレクションに接することが出来る。
3.MMM DOlomites(ドロミテ)-「雲に浮かぶ博物館」-は、アルペン・スキーのメッカの1つとして世界的に著名なコルティナ・ダンペツォ(1956年の冬季オリンピックで、猪谷千春選手が回転競技でこれまで日本で唯一の銀メダルを獲得、またコルティナ・ダンペツォは、2026年の冬季オリンピックをミラノとともに二度目、イタリアとしては、2006年のトリノを含め、三度目の冬季オリンピック開催地となる)の南、標高2,181mの高地にあり、垂直に切り立ち、氷雪に覆われたドロミテの正に奇観としか形容できない山岳世界をテーマとしている。ここでは訪問者は、ドロミテの圧倒的で素晴らしい絶景を360度の眺望で楽しめる。
4.MMM Ortles(オルトレス)-「世界の果て」-では、南チロル最高峰オルトラー(Ortler)(3,905m)を間近に見るSulden(ズルデン)にあり、南チロルの郷土小説家クリフトフ・ランズマイアー(Christoph Ransmayer)の作品「氷と暗闇の中」に因み、南チロルの氷河の世界をテーマにしている。
5.MMM Ripa(リパ)は、Puster Tal(プスター渓谷)にあるブルネック城(Schloss Bruneck)にあり、世界の山岳に暮らす人々の歴史と文化をテーマに、「山々の遺産」として様々な衣装や民具を展示している。
6.MMM Colones(コロネス)は、「アルピニズムの伝統」をテーマに、2015年に開設された。このMMMは、海抜2275mのプスター・タール(Pustertal)のクローンプラッツ(Kronplatz)にあり、南チロルで最も高い地にある博物館である。このMMMでは、ヨーロッパ・アルプスの名高い岩壁とこれらに挑戦したアルピニスト達の活動をテーマにしている。
以上六つのMMMを訪問する上で便利なのは、MMMツアー・チケットで、購入後一年以内であれば、これら六つのMMMに一回入館できるシステムとなっている。
最後に、メスナーに、故郷南チロルとドロミテの山々についてお奨めコースを聞いてみた:
1.一番素晴らしい縦走コースは、何と言ってもシュルレン(Schlern)の高原地帯だね。
2.どの山の頂きが最も美しいかと聞かれれば、標高と歴史の点で、何と言ってもOrtler(オルトラー)だ。でも登山技術上高度の難しさがあり、それだけに登り甲斐があるのはドロミテのLangkofel(ラングコーフェル)がベストさ。
3.何処から見た眺望がベストかと言えば、子供時代の記憶では何と言っても生まれ故郷のVillnoess(フィルネス)のGschnagenhart Alm(グシュナーゲンハルト・アルム)だけど、今となっては、MMMフィルミアンのあるSigmundskron(ジグムンズクロン)だね。Schlern(シュレルン)の雄大な景観を一望に出来るし、何と言っても、ボーツェンを見なくて済むからね。
4.初めて南チロルで山行を楽しむならば、1,000m以上の高原を縦走しながら素晴らしい山々の景観を楽しむに限るよ。縦走しながら山小屋から山小屋を訪ねれば、この土地の人々と知り合いになるし、彼らの日常生活にも触れることが出来るからね。アルプスの最高峰の登頂を目指すよりね、このような1,000m級の高原縦走を是非ともお奨めしたいね。