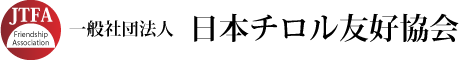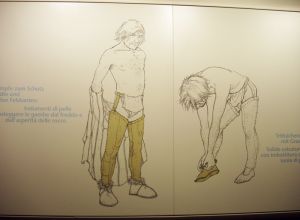南チロルの紹介
ドルフ・ティロール〈Dorf Tirol〉
チロルを現地風に発音して日本語に標記すれば「ティロール」となる。ここは抑も、チロル発祥の地であるからして、現地語の発音を尊重し、正式に「ドルフ・ティロール」と言う。南チロルの案内の始めは、やはり、発祥の地が挙げられて然るべきであろう。
この地域には、古くから人が住みついた痕跡が見られるが、遺跡はとなると、古いのはグラッチ地区から発見された紀元前2300年頃の石造りの墓である。また、ムートコップ、シャレンシュタイン、シュルンテンシュタインの各地区には、紀元前1300年から同850年代に造られた壁跡も発見されている。
紀元前15年には、他の地域同様ドルフ・ティロールもまたローマの支配下に置かれ、その支配は西ローマ帝国崩壊の476年まで続いた。ローマ帝国崩壊後、この辺りに侵入してきたのはバユヴァーレン族である。その侵攻は600年頃まで断続的に続き、彼らがこの地に定着して原住民の祖先となった。
1027年に、トリエントの司教に対してフィンシュガウの伯爵領が与えられ、1096年に、司教アルトマンは、その支配権をアルベルト一世に封土として授与した。アルベルト一世の後継者は、1141年に「チロル伯爵」を名乗り、1149年の教会文書にその名が記され、1248年になって正式に、その名称が認められた。それ以来、チロル伯爵は、勢力を拡大して領土を広げ、今日に至るまでその名を残したが、発祥の地そのものは、1360年の本拠地移転に伴って静かな村に留まった。
現在のドルフ・ティロールは、メラーンの北方にある日当たりのいい高台で、葡萄畑、林檎畑に囲まれ、暖かな陽光が降り注ぐのんびりした村・・・と思いきや、何とまあ人の多いこと。村の中心を走る一本の細い幹線道路。その周囲には、ホテル、ガルニ、そしてペンション。要するに、観光客が宿泊する施設に土産物屋が並び、活気のあること夥しい。やたらとドイツ系の人間が闊歩し、イタリア語は殆ど聞かれないのは、チロル人やドイツ人にとっては、ここが先祖参りのようなものだからであろうか。
実際、ここを訪れる観光客は多い。一年中、観光客の絶えることはない。その観光客の最大のお目当ては、何と言っても〈チロル城〉。皇帝フランツ・ヨーゼフをはじめ多くの著名人たちが訪れており、そのなかにはヒットラーの名前もある。城は、先に述べたアルベルト一世により建設され、その後、本拠地がメラーンに移されるまでは、チロル伯爵の居城であった。近代になって、このチロルを代表する城は、ナポレオンの支配下で売りに出され、後にメラーン市が4千グルデン(現在の価格で約4千8百万円ほど)で買い戻した経緯がある。メラーン市は、城をハプスブルク家に贈呈し、第一次世界大戦後の1919年、オーストリアの敗戦に伴い、イタリア王国のものとされた。その後1972年になって漸く、城は、本来の正当なる所有者である市民の代表、南チロル州議会に属することとなり、1984年に州博物館として一般にも公開され、今日に至っている。
城に行くには、「文化の散歩道」と名付けられた道を行けば良い。村役場を過ぎ、タンツ・ガッセの道端にあるチロルの基礎を築いたマインハルト二世の騎馬像を眺め、ホテル街が途絶えてファルクナーの散歩道(後述)と合流する地点に出れば視界が開け、前方の小高い丘の上に悠然として輝くチロル城の全景が見える。城までは、そこから歩いて15分程である。チロル城への道の途中には、エアデ・ピラミードと名付けられたノッポの茸形の岩も散見できる。城の内部は、現状を損なわぬ状態で保存されている一画と、博物館とからなる。城の解説は、ドイツ語とイタリア語のみだが、英語のパンフレットがある。城はそれ程、大きくはない。城内へはまず、大きな騎士の間から入る。ここには、城で使われた当時の品々が陳列されており、歴代の城主の肖像画もある。騎士の間から二階へ進めば王の間になり、カぺルへと続いている。カぺルは当時のままの状況で、上半身裸のマリアに出会って、足がハタッと止まる。
博物館では、各種の展示がなされるが、大抵、チロルの歴史に関係した展示物で、チロル全史がテーマになった部屋では、太古の昔から今日に至るまでのチロルの歴史が図解、写真などの展示を交えて解説され、全てを読了すれば、チロル学の権威になれる仕組みになっている。特に、日本人には馴染みの薄いイタリア併合後の南チロルの住民運動は詳細に説明され、添付された写真からは、民族分断の悲劇が生々しく感じられ、他国の支配下に置かれた民族がいかに不幸か、遍く知らされる。
チロル城の近くには、フィンシュガウ・タールの見張りとして建てられたトゥルンシュタイン城、現在は農業博物館になっているブルンネンブルク城があり、町の北方にはアウアー城がある。
ティロール村には、保養客のための散歩道が縦横に伸びている。その主だったものに、先の「文化の散歩道」の他「ワインの散歩道」「林檎の散歩道」「パノラマ散歩道」などがある。メラーンを見下ろしながら進む「ファルクナーの散歩道」からは、雄大な景色が望める。この散歩道は、ドルフ・ティロールに別荘を有していたエッツ・タールのホテル王ファルクナーの資金提供によって造られた散歩道で、メラーンの市街やフィンシュガウ・タールを眺めながら崖の縁を進み、適度な木陰もあって、夏でも快適である。
村で一番、目立つ荘厳な建物と言えば、かつての神学校である。現在は、ドイツ系住民のための小学校、中学校になっている。
ケーブルでホーホムートの展望台(1361m)に登れば、素晴らしい展望が待ち受けている。眼下には、チロル城をはじめとしてドルフ・ティロールの村。その先には、エッチ・タールを借景にしたメラーンがあり、東側の丘には、シェンナの村。視線を西に向ければ、フィンシュガウ・タール・・・
正に贅沢な展望台であり、ケーブルは、春先からフル回転で観光客を引き上げている。この展望台からは、ハイキング、トレッキングコースが縦横に走っている。有名なところでは「メラーナー高原路」があり、ルート22に沿って上を目指せば、テクセルグルッぺ自然公園のなかの秘境「シュプロンザー湖群」に達する。
ボーツェン〈Bozen〉
ボーツェンは、エッチュ・タールとアイサック・タールが交わる所に位置し、人口10万人を擁する南チロル唯一の大都会である。この地には数千年前から人々が住み着いていて、古くは、住民自身の呼称「バウツス」を取り「バウツァウム」と呼ばれていた由。紀元前15年にローマ軍によって市内に流れるタルファー川に橋が架けられて、それが記録に残され、この事実により、文書に記載された歴史を持つという意味では、ボーツェンはチロルで一番、古い記録を有している。
西ローマ帝国崩壊後、この地を巡ってランゴバルト族、フランケン族、バユヴァーレン族が争ったが、結局、バユヴァーレン族が勝利を収めて、紀元680年頃、フィルグルベルク付近にカステルウム・バウツァヌムを建設した。その後、トリエントの司教の支配下に置かれ、穀倉地帯としての重要性を帯び、12世紀頃には、現在のラウベンガッセに家々が建てられ始めた。
1277年、チロル伯爵マインハートがこの地を征服し、街を整備した。ちなみに、当時、建設された建物は、19世紀に至るまでそのまま保持されていた。14世紀に入ってアイサック・タールからブレンナー峠への道が切り開かれ、ボーツェンは交易上の重要な都市となった。
17世紀に入って、チロル大公妃クラウディア・デ・メディチが重商主義政策を推し進め、ドイツ及びイタリアに依存しない経済的な自立が図られ、ボーツェンもその枠組みの中で繁栄をみた。なかでも、グリース地域は、転地療養地として世界的に有名になり、多くの人々が訪れることになった。1919年のイタリアへの割譲後は、エットーレ・トロメイの圧政の下でイタリア化及び工業都市化が強行され、ボーツェンに住む住民は強制移住させられ、そこに多数のイタリア人が移り住み、今日では、ボーツェンの人口の70パーセント以上がイタリア語を母国語とする都市に人工的に塗り替えられた。
ボーツェン駅に下車すれば、一番ホームに置かれた彫刻が出迎えてくれる。嘆くような形の彫像は、戦争及び労働災害の犠牲者の冥福を祈るもの。献花の波が絶えることなく続き、いつでも花に囲まれている。駅を出たところは公園。バーンホーフ・シュトラーセの並木道を真っ直ぐに歩いていけば、数分で「ヴァルター広場」に出る。インフォメーションは、この広場に面したビルの一階にある。そこには、ボーツェンのみならず、メラーンやドロミテなど付近の観光地の情報も保管されており、求めれば出してくれる。
<南チロル考古学博物館=Suedtiroler ArchaeologieMuseum>
市内の地図が頭に入ったら、何はさておき、まずは南チロル考古学博物館へ足を向けよう。道は簡単で、市の中心部を通るラウベン・ガッセをウィンドウ・ショッピングしながら歩いていけば、その外れに博物館の建物がある。考古学博物館は1998年、ボーツェン市博物館の向かい側に建てられ、古代及び石器時代<紀元前15,000年>からカロリング王朝<800年>までのこの地域から発掘された品々を展示する施設であったが、突如として、世界の人々を惹き付けるようになったのは、人類の貴重な宝物といわれる人物が展示されたことによる。彼こそ、かの有名な氷河に閉じ込められたミイラ、5200年前の人類である「エッツィ」さんである。
エッツィは、1991年9月19日、エッツターラー・アルペンの標高3210mの高地でドイツ人夫婦により発見され、ミイラがあった場所がオーストリアから92.55m南チロル側に入ったところという理由で、ボーツェンの博物館で展示されることとなったとか。
入場料を支払い、コースに沿って二階(ヨーロッパ式一階)へ。解説者を囲んで説明に聞き入っているグループが幾つかあり、その中で一際、人だかりしている一角が、エッツィが覗ける窓である。大人から子供まで皆、エッツィ目当てでやってくる。イタリアからもドイツからも、スペイン語、フランス語に混じり英語も聞こえてくる。エッツィは世界の宝物なのだということを改めて感じさせられる。列に並んで漸く、小さな窓から、安置されているエッツィさんとご対面。腕を異様に折り曲げた体形は、氷の圧力によるものか、戦いに敗れて転倒したままの姿なのか、見た目には些か痛々しい。骨と皮だけの亡骸は、あれほど丁重に作られたファラオのミイラと差違がない。王も狩人も、死ねば同じ物体ということなのだろう。
ミイラとともに身に着けていた衣服も展示されている。パンツに当たる下着は何と褌である。現代人と変わらない生活感覚が興味深い。弓矢は狩猟用か戦闘用か、かなり精巧に作られている。生活臭が漂う品々がこれだけ一緒に発見されたということは当然、仲間がいたものと思われる。妻や子供だっていたに違いない。となると、埋もれていたのは、この一体だけでないような気がする。なお、エッツィについて、その後の研究により、年齢は大体46歳、身長約1.58m、死因は、矢で射貫かれたことによるものと解明されている。
<市博物館=StadtMuseum>
考古学博物館の向かいには、市博物館がある。この博物館は1905年に開館し、8世紀から20世紀に至るまでのボーツェン市の歴史と文化を語る品々を展示している。展示されているものは、化粧細工、金細工、衣装、版画、色彩を施したタイル製の暖房設備などである。また、図書館には、三万冊に及ぶ芸術史、考古学、歴史書などの専門的な書物が収容されており、どのような書物があるのかは、最新のテクノロジーによりオンライン化されていて、読み出すことができるようになっている。
<凱旋門=Siegesdenkmal>
博物館見学が終わったら、タルファー川に架かる橋を渡って対岸へ足を進める。そこには大理石のモニュメントが建てられている。凱旋門と名前はいいが、これがかの悪名高きファシストの遺産である。見上げればラテン語の文字が刻まれている。曰く、「ここに故郷の国境を記す。この地において、我々は言語、法律及び芸術を教える」
教えられる方は、たまったものではない。当然、闘争となる。事実、闘争となった。何年も続く民族間の闘争、憎悪、葛藤を経て、今日では、融和が図られている。その証左だろうか、イタリア政府との協定の下、ここに、「BZ’18-45,一つの記念碑、一つの都市、二つの独裁」と題し、虐げられた南チロルの人々の抵抗運動を記録として残す展示物が公開されている。この凱旋門は抑も、1926年から1928年にかけて、ファシズム政権の指令の下に作られたのであるが、展示施設は2014年の夏に、凱旋門の地階のスペースに設けられた。
全ての展示物は、ボーツェン市及び1918年にイタリアに割譲されたオーストリアの南チロル州と密接な関係がある。第一次世界大戦が如何ようにして起こったのかを解明する手がかりとして、当時の新聞記事、プラカードなどが展示され、大戦後に始められたボーツェンのイタリア化計画、ドイツ語が禁止されたことに起因する南チロル人民のドイツ語教育施設カタコンベ学校、1939年の南チロル住民の国籍選択問題、第二次世界大戦時におけるボーツェンのファシズムの軍隊などが展示物に基づき、説明されている。
<市街=Zentrum Bozen>
凱旋門を暫し眺め、国家権力が間違った方向へ作用した場合の怖さを噛み締め、敗戦により住民が虐げられる現実に戦きながら、来た道を戻って再びラウベン・ガッセへ入る。市街の東西に伸びているラウベン・ガッセは、中世においても重要な商店街だったが、その様相は今日でも変わらない。道の両側にはアーケードが続いて、高級ブテッィク店やら玩具屋やらが続いている。途中で南に折れれば、インフォメーションのあるヴァルター広場に出る。
この広場は、1808年、この地を占領していたバイエルンの王マクシミリアン・ヨーゼフ一世の命により作られ、当時は彼の名前を冠して「マクシミリアン広場」と呼ばれたが、バイエルンの撤退後は、フランス、バイエルン連合軍に対する解放闘争の指導者の一人であるヨハン大公にちなんで「ヨハネス広場」と呼ばれ、1901年になってドイツ語圏が生んだ中世最大の詩人であるヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ=Walter von der Vogelweideの名前をとり「ヴァルター広場」と呼ばれるようになった。その後、イタリアに割譲されて、また、名前を変えさせられたが、現在は元の名前「ヴァルター広場」に戻っている。
広場の中央に立っているのが、広場の名前の由来である恋愛叙情詩人ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデの像であり、1889年にラース産出の大理石で作られたものである。彼は1170年頃の生まれで、氏素性は明らかではなく、また生誕地はクラウゼンの近郊にあるライェン村と言われているが、これも定かではない由。彼は500以上の作品を残しているが、特に有名なのは「菩提樹の下で」「不機嫌」などの詩だとか。彼の作品については、山田泰完氏の翻訳による「ヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデ」(大学書林1986年)がある。
ヴァルターが生きていた当時は丁度、十字軍の遠征が華やかなりし頃で、彼は、その時代としては精鋭的な、「キリスト教徒もユダヤ教徒も異教徒も皆同じ」との言葉を残しているとか。死亡したのは1230年頃で、墓は、バイエルンのヴュルツブルクにあるノイミュンスター教会回廊にある。ちなみに、作曲家ワグナーは、自作のオペラ「タンホイザー」の劇中、歌合戦の主人公タンホイザーと対立する立場の騎士としてヴァルターを登場させている。
ヴァルターについて述べた因縁で、彼の著名な詩「菩提樹の下で」を披露する。現代語版はウィキペディアにより、現代語版に基づく邦訳(拙訳)は筆者である。
| Unter der Linde an der Heide wo unser beider Bett war, da konnt ihr schoen gebrochen finden Blumen und Gras, Vor dem Walde in einem Tal, tandaradei, sang die Nachtigall lieblich. Ich kam zu der Au, tandaradei, Da hatte er aus Blumen Dass er bei mir lag,wuesste das jemand, |
あの草原の菩提樹の下に 私たち二人の臥床がありました。 草の上に手折れた花々が綺麗に 敷き詰められているのが見えるでしょう。 谷間の森からは、ナイチンゲールが 愛らしく囀っています。 タンダラダイ。 私は、水辺に沿って行きました。 愛する人はもう、待っていました。 彼は、私に声を掛けました。 「気高い乙女よ、慎み深い乙女よ」 私は、とても幸せです。 彼が私にキスをしたかですって? もちろん、数え切れないくらい。 タンダラダイ。 ご覧なさい、私の唇がこんなにも赤いのを。 彼は、花で飾った素敵なベッドを誂えてくれていました。 誰かが小径を通ってここへやってきたら、 大笑いするでしょう。 でも、バラの側で悟ります。 タンダラダイ。 私の心がどこにあるかを。 もしも、彼が私の傍らで寝ているのを誰かに見られたら、 何て恥ずかしいのかしら。 彼が私に何をしたのか、 誰にも分かりませんように。 このことは、彼と私、 そして、小鳥たちだけの秘め事。 タンダラダイ。 小鳥たちもきっと、黙っていてくれるでしょう。 |
<ドーム教会=Domes Maria Himmelfahrt>
広場の南西側にどっしりと建っているのは、ドーム教会である。この教会の歴史はかなり古く、紀元500年頃には、バジリカ様式の初期キリスト教会が建てられ、カロリング朝の時代にも維持されていた。その後、11世紀頃になって建て替えられ、マリア昇天教会と名付けられた。聳え立つ塔の高さは、65メートルある。屋根はどことなく、ヴィーンのシュテファン教会を思わせるのは、オーストリア領だった名残だろうか。
教会の入り口は、広場とは反対の方向にある。教会をグルッと回るようにして正面入り口に着けば、両脇に猿顔の獅子像が身構えている。この教会の財産は何と言っても、カール・ヘンリッヒの「イエスの心臓」。その絵は正面右手の奥に飾られている。また、教会には、付設のドーム宝物庫=Domescha tzkammerがある。広範囲にわたるバロック様式の宗教上の品々が集められ、ここでは、18世紀の神々しい金製品、拝礼に使用される祭礼具、宗教上の旗幟など100点以上の展示品を見ることができる。正しく、真の宝物である。取り分け、金メッキを施された銀製の顕示台(高さ136m、重さ13Kg)は、目が釘付けになる代物である。また、謝肉祭の様子を表した時代を感じさせる人形劇とかアヴィニオンからもたらされた14世紀の古文書とかも展示されている。
宝物庫は、テーマ毎に四部屋に分かれている。第一の部屋では、商業的な国際都市として栄えたボーツェンと教会の歴史が描かれ、第二の部屋では、慈悲深い聖母マリアへの賛美品とか感謝祭の行列図など、第三の部屋では、神聖な聖遺物が展示され、第四の部屋では、地区教会の賞賛を通して地区教会長への献身が語られている。聖書に記されている、「襤褸を纏って布教せよ」との教えは、キリスト教がローマ帝国の国教となって変貌したのであろうか。
<ドミニカーナー教会=Dominikanerkirche>
ドーム教会から西へ100m程行ったところにドミニカーナー広場がある。この広場に面して建てられているのが「ドミニカーナー教会」である。1270年に初期ゴシック様式で建造され、内部のフレスコ画は、ボーツェンの重要な芸術品に教えられている。実際、壁一面に描かれた絵は見応えがある。
この教会は変わった造りになっており、ドミニカーナー広場からの入り口もあるが、横腹にもあって、そこから入ると左手と右手両方に説経台があるような構造になっている。正面から入った場合は、説経台の奥にまた説経台、その後ろに祭壇があるように見える。ドミニカーナー教会の裏手に修道院が付設されている。戦災で傷んだ後の復旧はまだ半ばであり、回廊のフレスコ画も痛々しい。修道僧の数が減ったのか、二階は音楽学校になっている。
ドミニカーナー教会の奥にあるのは「カプツィーナ教会=Kapuzinerkirche」。一般住宅風で、見た目には教会とは思えない建物である。ここは元々、チロル伯爵のヴェンデルシュタイン城があったところであるが、1600年頃、現在の教会が建てられた。内部には、聖テレジアの亡骸がガラス・ケースに納められている。
ドミニカーナー広場に戻り、北に向かってゲーテ・シュトラーセの細い路地を歩いていけば果物市場に出る。ここはラウベン・ガッセとの交差点になっている。果物市場では丁度、季節の冬柿が売られていた。その名も「kaki」と表示されていては嬉しくなる。冬柿風の柿が一山、4つで1.5ユーロと安い。果物市場から更に北へ路地を進めば、14世紀頃に建てられた「フランツィカーナー教会=Franziskanerkirche」。ここの礼拝堂の窓に描かれたステンドグラスは色彩も鮮やかで素晴らしい。聖書に由来する素朴な絵が生き生きと描かれている。
丁度、土曜日のミサが始まったところで、神父の話す言葉はドイツ語だった。礼拝堂を出た左手に、回廊がある。ここに描かれたフレスコ画は、1330年頃のもので今なお、色合いは鮮明である。
<商事博物館=MerkantilMuseum>
ドーム教会からそう遠くない歴史地区のジルバー・ガッセに商事博物館がある。ボーツェン市は当時、商業都市として国際的に重要な地位を占め、アウグスブルクやべニアからも商人たちが商売にやってきたことから、チロル大公妃クラウディア・メデイチは、1635年、ボーツェン市に商事裁判権の権限を与え、彼ら商人たちの間の係争を迅速に対応させた。この建物は1727年に完成し、その後、長い間、商事裁判所として機能し、今日は、商業都市ボーツェンの歴史を語るところとなっている。建物は、広い階段と華美な正面入り口が印象的である。博物館としては、家具類や絵画、歴史的価値がある生地のカタログなどが展示されており、また、以前は裁判所であった貴賓室の華美な設えは、取り分け素晴らしい。
<自然博物館=Naturmuseum>
ボーツェン駅から近く、アンドレアス・ホーファー通りに面したところに自然博物館がある。博物館が入居している建物は、マクシミリアン時代の市役所である。この博物館は、南チロルから採取された生物を展示しており、見所は、一つは、9000リットルの水を貯めた水族館で、見学者は、二億年前の三畳紀に栄えた珊瑚を見ることができる。当時、この地域は未だ亜熱帯の浅瀬で、その後、地殻が隆起して今日のドロミテを形成したのであるが、珊瑚もそれとともに隆起したものである。他の一つは、オウム貝水族館である。オウム貝は、生きた化石と言われ、グレドナー渓谷で発見されたものであり、二億年前には既に、この地域には、このような生物が存在していた証となっている。
<マレッチ城=Schloss Maretsch>
タウファー川に沿った土手づたいの散歩道を北に向かって歩いていくと、珍しく、平地にあって、周囲はブドウ畑に囲まれた四方形の城が見える。マレッチ城である。城の原型は12世紀頃まで遡ることができ、古文書によれば1194年、チロル伯爵の重鎮であった騎士ベルトホルトの命によって城の塔が作られたとか。ワイン畑の中に作られた初期の堅牢な城楼は、今日でも見ることができる。その後、所有者は変遷し、その度に改修が加えられ、レーマー家の所有になってからは、中世紀な城はルネッサンス様式に改築され、今日の姿になった。城の四隅に建つ円形の塔は、このときに作られたものである。内部の壁に描かれたフレスコ画は、命により、当時の時代を表すものが描かれている。1980年代になってからも、若干の改築がなされたが、今日では住居としての役割は終わっている。現在では、城は、メッセとかコンサート、展示会、文化的な催しの場、結婚式などとして使用されており、また、毎年の始めには、ワインの品評会が開催されている。
<ルンケルシュタイン城=Schloss Runkelstein>
ボーツェンの北方、ザルン・タールへの入り口付近に立つのはルンケルシュタイン城である。それほど大きな城ではないが、小高い丘の中腹に建っており、昔は、谷を行き来する商人や旅人たちを監視するには絶好の場所であったに違いない。
この城は抑も1237年、トリエントの司教の許しを得て、この地方の領主ヴァンゲンの命によって建てられ、ホーエン・シュタウフェン家の皇帝フリードリッヒ二世の領土的野心に対抗する防塁として役に立った。しかし、城は早くも40年後にはチロル伯爵マインハルト二世の手に落ちた。
この城が今日、絵画の城として脚光を浴びている基礎を作ったのは、1385年、城の新たな保有者フィントラー兄弟の功績に負うところが大きい。兄弟は、市民から貴族へと出世する意図を秘めて、城の内部をフレスコ画で飾った。その後、城はフィントラー兄弟からジグムント大公の手に渡りその後、皇帝マクシミリアン一世が夏の居城の一つとしてこの城を利用し、内部のフレスコ画を高く評価して改修させた。
城は、更に幾たびか所有者が代わり、1893年になってボーツェン市に与えられ、今日に至っている。城の内部は、騎士の間、浴室、騎士のトーナメントの間、恋人たちの間と続き、それぞれの名前の由来となるフレスコ画で埋め尽くされている。当時としては、宗教色が一切ない絵画は珍しい。回廊を渡ってトリスタンの間に入れば、トリスタンとイゾルデの話が描かれている。
<トリスタンとイゾルデ>
この話は本来、ケルトの悲恋物語「ディアドラとノイシュ」ないしは「グラーニャとディルムッド」に由来すると言われている。「話の原型は」と言えば、年老いた王に嫁ぐことになっていた美しい娘が若い男と恋に落ち、二人は駆け落ちをするが逃げ切れず、若い男は虐殺されて、娘は王の元に戻されるというもの。「ディアドラとノイシュ」では、戻された娘ディアドラは、恋人を思い自殺するが、「グラーニャとディルムッド」では、娘グラーニャは、王と仲直りして幸せに暮らすという筋になっている。いずれにしても、恋に翻弄された若い男は哀れである。
<ジグムンツクロン城=Schloss Sigmundskron>
エッチュ・タールが南東から真南に向きを変えるところ、ボーツェンから4Km西に小高い丘がある。その上に壮大な古城が建っている。ジグムンツクロン城である。ここに城らしきものがあった歴史は古い。ケルト人の時代のものと思われる防壁跡が発見されており、地形的に見ても当時から戦略上重要地点であったことは間違いない。紀元前15年、南方から進軍してきたドルスス将軍指揮下のローマ軍は、ケルト人との戦いでこの拠点を奪取し、これによってチロルの他の谷への侵略が可能になったと推測されている。
10世紀頃、トリエントの司教がここに城を建築させ、領域を管理する拠点とした。1473年に、お金持ちのチロル公ジグムントが城を取得し、堅固な要塞として改築した。城の名前は彼に由来している。
その後、所有者が次々に代わり、城は荒れるに任されていたが、その後、荒廃を食い止め、博物館として生まれ変わらせる工事が進められ、現在では、MMM<メスナー・マウンテン・ミュージアム>として生まれ変わった。
1957年、ここに南チロル人3万5千人が集合し、イタリア政府のパリ協定履行を求め、圧政に抗議する大集会が開催された。この運動は後に、南チロルの自治権獲得運動、更には、イタリアからの独立を目指す南チロル人の抵抗運動として激化した。廃墟の中に残る「白い塔」は、その闘争の犠牲者を奉る記念碑であり、この城自体、あまたの流血の惨事をみて漸く、今日の南チロルの姿が形作られた記念すべき遺構である。
メラーン〈Meran〉
メラーンの辺りは、既にローマ時代には人々が住むようになり、カストルム・マイエンス=CastrumMaienceと呼ばれたが、まだ聞けたところではなく、それ程の建造物は作られていなかった。ゲルマンの諸部族が侵入して西ローマ帝国が崩壊した後、パユヴ、アーレン族がこの地に定住し、農地を開拓して切り聞いたのが街の興りである。
メラーンの名前が初めて文書に現れるのは、857年である。が、まだ当時は独立した都市ではなかった。メラーンの位置付けを変えたのは、チロル伯爵マインハルト二世(1238?-1295)で、彼は、メラーンをチロル伯領の中心地とした。その後、メラーンは1317年に都市権を与えられて、名実ともに首都となった。この頃までには、散歩歩きに適した現在のラウベン・ガッセの原型も出来上がった。
しかしながら、1363年。チロルがハプスブルク家の手に落ちると、メラーンの役割は次第に低下し、代わって、インスブルックがチロルの中心となっていった。15世紀には貨幣鋳造所もメラーンからハルに移され、16世紀から19世紀の間、メラーンはフィンシュガウ・タール、パッサイアー・タール、エッチュ・タールの交差点として地理的に重要でありながらも、小都市のまま推移した。
1830年頃、メラーンは再び脚光を浴びるようになった。その理由は、知識人や医師が、気候温暖で空気が澄んでいるメラーンを転地療養地として評価し、特に肺結核に効果があると推奨したからである。彼らはまた、山羊の乳療法とか、ぶどう療法の効用も勧めた。そのことで、健康回復のために人々が来るようになり、1860年、ブレンナー峠を越える鉄道工事が着工され、その路線は、1881年にはボーツェンからメラーンまで伸びてきて、一般庶民もこの地まで足を運べるようになった。1874年には、クーアハウス(保養センター)が開設されて、メラーンは休暇・保養地としての地歩を固めた(ちなみに、このクーアハウスは、アルプス全域で最も美しいユーゲントシュテール様式=Jugendstil、フランス語でアール・ヌーボ一様式の建築物とされている)。1914年に始まった第一次世界大戦が、南チロルを不幸のどん底に突き落としたのは前述の通りである。イタリアに併合されて苦難の時代を過ごしたが、今では南チロル観光の中心地として毎年、大勢の観光客を集めている。
メラーンのインフォメーションは、クーアハウスの裏側にある。インフォメーションで市内地図を手に入れたら、まずは、エリザベート皇妃公園へ足を向けよう。そこでは、白い大理石で造られたエリザベート皇妃(愛称シシー)の彫像が待っている。椅子に座った姿で、手には読みかけのハイネの詩集を持っている。彫像には、いつも花が添えられており、メラーン市民の守護神のようである。蛇足ながら、一国の皇妃の彫像が当の国以外にもあるというのは、世界を俯瞰しても、エリザベート皇妃像だけではないだろうか。彼女の彫像は、本国のオーストリアは勿論のこと、イタリア、ハンガリ一、スイス、ポルトガル等の各国に見られ、ヨーロッパ中に人気があったことが伺われる。
なかでもメラーンは、シシーに愛された町であった。彼女のお陰で今日の繁栄がもたらされたと言っても過言ではない。何しろ、1870年から72年にかけて度々、彼女はメラーンに滞在し、と言うことは、お付きの者やら関係者やらが一緒に滞在した訳で、メラーンの素晴らしさは一気にオーストリア中に広まった。そればかりか、彼女は、バイエルンの兄弟たちをメラーンに呼び集めたから、彼らの知るところとなり、メラーンの評判はドイツにまで広まった。
エリザベート皇妃公園からパッサー川の南側に沿って逆上り、ローマ橋に至るまでの道が「夏の散歩道=Sommerpromenade」である。丁度、夏の日差しを遮るように、生い茂った木々の枝が道の上を被っている。真夏でもこの散歩道は涼しく、川面で冷やされた風が時おり、肌を撫でていくのも心地よい。
ローマ橋から更に進めば、「ギルフの散歩道=Gilfpromenade」である。ギルフの資金援助で作られた散歩道で、パッサ一川を遡って行けば、川幅がかなり狭まって、ちょっとした渓谷のような雰囲気がある。「冬の散歩道=Winterpromenade」は、パッサー川を挟んで「夏の散歩道」の対岸にある。ローマ橋からパッサ川の北側に沿って、ポスト橋まで下りてくる道であり、「冬の」と名付けられたのは、道端に雪を防ぐアーケードが続いているからである。
アーケードの壁には、故郷の画家が描いたチロルの景色で飾られている。レンハートの「オルトレス地方」やデメッツの「ザンクト・ウルリッヒの町」などが見られる。この冬の散歩道では時折、がらくた市が開かれる。どこから取り出してきたのか、古道具から古着、骨董品の類などを売る出店が、道の両側に沿って並ぶ。
ポスト橋まで来たら、右に折れて市内へと進む。入り口は「ボーツナ一門」である。ここから、昔ながらの建物が並んでいる旧市街に入る。門を潜った小道の両脇には、ファッション専門店が並んでいる。奇抜な下着の広告もあり、それらを眺めながら上って行けば、突き当たりは地区教会である。教会前の小さな広場には、香料品の屋台や果物屋の屋台が並んでいる。
この広場から西に進めば、高級ブテッィク、土産物屋からパン屋まで並ぶメラーンーの繁華街「ラウベン・ガッセ=Laubengasse」である。ラウベン・ガッセは、通路の上に屋根が続いていて、雨でも雪でも傘なしで行き交うことができる便利な構造になっている。道の両側の家々は、愛らしい張り出し窓で飾られている。ラウベン・ガッセの真ん中辺りに市庁舎があり、そこにちょっとした広場があり、果物市場になっている。
この広場に面して建てられているのが「ランデス・フュルストリッヒェ・ブルク=Land esfuerstliche Burg (領主の館)」である。15世紀頃に建てられた「お金持ちのジギスムント公」のメラーンにおける居城であり、保存状態の良好な城である。城と言うには珍しく、城を囲む城壁がないので、住居という感じである。16世紀まで、城は領主の住居として使用され、皇帝マクシミリアン一世も1516年に宿泊している。その後、城の所有者は何世紀にわたって何度も替わり、1875年に、メラーン市が所有することとなり、1878年から1890年までの大規模な改修工事を経て一般に公開されることとなった。今日では、博物館として機能している。博物館としての見所は、木製の化粧板を張り巡らした部屋、色鮮やかなタイル張りのストーブ、召使いの部屋、姫君の部屋などであり、これらは、当時のままに保存されていてる。また、当時の槍とか矛などの展示もある。16世紀のフレスコ画で装飾されたカペレも一見の価値がある。
城のある広場の横から、ドルフ・ティロールへ登るリフトが出ている。また、リフトの終着駅からはメラーンに下ってくる道があり、これは「タッパイナーの散歩道=Tappeine rweg」に続いている。したがって、タッパイナーの散歩道を歩いてみたいが、体力も根性もないという人は、一旦、リフトに乗って、そこから、なだらかな道を下ってくればいい。運動したい人は、リフト駅横の広場から階段状の登る道があり比較的、楽に上まで上がれる。それでは物足りない健脚向きには、地区教会の裏から始まる急な階段が利用でき、これがタッパイナーの散歩道に続いている。ちなみに、犬は楽々と健脚コースを登っていく。
タッパイナーの散歩道は、メラーンとドルフ・ティロールとの間の南斜面の中程に作られた西へ伸びる散歩道で、メラーンやフィンシュガウ・タールを一望の下に見渡せ、道の途中では様々な植物に出会え、小ぎれいな農家あり、教会の眺めありの誰もが楽しめる散歩道であり、気分爽快になること請け合いである。ちなみに、この散歩道は、引き続きアルグンダー・ヴァールヴェーク=Algunder Waalwegと呼ばれ、更にパルチンス方向に続いていて、全長は約8km、所要時間は片道約2時間半程である。
ラウベン・ガッセを抜けて、突き当たりの道レンヴェーク=Rennwegを右折すれば、国民銀行の建物の裏手に「女性博物館=Frauenmuseum」なるものがある。博物館は、オーストリアのフォア・アルベルク州出身の熱狂的な蒐集家エヴェリン・オルトナーが、1988年に創立した「服装及び女性たちのおしゃべりのための小さな博物館」が元となっている。今では、展示品が増え、現在ではメラーン観光の目玉にまでなっている。国際的にも知られ、女性のための博物館の世界的ネットワークの中心的存在となっている。女性用衣服の歴史が、コルセットや下着からスカート、ドレス、装飾品に至るまで、また女性に関係ある調理の道具類、医療器具なども展示されている。また、特別室では、女性にまつわる歴史的な事柄に関して説明するコーナーがあり、魔女裁判の特集が展示されたこともあって、魔女裁判の開始と終焉、その犠牲者の数などが地図上で示され、魔女関係の書物が自由に閲覧できるようになっていた。
レンベークに戻り、南方向に歩いて行くと、左手に「マミング宮殿博物館=Palais Mamming Museum」がある。1900年に開館された南チロル最古の博物館で、メラーンの医師フランツ・インナーホーファーが蒐集した品々が展示されており、メラーンの歴史的発展の様子が概観できる。また、外国から蒐集されたものもあり、「エジプトのミイラ」とかスルタンから頂いた「スーダンの武器類」などもある。貴重なのは、ペーター・ミッテルホーファーが世界で初めて制作したタイプライター(後述)である。
前述したとおり、メラーンは昔から療養地であり、今日は更に保養地として発展し、それを象徴するのが、2005年に新装されたテルメ・メラン=Therme Meranである。パッサー川の南側の広大な敷地に建築され、温水プールの数は15。8つのサウナ、トルコ風呂、フィットネス・センターなどを備えた施設で、夏は屋外プールも開放され、年中無休で、正に「療養公園」と言った感じである。メラーンの地下水は、ラドンを含み、様々な治療に使われている。わけても、温水の蒸気は呼吸器粘膜に効用があり、呼吸を楽にするとのお墨付きで、肺や気管支の疾患がある人には最高の場所である由。旧施設の時代にも、フランツ・カフカ、リルケ等の作家やエリザベート皇妃などかが、客として訪れていたとか。
パッサ一川の手前の道フライハイツ・シュトラーセ=Freiheitsstrasseを右折し、道なりに進めばメラーン駅である。メラーン駅は、各方面へのバスの始発駅でもあり、北のパッサイアー・タール、西のフィンシュガウ・タールへ行くには、メラーン駅始発のバスに乗ればいい。なお、鉄道線は、2005年には、オーバー・フィンシュガウのマルスまで延長され、二両連結の可愛い電車が庶民の足となって活躍している。メラーン駅前の公園には、郷土の英雄アンドレアス・ホーファーの立像があり、市民を見守ると同時に、旅行客を出迎えてくれる。駅の前のキオスクでバスの切符を買い、1B番か4番に乗って「トラウットマンスドルフ城」へ足を向けてみよう。
<トラウトマンスドルフ城=Schloss Trauttmansdolff>
この城が建てられているところには既に、古くから居住の跡があって、その後は大農園となっていたが、14世紀頃、城として建築された。1543年に、城は貴族トラウトマンスドルフが購入し、拡大が図られたが、その一族が絶えた後は、城は荒れ放題となった。1846年、シュタイア一マルク伯爵が城を購入し、再建された。
1870年の10月。エリザベート皇妃が、皇女二人を連れて、この城に滞在した。彼女はメラーンの静かな保養地がすぐ気に入り、翌年の6月まで滞在し、更にその年の冬にまた訪れ、春までメラーンで過ごした(二回目はロッテンシュタイン城に滞在)。メラーンは、病気がちの皇女マリー・ヴァレリーの健康にも良く、シシーは、この城を拠点として小さな砂利道を散歩がてらに市内まで下りて行った。その道が後述する「シシーの散歩道」である。
第一次世界大戦の後、城は幾度か所有者の変遷を見たが、1977年、最終的に州に帰属することとなった。トラウトマンスドルフ城の庭は、現在、植物園になっている。この植物園は、メラーン観光のハイライトであり、2005年には、イタリアでもっとも美しい庭園との評価を得ている。12ヘクタールの園内には、世界各国から集められた植物が観光客を引きつけている。園内は、四つの区画に分けられており、その一つ「森林公園=Waldgaerten」には、北アメリカや東アジアからの針葉樹、生きた化石と謂われるシダ類が植えられ、カラフルな羽根を纏ったオウムが出迎えてくれる。「太陽の庭= Sonnengaerten」と名づけられた区画は、城の下方にあり、陽が注ぐ斜面にはラベンダーの魅惑的な香りが漂っている。「南チロルの風景=Landschaften Suedtirol」の区画には、南チロルの様々な植物が植えられており、特記すべきは、7000年の前のブドウの種のレプリカである。四つ目の「水と花壇=Wasser-und Terrasengaerten」には、睡蓮とか蓮の花が咲き誇っている。
植物園のなかには、シシーのプロムナーデがある。標識に従って歩いていけば、金色のシシーの胸像に出会う。シシーの胸像の横には、<ブリレ>と呼ばれる展望台に上る階段がある。登っていけば、岩山から鉄橋が突き出ているのが見える。まるで、空中に浮かんだ展望台で、高所恐怖症でなくても足元が覚束なく、時には揺れたりして、観光客たちは顔をひきつらせる。
<州立ツーリズム博物館=Landesmuseum fuer Tourismus>
城の建物内部は、2003年に開館されたツーリズム博物館となっており、チロルが観光地として発展してきた200年間の流れが展示されている。中には鉄道模型もあり、見て回るだけでも結構、楽しい。丁度、尼さんのグループが見学しているのに出会った。若い尼さんも年老いた尼さんも皆、ニコニコしながら見て回っていた。「こっち。こっち」そんな声が聞こえ、釣られて上がっていくと、そこには等身大のシシー像があって、尼さんが記念写真に収まっていた。尼さんだって、はしゃぎたくなる博物館である(2018年現在、シシー像がある渡り廊下は、通行禁止となっている。)。
<シシーの散歩道=Sissi-Weg>
城からメラーンの市内へ戻るには、「シシーの散歩道」がいい。城の駐車場から道筋を示す表示が掲げられているので、それに沿って行けば迷うことはない。小川を渡り、林檎畑、葡萄畑の間を通って、なだらかな上り坂を歩いて行くと、果樹園の中にポツンと現れるのは、「ピエンツェナウ城=Schloss Pienzenau」である。1394年に建てられた城で、元々は、バイエルンにあるエッタール修道院の修道僧の保養所として使用されていた由。それは18世紀まで続いて、その後、持ち主が何度か変わり、今では団体や家族の祝い事や行事のための高級レストランに様変わりしている。
ピエンツェナウ城の正門から出て右手に折れ、木々の生い茂る道を潜るように進んで、辺りが開ければ、次に見えるのは「ルバイン城=Schloss Rubein」である。この城は12世紀に建てられたとかで、シシーは、1870年の秋に宿泊したことがあるとか。余談であるが、当時の城の持ち主であるクリストマンスは、ドロミティ・アルプスを観光地として開拓するのに多大な功績のあった人物で、彼の甥のコンスタンティンは良き案内人としてシシーに同行した由である。城は、現在、個人の所有となっているために残念ながら、内部はおろか庭の見学もできない。
ルバイン城から標識に従い、道がいよいよ狭くなってきたら「アンズィッツ・ライヒェンバッハ城」の横を通り抜けて、ブルンネン・プラッツ=Brunnenplatz(広場)へ出る。アンズィッツ・ライヒェンバッハ城は、14世紀に建てられ、1854年から1902年の間、フランツ・タッパイナーが住んでいた。彼は、保養治療を初めてメラーンに持ち込んだ医師で、メラーンを保養地として開発するのに人力を尽くした。前述のメラーンを見下ろす「タッパイナーの散歩道」は、彼の音頭により、彼の資金提供を受けて造られたものである。
ブルンネン・プラッツの北側にあるのは、13世紀に建てられた「ロッテンシュタイン城」。皇帝フランツ・ヨーゼフ一世の弟であるチロル大公カール・ルードヴィッヒが1863年に城を買い取り、シシーは二度目の滞在のとき、この城を利用した。広場から下る細い道「キルヒシュタイク」を抜けて行けば、ホテル・バヴァリアの横に出る。正面入り口の両脇には、二頭のライオン像がある。ライオンはバイエルンの紋章であり、これを見たシシーは、故郷や弟のカール・テオドール公を懐かしがったということである。ちなみに、カール・テオドール公は、この地に来た際、眼科医として無料で住民の目の治療を施し、メラーン市民から感謝されたという逸話が残っている。
ホテル・バヴァリアから下ってパッサ一川を渡る。石造りの立派な橋は、ローマ橋である。昔は木造の細い橋が架かっているだけだったが、19世紀の終わりに現在の橋が建てられた。この橋を渡れば、そのまま冬の散歩道に繋がっている。シシーの歩んだ道は、冬の散歩道から更にクーアハウスに進み、そこから引き返して終点はエリザベート皇妃公園である。のんびり歩いても約1時間の散歩道。メラーンの良さが満喫できる散策であること、請け合いである。
メラーンの祭事と言えば、毎年10月の第三週末に開催される「ワイン祭り」がある。このお祭りは、年の初めから農園でぶどう栽培に勤しみ、今や収穫の時期を迎えて労働から解放されたことを祝う祝典で、そのハイライトは、近隣遠方を問わずに集まってきた楽隊や着飾った市民たちの行進である。騎乗の騎士たちは、威風堂々とサーベルを引っさげており、猟師たちは、鉄砲を肩に担いでメラーンの市中を練り歩き、装飾を施した馬車とかトラクターなどが後に続く。
国際的な「ワインと食の祭り」も1992年以来、毎年秋に、クーアハウスの前で開催されている。シェフたちは、チョコレート、パス夕、トリュフ、チーズ、コーヒーなどの食通の胃袋を満たす美味しい料理を提供し、美食家たちは、祭りの間中、ここかしこで腹鼓を打つ。世界中から集まってきたワイン生産者たちは、丹精込めた美酒が酒飲みたちの喉をすんなり通っていくか気に掛けている。この「ワインと食の祭り」は今や、イタリアのぶどう栽培学、葡萄酒醸造学とって、重要なイベントとなっている。
<シェンナ=Schenna>
メラーンの高台にある保養地として有名なのは、シェンナである。この高台に、村を見下ろすように建てられているのは「シェンナ城」。1346年に当時のこの地の貴族ペーターマン・フォン・シェンナの命によって建てられた城であるが、歴史的、政治的観点からは、別に重要な意味はなかった。その後、所有者が何度か変わって、1844年、ハプスブルク家のヨハン大公(1782-1859)が購入した。
彼は1809年、アンドレアス・ホーファーと組んで対ナポレオン闘争を指導したことで知られているが、1819年に、アンナ・プローホル(1804-1885)を見初めた。彼女が郵便配達吏の娘であったことから、二人の結婚は許されなかったが、その後、兄のフランツ一世は、ヨハンが皇位継承権を放棄することを条件に結婚を許し、アンナはメラーン伯爵夫人の地位を得た。二人の子孫は、メラーン伯爵を継ぎ、城は現在、彼らの子孫が所有している。因みに、ヨハンとアンナの二人は、シェンナの地区教会裏手にある「マウゾレウム=Mausoleum」で仲良く眠っている。
愛の舞台となった城ではあるが、中世の趣をそのままに残しており、ロマンティックという訳ではない。解説つきで城内を覗けば初めに、各種殺戮用具である武器庫に案内される。続いて騎士の間、寝室、食堂などがあり、17世紀の著名な画家シュテファン・ケストナーの絵で占められた部屋もある。また、チロルの風景画を集めた部屋、そしてヨハン大公の縁だろう。アンドレアス・ホーファーに関する絵画を集めた部屋もある。それらの絵はオリジナルとかで、一見の価値がある。
ブリクセン〈Brixen〉
ブリクセンは、アイサック川とリエンツ川が合流する要所に発展しきた南チロル第三の都市である。市として認められたのは、南チロルでは最も古く、901年9月13日であり、当時の名前は、プリヒスナ=Prichsna。西ローマ帝国の崩壊後は他の地方と同様に、諸民族が入り乱れたが、西暦590年頃から、この地方は、バイエルン公の支配するところとなった。その後、バイエルンはフランク王国に吸収され、カ口リング王朝最後の王ルードウィッヒは901年、ゼーベンに司教座を置いていたザカリアスにこの地方を与えた。
970年頃、後継の司教アルブインが、司教座をゼーベンからブリクセンに移し、ブリクセン繁栄の基礎を作った。1027年、皇帝コンラート二世は、爵位とともに、下インタール伯領とノリタール伯領を司教ハルトヴィヒに与え、司教は、ブリクセンをその領域一帯の首都と定めた。しかし、その後、チロル伯爵が台頭し、13世紀頃までには地域の大半がチロル伯領に組み入れられ、ブリクセンの司教が支配する地域は、首都のブリクセン、クラウゼン、ブルーネックその他の小領域でしかなくなった。
以上のような経緯を経たブリクセンは、チ口ルの他の地域と異なり、司教という「聖職者が領民を支配する」という特異な形態を取ることになった。一般的には、司教は「神の使い」だから領民に善政を施したと考えられがちであるが、実体はその逆であった。司教は、他の領主同様、領民に貢租を課し、その上に教会税として収入の十分のーを取り立てた。また、移住税、死亡税などを課し、共同体の用益権の制限などの経済的圧迫を加え、結婚の制限まで行った。その一方で、贖罪を行うことにより金品を得るなど、やることなすことは卑劣極まりなく、領民の不満は、他の地域よりも先鋭化していた。
1525年、ドイツ全土で発生した農民戦争は、チロルではブリクセンが一番、激化したのは、ミヒャエル・ガイスマイアー<前述>の指導もさることながら、このように領民の間に不満が渦巻いていたからであった。そんなブリクセンではあるが、中世の時代を通して、芸術と教育の中心地であった。近代の幕開けとともに商業、手工業が発展し、力を得た市民は司教座からの独立を目指して自治権獲得に乗り出した。その一方で、司教座は傭兵の維持に多大な負担が強いられて弱体化し、1803年、ハプスブルク家に教会の財産が没収された後は、ブリクセンは地方の小都市に過ぎなくなった。
しかし、温暖な気候と風光明媚な地形の恩恵をうけて観光産業が発展し、それによってもたらされる収入により、市は経済的に立ち直った。以上のような歴史的背景を有するブリクセンであるからして、見どころと言えば、まず司教の住処であったホーフブルクを上げなければならない。ブリクセン駅に下り、駅前広場から左へなだらかに下る道(バーンホーフ通り)をどこまでも真っ直ぐに進めば観光案内所に突き当たり、その裏の高い塀に囲まれた城がそれである。塀の横に庭園へと通じる小道があり、失礼してそこから入る。庭園を横切って門から出れば、右手に正門が見える。
ホーフブルクは、1595年から1610年にかけて、ブリクセン司教の居城として建築されたもの。一部とは言え、正面入り口に堀があるのは珍しい。ホーフブルクには、ニつの博物館がある。一つは、キリストの降誕の様子を題材にした博物館で、小さな木彫り人形が表情も豊かに生活している様が展示されており、その内容は多岐にわたっている、特に、第三室の聖書の部屋は圧巻であり、当時の風俗、召使いたちの仕事、結婚式の様子などが人形劇のように配置されている。ヘロデ王の幼児虐殺の場面もある。それらの演出に加わっている人形たちは、総数、約一万体に及ぶ。
もう一つの博物館は、宝物殿となっている。ホーフブルクそのものの歴史を示す価値あるインテリア用品、織物、地図、文書などが展示されている。また、歴代の司教たちが集めた彫刻や絵画、高価な金銀の細工類なども展示されており、一際、人目を引くのは、1000年頃のアルブインのミサの衣装=Albuinkaselである。ピザンティンの絹で織られた礼拝用の衣装で、当時のローマ法王からブリクセンの司教アルブインに贈られたものだとか。キリスト教とは無縁の者にとっては、唯々、これらの宝物を集められた司教の財力に感心するばかりである。この博物館での普遍的かつ人間的な彫刻といえば、キリストに授乳しているマリアの像くらいか。その他、チロルの現代画家たちの絵も僅かながら展示されている。
ホーフブルクの正門前には、千年記念柱が建っている。901年に司教ザカリアスがこの地方の支配者となってから千年目の記念及び1809年のフランス・バイエルンに対する闘争百年を記念して建てられた塔である。柱の一面には、後者の戦いで逮捕されたアンドレアス・ホーファーと、許しを乞う彼の妻の姿が描かれている。千年記念柱前からドーム広場に出れば、二つの塔を持つドーム教会が聳えている。教会は1200年頃に建立され、現在の建物は18世紀中頃に再建されたものである。さすがに大きい。ヴァチカンのサン・ピエト口寺院には敵わないが、それでも大きい。司教座が置かれていた昔の威光を今に伝えるかのようである。
教会内に入ってすぐ右手に、ザカリアス司教の像がある。手にした石版に彫られた文字はラテン語で、「さて、血を分けた兄弟よ。お前のために余は墓の中からお前の頸を解き放ってやろう」と書かれている由。正面祭壇の左手に紫色の布で覆われた大理石造りの立派な椅子が置かれているが、司教だけが座れる椅子である。日曜日の朝。丁度、ドイツ語によるミサが始まったが、この地方の保守的な風土を反映してか、参列者は続々と訪れ、終いには、椅子席が全て埋まるほどに集まった。
ドーム教会の正門を出て左手に行くと、今は抜け道の通路と化した回廊がある。14、5世紀のもので、壁といわず天井といわず、聖書の記述を素材としたフレスコ画が描かれており、今日でも一部は色彩も鮮やかである。楽園を追われるアダムとイブの絵もある。ドーム教会から出て右手に進めば、地区教会との間に庭園がある。その庭園に面して、戦没者記念碑がある。二度の世界大戦の際、この町の出身者で犠牲になった者、行方不明の者の名前が列記されている。
ドーム広場に面した市庁舎の左隣りに、喫茶店「ゴルデネン・口ーゼ」がある。そこで一服してトイレに行けば、そこには中世のおどろおどろしい武器、拷問具の類が展示されている。「拷問及び異端審問に関する博物館」であり、鉄裂の打撃機や拘束具から、変わったところではガラス・ケースに収められた貞操帯もある。曰く、「婦人用貞操帯もしくは拷問帯。不倫またはソドミーの罪を犯し、死刑の判決を受けた婦人に施したもの」とある。が、見たところ馬鹿でかい。ちゃんと着用できたのか疑わしく、実用的ではなかったような感じである。この喫茶店には、その他、チロルの英雄アンドレアス・ホーファーや農民指導者ミヒャエル・ガイスマイアーの肖像画もある。コーヒーを飲みながら、チロルの歴史の一端を垣間見ることができる。
ドーム広場から北側に出て左手の小道に入れば、クライネ・グラウベンに出る。名前の通り実際、ほんの僅かな道のりだが、古くからの建物が並び、当時の旅龍のフィンクやフィンスターヴィルトも軒を並べている。クライネ・グラウベンを真っ直ぐに歩けば、グローセ・グラウベンに突き当たる。広い道の両側は、衣料品店から銀行、電化製品の店と並んでいる。
ドーム広場から今度は東側への小道をアイザック川に向かって進めば、「薬剤博物館」がある。博物館は、市立薬局ピール=Peer内にあり、頭文字を取ってPMBと呼ばれている。ここには、400年前からの薬剤製造方法とか製造に使われた器具の類いが展示され、当時の治療法、薬学など、そして、「ワラジムシを甘く煮たものは熱冷ましに効果がある」といった迷信治療の方法などが分かるようになっており、効果がありそうな金メッキの錠剤も展示されている。薬学との関係は不明だが、博物館には、アルマジロの頭、大鹿の蹄、エジプトのミイラの破片とかも展示されている。これらも、迷信治療薬の類いだろうか。ここは、数世紀にわたり進歩してきた治療薬の宝庫であり、19世紀に入るまでは、薬剤は、薬剤師の個人的な労力によって製造されてきたことが見て取れる。また、博物館では、薬学に関する催事も行われる。2015年には、「毒草一美しいが危験」、2016年には、「鉱物より製造される薬品」の展示会が催された。
市内の散策から離れ、アイザック川治いに下って行けば、ホテル・グリュナーバウム辺りで左手から流れてくるリエンツ川との合流地点に達する。川沿いの長閑な散歩道は、早朝の散歩に丁度良く、夏の暑いときでも川面から涼しげな風が送られて気持ちがいい。
ザイス〈Seis〉
ザイスは、シュレルン山塊の麓の村。チロルと聞いて、人々がイメージする光景そのものが、正に目の前に広がっている牧歌的な村である。シュレルン山塊への登山基地、ザイサー・アルム高原散策の出発点であり、ホテルの数は毎年、増え続けている。観光客はここで数週間、滞在し、冬はスキーに明け暮れ、夏はハイキングに精を出す。村は、シュレン山塊のなだらかな頃斜地に広がっており、中心はヴォルケンシュタイン広場。観光案内所もその近くにある。
村の見どころとしては、あまたの教会があり、どっしりした聖十字架教会、赤壁が映えるマリア・ヒルフ教会などがある。教会に縁のない観光客向けには、シュレルン山塊の翠微ハウエンシュタインの森にひっそりと建つ廃城、ハウエンシュタイン城とザーレック城がある。前者は、この辺りの当時の領主ハウエンシュタインの命により、12世紀頃に建設され、15、6世紀に拡充されたものであり、その後は所有者が転々として、オズヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタインのものとなったとか。いずれの城へも、ハイキング・コースが通じている。
村にはまた、観光客向けに散策コースが幾っか設けられている。その一つに「ザクセン王の散歩道」がある。コースは、ヴォルケンシュタイン広場から出発し、ザーレック城下にあるホテル・ザーレックで一服し、回遊するものであり、コースの名前の由来は、ザクセン王国最後の王フリードリッヒ・アウグスト三世が1903年から1914年まで屡々、家族とともにホテル・ザーレックに滞在したことによる。因みに、「体験と詩作」で知られるドイツの哲学者ヴィルヘルム・ディルタイ(1833年生)は1911年10月1日、このホテルで亡くなっている。村には「糸紡ぎ女たち」で知られる南チ口ルの著名な肖像画家オスカー・ヴィーデンホーファー(1888-1987)の工房が残されており、そこを回る散策ルートもある。
ザイスの村では毎年、五月下旬乃至六月上旬の週末に「オズヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタイン・リット」と名付けられたお祭りが行われる。中世の騎士祭りの類で、初日には、中世の衣装に身を包んだ、人々がメイン通りを練り歩く。先導は、ザイス村の音楽隊。続いて、花車やこの地方の村長さんたちの行列、前年度の馬術競技の優勝者の誇らしげな雄姿などが続き、見目麗しき乙女が馬上、肅然として進んでくる。その馬が、馬の林檎を落としていくが、乙女は知らん振りして過ぎていく。行列は更に続き、仮装行列となってプレーゼルス城主夫妻、カステルルート城主夫妻、最後はザイス村の白十字架で締め括られ、ヴォルケンシュタイン広場に参集して終わる。
二日日は、中世の馬術競技が行われる<於、プレーゼルス城>。この馬術競技の圧巻はラビリント(迷宮)と呼ばれる競技であり、これは、四人がそれぞれ馬に乗り、横並びで一本の棒を握り、スタート地点から駆け出し、中間点で今度は一人づつ馬を疾駆し、迷路状に作られた馬場を素早く走り抜け、四人が順次、走り抜けたところでまた並列し、一本の棒を握って出発点まで戻り、所要タイムを競うものである。競技参加者には、女性群も含まれている。この祭りの最中、屋台が出るが、売り子も中世風の衣装を纏ってる。
ザイスから南へ数キロ走ったところに、ゴルフ場ザンクト・フィギル=St.Vigilがある。本格的な18Hのゴルフ場で宿泊施設も整っている。コースに出れば、間近にシュレルン山塊を展望でき、自然と力が入って豪快なショットが期待できる・・訳がない。
<ザイサー・アルム=Seiser Alm>
ザイサー・アルムは、グレドナー・タールの南側にある高原地帯。ここへの基地としては、シュレルン山塊の麓のカステルルート、ザイス、フェルス・フィエなどがあるが、ザイスの村からザイサー・アルムのコムパッチまでケーブル・カー(ザイサー・アルム・バーン)が開業したことにより、ザイスの村が断然、便利になった。ザイサー・アルムは、ヨー口ッパ最大の高原地帯である。大地から浮き上がったように広がる高原は、平均高度二千メートル。広さは64平方キロ以上ある。
ここは一年中、季節を問わず楽しめるところ。春ともなれば辺り一面、お花畑であり、夏は避暑地として賑わい、秋ともなれば高原散策の家族連れが後を絶たず、冬となれば勿論、スキー客で満たされる。要するに、自然と戯れる人たちの天国である。高原の中心となるのはコムパッチの村=Kompatsch。ここに案内所があり、ザイサー・アルムでの遊び方を教示してくれる。散策のための馬車もあり、これに乗って更に奥を目指せば、目の前にラング・コーフェルが立ちはだかる。ここから見るラング・コーフェルは、南側にプラット・コーフェルを従え、頂きが二つになっている。
コムパッチの北側にある台地は、プフラッチ=Puflatsch。なだらかな高原の散歩道であるが、その先端に、通称「魔女のベンチ=Hexenbaenke」と呼ばれている場所がめる。このベンチは、一風変わった岩石の一群から成り立っており、敷石が露出したように見える。登り行く道筋は階段状になっており、その規則正しい配列から、何時の時代かは不明であるが、人の手が加わったものと考えられている。ベンチに立って下を覗けば、目が眩む絶壁で、大地はグレドナー・タールに向かってスパッと落ち込んでいる。因みに、何故かここには防護柵がない。落ちたとしても当局にお咎めはなく、下を覗き込むのは、個人の責任において為すこととなる。
ところで、ここが何故「魔女のベンチ」と呼ばれているのか。それには、この地方に伝わる伝説とか民話とかが関係してくる。それらの話は、自然の不思議な力と絡められた魔法が主題となっている。シュレルンの魔女たちは、多くの伝承では意地が悪く、日照りとか雹を降らせるとかの「悪天候を呼ぶ」として恐れられていたが、その一方で、マルタと呼ばれる人?のいい親切な魔女もおり、彼女は特に子供達に優しかった。要するに、性格の悪い魔女もいれば良い魔女もいた。また、魔女たちは、長年の経験から薬草の知識に長けており、病気を治癒する術を熟知していた。その魔女たちは、プフラッチの石積み辺りで集会〈今で言う情報交換会〉を開き、飲食を伴にして踊りあかしたと言われ、それ故に、その石積みの場所が「魔女のベンチ」と呼ばれるようになった。
この魔女たちが薬草を使って病気を治癒する知識は、現代にも通用する極めて科学的な療法であるが、魔法は神の専売特許であって「信ずる者は教われる」とする中世の時代にあっては、邪悪な施術であると見做された。それ故に、魔女の概念は一方的に悪魔=Daemon,Teufelと同一視されて糾弾の対象とされ、それが嵩じて、魔女のような特別な知識を持つ婦人達が槍玉に挙げられ、犠牲になったのは、後述「魔女裁判」で述べる通りである。
コムパッチから南西方向に目を向ければ、どっしりとした研ぎ石のようなシュレルン山塊=Schlern(最高地点はペッツ2563m)が横たわっている。その平たく見える台地は東方向に長く尾を引き、まるで馬の背のように見える。反対側の西方に伸びたところは切れ込んで、針峰となっているのは、ザントナー・シュピッツェ(2413m)である。さて、このシュレルンは、登山には手頃な高さでハイカーに人気があり、夏ともなれば頂上を目指す人々が群れをなして訪れる。起点となるのはコムパッチから近いザルトナー・ヒュッテ(1825m)で、北壁に治ってただひたすら登っていけば、二時間程で台地の端に辿り着く。ここまで登れば、シュレルンの馬の背の形をした鞍部が東に伸びているのがはっきり分かる。
ここからシュレルン・ハウス(2450m)までは、あと半時間。シュレルン・ハウスでは飲食ができ、宿泊もできるようになっている。更に頂上のペッツへは、残り20分。頂上に立てば、南西の方向にはボーツェン市街。その右手北方向には、深い谷の向こうに屏風のように切り立ったプエツ・ガスズラー山塊の壁面。東側には、ザイサー・アルムが見渡せる。ザイサー・アルムの先には、ラング・コーフェル。そして、南側にはローゼン・ガルテン山塊。自分の足で登り詰めた達成感とともに味わうド口ミテの山々は、美しく、険しい。
<フェルス=Voels am Schlern>
ザイスの村からシュレルンを周回するように走る高原道路を走っていけば、始めにフェルス・フィエの村に辿り着く。村の雰囲気はどことなく、要塞風。高台にある教会を中心として家々が幾重にも軒を並べ、広場に通じる通路も階段も狭い。教会前広場に出れば気のせいか、寒々とした雰囲気が辺りに漂う。この村は、チロルで初めて魔女裁判が行われたことで有名である。
1510年のこと、9人の農婦が魔女として告発されて裁判にかけられた。勿論、その当時の裁判であるから「法の適正な手続き」などという理念はなく、彼女たちは拷問を加えられ、苦しみの中で「魔女である」と自白した。それらの調書は当初、プレーゼルス城に保管されていたが、今ではインスブルックの州立博物館に収められている。曰く、「私は悪魔と契りました。シュレルンのある場所で行われた悪魔の集会に参加し、悪魔に命じられて踊り、笛を吹き、喇叭を鳴らし、大いに飲み、食べました。集会は、それは大規模なもので、まるで蝿が群がっているようでした。私は悪魔に身を委ね、悪魔の言いなりになって雹を降らせ、日照りを呼び、家蓄を崖から突き落とし、嬰児を殺しました」そのように自白した農婦は「魔女である」と認定され、立木に縛り付けられ、足元い薪を積まれて、生きながら火炙りの刑に処せられた。
今日の常識からは全く、野蛮としか言いようのない裁判が真面目に行われ、人は人でしかないのに、魔女と認定されて焼かれた農婦たちは、哀れとしか言いようがない。が、今日、それが観光の目玉になるとは、何と因果なことであろうか。シュレルンの魔女たちは、今ではこの地域のシンボルとなり、人々を呼び寄せるキャッチフレーズになっている。焼き殺された魔女たちは一体、どんな心境で眺めているのか複雑である。
<魔女裁判>
魔女裁判ないし魔女狩りは、十字軍の遠征と並んで、キリスト教史における最大の汚点と言われている。いずれも、ローマ教皇が指導的な役割を演じ、世俗領主との利害が一致して大きなうねりを形成し、そのために十字軍の遠征では、罪のない異教徒が暴虐、略奪の嵐に巻き込まれ、魔女裁判では、同じ教徒が同じ教徒に売られて悲惨な目に遭い、一神教が有する限界を露骨に示した残虐極まりない事例である。
魔女裁判の事の起こりは1484年12月5日、ローマ教皇イノケンティウス8世が発した「魔女教書」から始まる。「限りない愛をもって要望する」と題されたこの教書において、教皇は、北ドイツの幾つかの地方で魔女が横行していることを憂い、審問官であるハインリッヒ・インスティトリスとヤーコプ・シュプレンガーの両名が行う魔女狩りに協力するよう各司教や管区長に説いた。
この両名は1487年、「魔女に対する鉄槌」なる偽書を著し、魔女の行いを列挙して、これを取り除くことが信者に課せられた義務であるとし、魔女は如何なる特性を有しているかを詳細に説き明かして後の魔女裁判の基礎を作り上げた。魔女として告発された者は始め、魔女であることを告白するように勧められる。が、認めれば即、火炙りであったから、告発された者は否認せざるを得ない。
否認した者に対しては、白状させるために拷問が許された。まず、身体に魔女の印があるか否かを調べるために全裸にされ、体毛は隅々まで剃られて入念にチェックされ、次いで、後ろ手に縛り上げられて吊り落とされ、数々の拷問を経てもなお自白しない場合は、脇の下を松明で炙られることまでされ、大抵の女性は苦痛に堪えかねて魔女であることを認め、審問官の言いなりに告自し結局、火炙りにされた。告発されたらまず助からないという、まことに救いようのない似非裁判であった。尤も、裏では賄賂が横行し、魔女との嫌疑を受けた娘を救うために、教会に献金して命乞いした父親がいたという話もあり、魔女裁判を利用して政敵を抹殺するというあくどい輩もいた。
また、魔女とされた者の財産は没収となったから、教会にとっては割りのいい錬金術でもあったことが伝えられている。因みに、この当時はプロテスタントも勃興したが、マルティン・ルターでさえ、無知としか言いようがないが、「魔女というのは、悪魔と寝るような悪い女で、人の牛乳を盗み、雷雨を起こし、箒にまたがって空を飛ぶ。身体を麻痺させたり、漏水させて殺したり、夫婦には淫乱を勧め、その他、悪事となれば何でもやる」と語っている。事、魔女に関する限りは、新教もカトリックもなく、信者は告発を恐れて身の縮むような思いで暮らしていたようである。
それでは、「信者であることを止めればいい」と考えるのは後世の人間の考えで、アフリカや中南米に侵略し、殺戮の限りを尽くしたキリスト教徒を見れば分かる通り、異教徒は抑も、人間扱いされなかった。従って、信仰を捨てた者は、社会的保護の対象外となり、彼らを殺したとしても、まともな裁判は為されなかった。一神教が世俗の権力と結びついたときの怖さは、この点に於いて明瞭である。
ブルーネック〈Bruneck〉
ブルーネックは、「プスター・タールの真珠」と呼ばれているこの地方の政治的、経済的な中心地である。1251年、ブリクセン司教のブルーノが、ザンクト・口レンツェンを拠点とするプスター伯爵に対抗するために、ク口ウン平原の麓に建設を命じて出来た都市で、ブルーネックの名前は彼にちなんで付けられたもの。この地は、中世の時代、アールン・タールの銅の採掘によって大いに繁栄したが、今日、住民は農産物生産、観光業、伝統工芸品制作などで生計を立てている。
市の見どころは、「ブルーネック城」とその下の旧市街である。駅を下りたら真っ直ぐに伸びる道を歩み、突き当たりのザンクト・口レンツナ一通りを左折してそのまま進めば、グラウベン通りに通じる。観光案内所は、グラウベン通りに入ってすぐの左手建物一階にある。グラウベン通りに入って右手に小さなチュルチェントハーラ一公園があり、公園に面して塔が立っている。この塔から続く道がシュタット・ガッセであり、旧市街である。道の両側は商店街が続いており、買い物客が行き来するブルーネックの銀座である。
シュタット・ガッセから、更に先へ進んで入り口と反対側にある塔から出てれば、オーバーラーゲン通りと名前が変わり、その突き当たりに聳えるのが地区教会。教会の右手にあるのは、ラーゲンハウス。ブルーネックでは、一番、古い建物の一つであり、昔はブリクセン司教のための食料貯蔵庫として使用されていた。16世紀になってヴェンツル家が買い取り、建物を今日ある姿に改築した。1851年以降は、市の所有となり、音楽学校校舎として使用され、ホールではコンサートが催されるようになった。地区教会から、来た道を戻れば、左手上にブルーネック城が見える。
ブルーネック城は、その昔は司教の住居として使用されていた建物で、小高い丘の上に立っており、散歩がてらに登れる。内部の一部が公開されており、司教の間とか城のカペレなどが見学できる。また、ラインホルト・メスナーの五番目の博物館MMMがオープンし、世界中の山男を惹き付けている。ブルーネック城から北方向に下りたところに聖カタリナ教会がある。正面扉の上に処刑される聖カタリナの姿が描かれている。市の見どころはこの範囲に集中しており、見学は半日もあれば足りる。
ブルーネックでは、毎年、12月7日に「クラムプスの祭り」が行われる。抑も、クラムプス=Krampusとは、その昔の民話によれば、12月になるとアルプス地方の村々を徘徊して災いをもたらす悪霊であったが、後にキリスト教信仰と結びついて聖ニコラウス(日本ではサンタクロースの名前の方が通りがいい)の従者となり、行いの悪い女、子供を咎める悪魔となったものである。聖ニコラウスは、小アジアにあるミラの司教であり、彼は、その善行によって名前が知られていた。伝説によれば、彼は落ちぶれた貴族の三人の美しい娘を助けたということであり、話の概要は以下のようである。
貴族である父親は、貴族であることを誇りに思い、娘たちの結婚に際しては身分相応の持参金を持たせようとしたが、お金がなかった。そこで娘たちの貞操を犠牲にしようとしたところ、それを知ったニコラウスは、娘たちが生贄として差し出された三日の間、貴族の家の窓辺に金貨をたっぷり入れた小袋を置き、その金額は、娘たちが持参金とするのに十分な額であったので、彼女たちの貞操は救われた。
この伝説に基づいて、聖ニコラウスの日には、彼が子供たちにプレゼントをするという風習が生まれたのであるが、聖ニコラウスは、子供たちの一年間の行状を確かめ、よい子であった子には贈り物を与え、悪い子であった子には小枝で叩く罰を与え、それが次第に聖ニコラウスは贈り物だけして、お仕置きをする役目は先の悪霊クラムプスとなったという次第である。このように、クラムプスは、聖ニコラウスと密接に結びついたことから、クランプスの祭りは、聖ニコラウスの日の翌日に行われるようになり、ブルーネックにおいても、12月6日の聖ニコラウスの日は、彼に扮したサンタ・ク口一スが子供たちにお菓子を配り、翌7日の夜、クラムプスが市中を練り歩く祭りとなっている。
ブルーネックのクラムプスの祭りは、かなり有名で、大勢の観光客、見物客が訪れ、道という道は、彼らでごった返していた。クラムプスは総勢、百とかで、定刻の5時半、悪魔の仮面を被り、腰にはカウベルを幾つも取り付け、けたたましい音を響かせながらやってきた。子供を見つけるや、駆け寄って脅かし、若い女性を見つければ、追い回して、お尻を小枝で叩きながら走ったり歩いたり、時には逆戻りしたりして獲物を物色していた。続いて、二人のクラムプスが荷車に少女を乗せてやってきたが、これは「囚われた少女」だろうか。また、罪人らしき男が縛られて、クラムプスに引きずり回されながら進んくる光景にも出食わした。本来の趣旨から脱線したような魔女の登場もあり、最後になって、聖ニコラウスが若い女性たちに伴われてやってきた。これらの行進を眺める外の気温は、零下7度。アルプス地方の長く続く寒い冬。人々は、こんなお祭りを楽しみ、憂さを晴らしてきたのだろう。
ドロミテ〈Dolomiten〉
アイザック・タールの東側に広がる広大な地域は、「ドロミテ」として知られている。アルプス山脈の中でも一風、変わった岩山が乱立しており、この地に足を踏み入れた人々は、見上げるような切り立った崖や、尖塔のように突き出た岩の数々に圧倒される。あるいは、階段状に重ね合った岩山、平らに均された頂上などを目にして呆然とする。この辺りの地層は白雲岩で、地質時代に暖かな海の底で形成された堆積岩である。約3億年前から地殻変動により徐々に盛り上がり、海底から地上へと姿を現したものである。セッラ山塊その他の山々は、当時の珊瑚礁で、約2億年前に形成され、更に盛り上がって風化と崩壊を繰り返し、今日、見られるような独特の景観をなすようになった。その当時の名残りで、地層からはアンモナイトや貝類の化石が発掘されている。
この地球上の他の地域に見られない荒々しい姿は、訪れる多くの人々を魅了する。どれ一つとっても同じものがなく、奇岩に続く奇岩の連続で、見る者はただ、呆気にとられ、或いは自然の造形美に感動し、ハタと立ち止まって動くのを忘れる。誰もが、「こんな世界があったのか・・」と目を見張る。ドロミテの名付け親は、フランスの地質学者デオダ・ドゥ・ドロミュー=Deoda de Dolomieu。彼は、南チロルで調査していたとき、炭酸カルシウムと炭酸マグネシウムの複塩である苦灰石(白雲石)を見つけ、これは、彼の名を取ってドロマイトと名付けられた。その後、この地の山塊が苦灰岩で構成されていることが判明し、この一帯がドロミテと呼ばれるようになった。
さて、この奇岩群が乱立するドロミテ。ここをどのように見るかであるが、この一帯は観光地であるから、勿論、ちゃんとバスの便がある。しかし、ドロミテ周遊の旅は、レンタカーないしチャーターが望ましい。そもそも、これだけ広大な地域を定期バスで回るのは無理というものである。何日も何日もかかってしまい、余程、時間的な余裕がある人なら兎も角、時間的間隔があるバス便は避けた方がいい。それに、バスは毎日、運行しているとは限らない。天候だって「毎日が晴れ」とは限らない。行ってみて「駄目だった」では、折角の時間が勿体ない。車の運転に自信がなければ別だが、日本での運転経験があれば、ドロミテの山道はそれほど難しくはない。バスが擦れ違える道であるからして、大抵の道は、片側一車線が確保されている。対向車両との擦れ違う道幅は十分にある。で、用意が整ったら、いざ、ドロミテへ。
グレードナー・タール〈Groedner Tal〉
ドロミテへの入り口となるグレードナー・タールは、春夏秋冬、一年を通じて観光客が大勢おしかける世界四大山岳保養地の一つに挙げられている(ちなみに他の三つは、北アメリカのヴァイル、アルゼンチンはパタゴニアの中心都市バリローチェ、そしてニュージーランドのクイーンズタウンである)。グレードナー・タールは、アイザック・タールのクラウゼン辺りから、ドロミテ山々の間を樹木の幹のように東に延びており、全長約25kmある。途中、ザンクト・ウルリッヒ、ザンクト・クリスティーナ、ヴォルケンシュタインの保養地を抱えている。
と、ドイツ語の表記に従って記述したものの、渓谷に入って9キロ程進んだところにあるポンティフェスからは言語が変わり、ラディニシュ語である。したがって、ザンクト・ウルリッヒと呼ぶのは正確ではなく、ラディニシュ語では(ウルティイェイ)という。グレードナー・タールの住民のうちの85パーセントはラディニシュ語を話し、残りの10パーセントはドイツ語、イタリア語を話す住民は僅か5パーセントである。つまり、この渓谷の住民の大半は、ラディニシュ語を話すラディン人である。
このケルトに由来する民族の定住は、紀元前に遡る。その後、この地方一帯がローマに占領され、それとともに古代ケルト族はローマ化された。語られる言語もラテン語の影響を受け、それが後にラディニシュ語になった。その後、チロル全域にはバユヴァーレン族が侵入してゲルマン化されたが、深い谷間の村々は取り残されて今日に至り、言語もそのまま使用されてきた。
ドイツ語とラディニシュ語を対比すると、
Wie geht es Ihnen? = co vala pa?(元気?)
Gut = Bona(ああ、いい)
Schlecht = Nia bona(調子が悪い)
となる。簡単な挨拶言葉として、
ボンディ(こんにちは)
アスデイ(さようなら)
などを覚えておくと、地元での受けが良い。このラディニシュ語は、グレードナー・タールの他、ドロミテ領域のファッサ・タール、ガーデル・タールなどで話され、また遠く、スイスのグラウビュンデン地方でも使われている。
バンウニ・トェ・ゲルディーナ(グレードナーへようこそ)と迎えられて、では、グレードナー・タールは、どこを拠点に見て回るべきだろうか。宿泊地としては、前述のザンクト・ウルリッヒ、ザンクト・クリスティーナ、ヴォルケンシュタインを挙げることができる。迷うところだが、いずれの地に宿泊しても、渓谷全域を見て廻るのだから、宿泊地は個々人の好みとなる。
ちなみに、グレードナー・タールでの楽しみは、ドロミテ一帯を探訪して、その風光明媚な眺めを堪能し、豊かな自然に触れる山登りに勤しみ、高原地帯を散策するなどである。健脚を誇れる御仁はそれで良しとして、年齢を感じる御仁はと言えば、彼らも山男になれる数多くのゴンドラ、リフト、ケーブル・カーの類いが備わっていて、高みへと容易に引き上げて貰える。しかも、各保養地のインフォメーションで購入できる「グレードナー・カード(3日間有効、€60(2018年現在)」を購入すれば、ケーブル・カー等に乗り放題。この額は、4本のケーブル・カー等に乗れば元が取れるという、かなりお得なもの。勿論、いつも晴天とは限らないので、ケーブル・カーに乗ったはいいが、展望台に辿り着いても絶景に恵まれないときもある。が、それは、「運が悪い」というか、「普段の行いに原因があるのではないか」と、霧の中でじっと佇み、己が人生を顧みる機会が与えられたと達観し、コーヒーを啜りながら瞑想に耽る。
ザンクト・ウルリッヒ〈St.Ulrich〉
グレードナー・タールの中心となる村は、ザンクト・ウルリッヒである。この地の高台から先史時代の遺跡が発見され、それらの出土品は郷土博物館に展示されているが、人が定住したのは鉄器時代以降と考えられている。前世紀に入り、ツァホリズム時代の幕開けと同時に、この地域は、農業主体の経済から脱皮し、俄に観光業が盛んとなった。1917年には、クラウゼンからザンクト・ウルリッヒを経由し、ヴォルケンシュタインまで通じる鉄道が開通し、多くの観光客を運んだが、車時代の到来とともに廃れ、惜しいかな、1960年に廃線となってしまった。それが今日となって、環境重視政策から「グレードナー・タールの自然を守るために車両の総量を規制する動き」が芽生え、それとともに鉄道の復活が叫ばれるようになった。復活がなれば「グレードナー線」として、ロマンティックな夢を乗せて走ることとなる。
村の中心には、1796年に建てられた地区教会がある。両翼のカペレは1906年に付け加えられたもの。教会内の数ある彫刻の中でも人気があるのは「施しをするテューリンゲンの聖エリザベート」像である。聖エリザベートは、1207年の生まれのハンガリーの王女で、テューリンゲン方伯の妃となった人物。レプラ患者の救済に尽力し、若くして寡婦となったが、未亡人として受け取った化粧料を元手に、病院を建設して多くの貧民や病人を救った。24歳で死去。1235年に教皇グレゴリウス9世によって列聖された。地区教会を中心として、その界隈には、ホテル、土産物屋、カフェ、レストランなどが軒を並べている。典型的な観光保養地であり、一年中、賑わいを見せている。また、冬場の手工業として営まれていた木工品は、現代では、地域の特産物として販売されている。
フィギィア・スケート界のスターの一人であったカロリーナ・コストナーは、この村の生まれのラデン人である。彼女は、イタリア選手権・ヨーロッパ選手権では表彰台の常連で、長らく、トップ・スケーターとして活躍し、ソチ・オリンピックでは銅メダルに輝いた。また、彼女の従姉のイゾルデ・コストナーは、アルペン・スキー種目で活躍し、ソルトレイク・オリンピックで銀メダリストとなっている。
町からは二本のケーブル・カーが出ている。その一本は、村の南側にあるザイサー・アルムへ登るケーブル・カーで、登り詰めた山駅「モント・ゾイク=Mont Seuc(2005m)」から見るランク・コーフェル山塊の形は、何匹もの子蛙を背負った巨大な母蛙のようである。ザイサー・アルムの眺望はと言えば、それ程でもない。唯、ここからザイサー・アルムを廻る散策の道が縦横に走っており、多くのハイカーは、この村に宿を取って、ザイサー・アルムに入っていく。もう一本のケーブル・カーは、村外れの北側にあり、これはガイズラー山塊=Geisler(3025m)の「セッチェダ展望台=Seceda」へ登るケーブル・カーである。
セッチェダ展望台は、標高2518m。ここからの視界は360度。北側彼方に突き出て見える頂きは、パイトラー・コーフェル。東側の目の前には、恐竜の背中を思わせるガイズラー山塊が見え、南側に目を向ければ、セッラ山塊(3151m)とランク・コーフェル山塊、その間の窪地は、セッラ峠(2244m)である。西側に目を転じれば、ザイサー・アルムの台地がはっきり見える。その向こうに見えるのは、シュレルン。ここまで記せば分かる通り、ここはドロミテの西の部分が殆ど、見渡せるという、まことに贅沢な展望台である。
この展望台からは、ハイキングのための散策路が数多のびている。南東方向に向かうコースには、ホーホ・アルムと呼ばれる広大な台地があり、スキーには絶好の斜面が谷底へと続いている。積雪を迎える季節ともなれば、一面がスキー場と化す。ガイズラー山塊の頂上近くには、小さな湖が数多くある。いずれも、アルプス一帯における最後の氷河期が終焉を迎え、温暖期に入ったときに形成された湖である。なかでも人気なのは、セッチェダから容易に行ける「イマン・ゼー=Imansee」で、夏場の湖水の冷たさは気持ちが良い。ちなみに、イマン・ゼーへは、後述のコル・ライザーからも行ける。
ザンクト・ウルリッヒの南側にそそり立つ岩壁に入り込むような形で、ザイスへと通じる道路がある。その途中から奥まったプーフェルス村=Pufels にあるウーラー・ホテルの裏手に、バラ園「ロザリウム=Rosariun」がある。バラ園は、海抜1500mの位置にあって、ヨーロッパで最も高地にある植物園である。斜面を利用して展開されており、植えられているバラの株数は6千以上、品種は250を越える壮大さで、正に辺り一面、バラ、バラ、バラ・・中でも白い光沢を放つ新種のバラは、「ドロミティ=Dolomiti」と名付けられて珍重されている。
ザンクト・クリスティーナ〈St.Christina〉
この村は、グレードナー・タールの他の村と比べて幾分、素朴な感じがする。北側はガイズラー山塊が迫り、南側はランク・コーフェル山塊が迫り、その間に挟まれた位置的な関係から、そう感じさせられるのかも知れないが、住民の90%以上がラディニッシュ語を話す人々であることも影響しているかも知れない。素朴ではあるが、この村には、保養を求める人々やスポーツ愛好家が多く訪れ、高く評価されている。村には、ランク・コーフェル山塊に向かう「モンテ・パナ」と、ガイズラー山塊に向かう「コル・ライザー」の二つのケーブル・カーがあり、それぞれの展望台からは、自然の神秘的な造形をあますところなく見ることができる。
村の南側台地にある「モンテ・パナ= Monte Pana(1636m)」は、子供連れで楽しめる憩いの場所であり、ちょっとしたハイキング気分に浸れ、体力に全く自信がない御仁でも、「高原に足を踏み入れた」という実感が堪能できる。ここにはレストランもあり、日なが一日、のんびりするのもいい。ランク・コーフェル山塊を「もっと、間近で見てみたい」と仰せならば、モンテ・パナからケーブル・カーを乗り継いで行く「モント・デ・ゾイラ= Monto de Seura」がお勧めである。降り立ったところは、標高2117m。台地に広がる肥沃な草原地帯に迎えられ、南東側に聳える巨大なランク・コーフェル山塊は、圧倒的な至近距離にある。草原地帯では、馬や牛たちが延べつ幕なしに、食事に勤しんでいる。人間はと言えば、食を忘れ、ランク・コーフェル山塊、シュレルンなどのドロミテの山々の絶景をひたすら満喫する。
モント・デ・ゾイラまで来た多くのハイカーたちは、ランク・コーフェル山塊の懐「シャルテ= Scharte」へと吸い込まれるようにハイキング・コースに足を踏み入れ、魔の山を目指して進んで行く。彼らと一緒に歩を進め、下り坂に差し掛かったところでランク・コーフェル山塊を見上げ、「ふむう・・素晴らしい」との感想を抱き、シャルテに向かって下って行く人々に別れを告げる。ちなみに、ハイカーたちは、ランク・コーフェル山塊のシャルテから別のケーブル(後述)に乗ってセッラ・ヨッホへと下り、グレードナー・タールの宿泊地に戻ってくる。時間と体力がある若者向きである。
時間と体力はあるが、そこまで無理をしたくないという御仁は、村の北側にある「コル・ライザー= Col Raiser」に乗って山駅(2107m)に達し、案内板の地図を見て、ここから、どうするかを考える。ハイキング・コースが多々あり、前述のセッチェダ展望台へ行くルートもあるが、特にお勧めなのは、ガイズラー山塊の懐を目指すルート4である。山駅から歩を進め、途中、若干の難所があるが、乳母車を押しながら進む家族連れでも挑戦できるコースで、ほぼ下り坂の道を、「帰路は・・登りか」と思いつつ、「まっ、いっか」と思い直して歩めば、谷間の展望台「レーゲンスブルガー・ヒュッテ= Regensburgers Huette(2037m)」に到着する。ここに立って一服し、北側を眺めれば・・「なっ、何なんだ・・これは・・」目の前に展開しているのは、ガイズラー山塊の西壁から北壁、そして、東壁とに囲まれた「チスレス・アルム= Cisles Alm」と呼ばれる高原地帯。雄大な山々の連なりと、それらに包まれた高原を目にして、「これは・・一体・・」と呆然として見つめ、開いた口が塞がらない。
正に、驚嘆して立ち竦んでしまう自然の圧倒的な存在感。その前で、いくら虚勢を張っても、ちっぽけな存在でしかない我が身・・ここから眺める雄大なパノラマを見ていると、人の苦悩など些事に思え、気持ちを新たにして人生を歩める気がするのは、あまりにも感傷的か・・ここは、誰も己の感動に浸れる全行程所要約3時間の人生に残る体験ができる魅惑的なコースである。
この村では、渓谷の村々の持ち回りで、3年毎に「グレードナーの民族衣装(後述ヴォルケンシュタインの項)」と呼ばれるお祭りが行われる。旅行案内所前の広場が行進の出発地点になり、参加者たちは広場に集合する。広場には、「聖フィロメナの水槽」がある。聖フィロメナについては、残念ながら確たる史実が少なく、教皇庁が定める教会暦に記載されていない。
ザンクト・クリスティーナからヴォルケンシュタインへと向かう道の右手に、「フィッシュブルク城=Fischburg(ラディニッシュ語でチアステル・デ・ゲルダイナ=Ciastel de Gherdeina)」が見える。名前は文字通り、この辺りに数多ある池で魚が釣れたことに由来している。17世紀の初頭に、この辺りの領主の夏の離宮として建てられ、狩りの拠点として利用された由。その後、城は強固に改装されたが、18世紀に入って倒壊し、見る間に荒廃していった。19世紀の中頃になって、当時の領主は、城をザンクト・クリスティーナ村に譲り渡し、村は、老人や貧困者の教護施設としての利用を計画した。その計画が頓挫し、1926年、城はヴェネチア人に売り渡された。現在、城はその子孫に引き継がれていて、内部の見学はできない。
ヴォルケンシュタイン〈Wolkenstein〉
ヴォルケンシュタインをラディニシュ語で言えば「ゼルヴァ・ゲルダイナ=Selva Gherdeina(ゲルディーナの森)」という意味である。グレードナー・タールの一番、奥まったところにあり、昔は、この辺りは森の中に埋もれていたのだろう。開けた今でも森に覆われ、セッラ山塊(3151m)、ガイズラー山塊、ランク・コーフェル山塊に囲まれた谷底の村である。ここが脚光を浴びるようになったのは20世紀の初頭のこと。それからは瞬く間に、アルプスでも著名な観光保養地として発展した。住民2500人に対してホテルのベッド数は8千名分あり、年間の宿泊人数は100万人を超えるというグレードナー・タールの中でも圧倒的人気を誇っている村である。
村の地区教会は、ドロミテの山を背景にした建物がカレンダーの一頁を飾ることで有名な八角形をした珍しい構築物である。ヴォルケンシュタインのお目当ては勿論、ドロミテの風景。ドロミテの山々は、村からも見えるが、景観を楽しむには、やはりケーブル・カーに乗らなければならない。そこは用意周到、村からは二つのケーブル・カーが出ている。その一つは、村の南側にある「シャムピノイ展望台=Ciampinoi(2255m)」へ登るケーブル・カーである。
この展望台は、ランク・コーフェル山塊の直近のやや低い頂きにあり、目の前にはランク・コーフェル山塊の岩山が迫っている。西側に目を向ければ、シュレルンからザイサー・アルム、その右手下にザンクト・ウルリッヒの村。北側に展開しているノコギリの歯状の連なりは、ガイズラー山塊。そこから東側に、台形のセッラ山塊西壁、その麓のセッラ・ヨッホ、そして、ランク・コーフェル山塊の南側彼方には、マルモラーダ(3343m)も見える。セッラ山塊北壁とランク・コーフェル山塊の全貌を見るには、村の北外れにある「パノラマケーブル・カー」に乗って、「ダンターシェピエス展望台=Dantercepies(2298m)」に登るのがいい。否、このケーブル・カーに乗らなければ、グレードナー・タールに来た意味がない。
展望台に近づいて、登ってきた背後を振り返れば、
「おっ!」と目を見張り、更に登って、
「おおっ!」と前のめりになり、そして、最後は、
「うおっ!」と叫んで絶句する。そして、展望台に達して、じっくりと見回す。
南側には、セッラ山塊の北壁のその露骨なまでに荒々しい山肌が、覆い被さるように迫っているのが見える。この光景を例えれば、「巨大な隕石が地上に落下して、そのまま居座った姿」とでも言おうか。そして、セッラ山塊の右手には、地中から盛り上がって台形を為している山塊。見る方向によって形が異なるランク・コーフェル山塊の勇姿である。その西側には、シュレルンを背景にしたザイサー・アルムが広がっているのが見える。そして、谷底には、グレードナー・タールの村、村、村・・・「ここまで来て良かった・・」この光景は、写真に撮れども、とても収まりきらず、人間の生物としての目の確かさを再認識させてくれる。感動と興奮に包まれ、見飽きない景観である。一転して、目を東側に転じれば、遙か彼方にクロイツ・コーフェル山塊の連なりが遠望できる。ここはまだ、ドロミテ山群のほんの西側。東側にまだまだ、ドロミテが続いているのが垣間見える展望台でもある。
グレードナー・タールの村の持ち回りで、前述したように、3年に一度、8月の第一日曜日、「グレードナーの民族衣装=Groedner Tracht」と名付けられたアルプス全域で一番、美しいお祭りが催される。渓谷の各村々から老若男女が年相応の民族衣装に身を固め、村の中を練り歩く。それは華やかで美しく、観光客は、着飾った少女たちを呼び止めてはシャッターを押している。女性の衣装には特徴があり、既婚女性が被る黒の帽子は「クナイドゥル」、黒の衣装は「バガナ」。未婚女性の愛らしい頭飾りは「ゲルランダ・シュピッツァ」と呼ばれている。ブラウスは大抵、白で、襟飾りのレースが清楚であり、ベルトは銀製で「チェンタ」と呼ばれ、調理用のナイフとフォークが差し込まれている。幼女までもがそのような姿で着飾っている。村中を練り歩く行進が始まれば、年上の少女に手を引かれて歩く幼女の姿は、あどけなく微笑ましい。
ヴォルケンシュタインの村からは、付近の山々へのハイキング・コースが縦横に伸びている。村からそのまま行ける手軽なコースには、「ランゲン・タール=Langen tal」がある。プエツ山塊=Puez(2913m)が深く切れ込み、U字形に形成された谷で、入り口にはレストラン「チィアヤタ」がある。そこからは歩行者天国になっており、牛や馬たちがのんびりと屯し、周囲を見上げればドロミテの荒々しい岩肌や、鉈で割ったような切れ込みがあちこちに見える。この渓谷の名所の一つは、岩盤に穿たれたような風の通り穴。そのため、まるで橋が架けられたように見える岩山がある。渓谷に入って十分程も歩き、左手のシュテフィア山を見上げれば遙か上方に望める。
<ヴォルケンシュタイン城=Schloss Wolkenstein>
ランゲン・タールの入り口、シュテフィア山の断崖絶壁の中腹に引っかかるように建てられ、今では廃墟となったヴォルケンシュタイン城がある。
ブリクセンの司教領が確立されたとき、グレードナー・タールはその一部とされたが、司教はこの地を自ら統治することなく、封土として貴族マウルラップに与えた。1225年に、彼はここに城を築いたが、1291年、ヴォルケンシュタイン家の祖先が譲り受けた。城は同家の夏の居城として使用されたが、1525年に崩壊し、その後は再建されることなく今日に至っている。1994年になって公的補助を受け、城の一部が復修されて一般人に公開されるようになった。
城まではハイキング・コースが通っている。城自体は、崩壊したままで見るべきものはないが、中腹からのランゲン・タールの眺め、プエツ・ガイズラー山塊の景観、ヴォルケンシュタインの村の佇まいなどが楽しめる。しかしまあ、よくぞ、こんなところに城を建てたものだと感心させられる。
この城に纏わる伝説がある。語られるところによれば・・・ボルケンシュタインの廃城には、噂では、途方もない莫大な金銀財宝が埋められているのだとか。人々は、城のあちこちを掘り返して財宝を我が物にしようとしたが、発見できなかった。噂を聞きつけた宝探しがやってきて、絶対に見つけ出そうと、廃城内の至る所を掘り起こし始めた。その時、漆黒色の巨大な鳥が飛来し、燃えるような赤い眼差しで宝堀りたちを睨みながら、彼らの頭上を旋回し始めた。宝探しは、あたふたと右往左往し、もんどり打って城壁から転げ落ちてしまった。このことがあって以来、財宝を掘り出そうとする勇気ある者はいなくなった由。
コルティナ・ダムぺッツオ〈Cortinad'Ampezz〉
(ラディニッシュ語でアンペツォ=Anpezo. ドイツ語ハイデン=Hayden)
アンペッツォ渓谷のコルティナ。そんな意味合いの村で1956年、冬季オリンピックが開催された。老齢の人ならば、この大会で2018年現在の今なお、アルペン種目では日本人唯一のメダリスト猪谷千春選手が活躍したのを記憶しているだろう。平和なスポーツの祭典が催された村ではあるが、この村は、歴史の渦巻く波に翻弄された悲しい過去を有している。
この辺りは、元々は、ケルト系の民が農業で細々とした生計をたてていた寒村であったが、6世紀頃、エルベ川付近から南下してきたランゴバルト族がランゴバルト王国を樹立し、この地一帯にも支配権を確立した。とは言うものの、この地域ではドイツ語化が進まず、その状態は今日まで続いており、ドイツ語とラディ二シュ語の言語境界地域となっている。
ランゴバルト王国は、王権が弱体なために各地域では地方自治権が確立された(この制度は1918年、この地がイタリアに割譲されるまで続いた)。776年以降は、王国は、カール大帝が率いるフランク帝国に属した。その後、この地はバイエルン大公領となり、神聖口一マ帝国の一部となった。交易が盛んになるにつれて、この地は、神聖ローマ帝国とイタリア特にヴェネチアとの中継地点となり、14世紀に入って一旦は、ヴェネチアの支配するところとなったが、1511年10月21日に再び、神聖ローマ帝国領〈オーストリア領〉に復帰し、正式にチロル大公領となった。
19世紀後半になって観光産業が興り、この地には、オーストリアの貴族たちやフランス、イギリスのブルジョアジーたちが好んで訪れるようになり、豪華なホテル、レストランなどが建設され、スキー学校が開設された。しかしながら、第一次世界大戦の勃発が、この華やかな時代に終止符を打った。この地の成年男子たちは戦線に駆り出され、遠く、ロシア戦線に派遣され、故郷に残っていたのは、婦女子及び16歳以下の少年と50歳以上の男子だけであった。このような状況下でイタリア軍が攻め込んできたのであるが、オーストリアは、戦略上の理由から山岳地帯まで後退し、この地の防衛は放棄された。この地が、再びチロルに復帰できたのは、カポレットの戦いでオーストリア・ドイツ連合軍がイタリア軍を蹴散らした(この様相については、ヘミングウェイ著「武器よ、さらば」に描かれている)後である。
しかしながら、大戦は結局、ドイツ、オーストリア側の敗戦に終わり、1919年に締結されたサン・ジェルマン条約で、この地は、他の南チ口ルやトレンティノと同様、イタリアに割譲されることとなった。この地のイタリア化は、それとともに始まったのであるが、イタリア政府の施策は過酷を極め、政策に反対の声を挙げれば逮捕され、遠方に追放されたりした。また、ラディニシュ語圏の渓谷は分断され、この地は、他の南チロルから離されて、ベッルーノ州に属せられ、村は「コルティナ・ダムぺッツォ」と改名させられた。
第二次世界大戦の最中、この地はドイツの占領下に置かれ、大戦後、住民はオーストリアへの復帰を希望したが、住民投票の機会さえ与えられず、復帰は適わなかった。そんな歴史的経緯のあるアンペツォ=ハイデン=コルティナ・ダムペッツォ。観光の復活とともに、再び、華やかな時代を迎えることとなった。今日では、おしゃれで活気のある村にすっかり変貌し、訪れる人々を歓待し、魅了してくれる。村の中心には、薄緑色した地区教会の塔が一点、際立ち、絶妙なアクセントになっている。歩行者道路の両側は、ホテルあり、高級ブテックあり、レストランあり、土産物屋があり、スーパーもある。
この村のキャッチフレーズは、ホテルの受付嬢が言うには、「世界で最も美しい癒しの場所」だとか。確かに、ここは風光明媚な光景に囲まれている。村の周囲には、トファーナ山塊、ソラピス山塊、モンテ・クリスタッ口山塊などが控えており、仰ぎ見て、「絶景かな」と陳腐な感想が十分、マッチする素晴らしさである。但し、晴天の日ならばである。曇天、特に雨天となったら、目も当てられない。恨めしく空を見上げ、「あそこに、トファーナ山塊が見える筈なんですが・・」と言われて慰められ、肩を落とすしかない。何はともあれ、保養地でどのように過ごすかは、人それぞれ。どっしりと腰を据えて、買い物ツァーもよし、ウインドウ・ショッピングもよし、公園とか建物を眺め歩くのもよし。
あるいは、郊外のペンション風ホテルで日長、読書するなどして、のんびりと過ごすのもよし、気が向いたらハイキングに出かけるのもよし、馬に乗るのもよし、素養のある人はアートな雰囲気に浸り、イメージを具象化するのもよし・・晴天、雨天にかかわらず、時間の楽しみ方は各人各様である。ホテルも、観光客の各種多様な要望に応えるべく、万の施設を取り揃えて待ち構えている。勿論、当然のことながら、サービスの対価としての金の無心という下心を秘めてはいるが・・この村でー番、著名なホテルは、村の郊外にある「ミラモンティ」である。村で唯一の五つ星の評価を得ており、格式は最高級である。世界中から数多の有名人が来て宿泊しているが、芸能人で言うならば、フランスからはブリジット・パルドー。イタリアからはソフィア・口ーレン。アメリカからはクラーク・ゲーブル。イギリスからはジョン・レノンなどが訪れ、その他の王侯貴族となったら枚挙にいとまがない。
ホテルから村の中心へは頻繁に、連絡バスが運行されている。このホテルには、ゴルフ場も併設されている。6ホール、パー21のミニ・コースの料金は安く一日16ユーロである。ゴルフ・プレーヤーは、コルティナ・ダムペッツォに来た記念に是非とも、クラブを振りたくなるところだが、かなりの難コースである。さて、山好きでなければ抑も、この村には来ないだろうから、これだけの名山を控えていて、どこにも登らないというのは、ここに来た意味あいが褪せるというもの。とは言うものの、山に魅せられつつも「自力で登山する気はない」と仰せならば、そのような御仁向けに、ここにはケーブルー・カーやリフトの類いが揃っている。その主だったものは、トファーナ山塊、プンタ・ソラピス山塊、モンテ・クリスタッ口山塊へ登るケブル・カーである。
<トファーナ山塊=Tofana Mezzo>
村の西側にどっしりと構えているのは、巨大なおむすびを思わせるトファーナ山塊(3244m)である。トファーナ・ディ・口ーゼス(3225m)、トファーナ・ディ・メッツォ(3244m)、トファーナ・ディ・デントロ(3238m)の三峰からなり、トファーナ・ディ・メッツォの山頂近くまで、ケーブル・カーが通じている。ケーブル・カー山駅から山頂までの登山路は、砂利道もあって滑りやすく、準本格的な登山装備が必要である。背広、革靴でも何とかなるマリア・ヒュッテとは大違いである。山頂からの眺めは、異彩である。ポルドイ峠のマリア・ヒュッテが西ド口ミテを眺望する展望台ならば、ここからは東ド口ミテを一望の下に置く眺めが堪能できる。
眼下にコルティナ・ダムぺッツォの村。北東側にはモンテ・クリスタッロ山塊。南東側にはアンペッツォ渓谷を挟んでソラピス山塊、南側にはモンテ・ペルモ山塊(3168m)、モンテ・チヴェッタ山塊(3220m)。西側は間近にトファーナ・ディ・ローゼス、その右手にはマルモラーダ山塊、更にセッラ山塊、トファーナ・ディ・デント口等々・・四方を見渡せば、灰褐色に覆われた世界に降り立ったようで、荒涼たる剥き出しの岩山が遙か彼方まで連なって見応えがある。登ってきた甲斐があったと言うものだが、さて、どうやって下りるかは難題である。足を踏み外せば、千メートルは滑落することを覚悟しなければならない。勿論、覚悟しても、命が助かる訳ではないが・・
頂上から山駅へ戻る途中、珍しく、日本人のご夫婦と遭遇した。かなりお歳を召したご夫婦で、それでも、頂上を目指して歩んでいく。ご主人が山好きなのだろうと思い、後方を付いて行く奥方に声を掛ければ、「そうなのよ。あの人が好きなものだから、こんなところまで来るの」と愚痴っぽく言う笑顔が幸せそのもので、微笑ましかった。
<ソラピス山塊=Sorapis>
ソラピス山塊は、村の南東方向。バスターミナル近くに、その前峰(プンタ・ネラ)の更に手前のファロリア展望台(2123m)まで上がるケーブル・カーがある。上がったところは南側に、冬場のスキー場が開けている。夏はハイキングであるが、リフトは運休しており、南側の展望を望みたい向きには、プンタ・ネラ(2846m)まで自力で登らなければならない。その精神力も脚力もない御仁は、ここへは登らずに節約して別のケーブル・カーを目指した方が「損した」と後悔することはない。因みに、ファロリア展望台からは北西方向に、トファーナ山塊の麓に抱かれたコルティナ・ダムペッツォとその周辺の高原地帯が箱庭のように見える。勿論、モンテ・クリスタッロ山塊も目の前である。
<モンテ・クリスタッロ山塊=Gruppo d. Cristallo>
村の北東に鎮座しているのは、モンテ・クリスタッロ山塊(3221m)。この山塊は荒々しく、山肌はとげとげしく、肉野菜の滅多切り、山賊焼き豪華版の様相を呈している。それ故に見る確度によって、「これが同じ山か」と唖然とさせられる。早い話が、「山の形をなしていない」と言えば正解であろう。このゴツゴツした岩肌が剥き出しの山塊にも「よくぞ、作った」と感心させられるリフトとケーブル・カーがある。乗り場は、村からミズリーナ湖へ向かうパッソ・トレ・ク口ーチ峠道の少し手前のリオ・ゲレ。ここからソン・フォルカ展望台(2235m)までは、四人乗りのリフトが通じている。
ソン・フォルカ展望台からは、南側及び西側の眺めが素晴らしい。プンタ・ソラピス山塊(3205m)、トファーナ山塊がパノラマのように広がっている。イタリア・ドロミテのモンテ・ペルモ山塊、モンテ・チヴェッタ山塊、ジァウ峠も見渡せる。ソン・フォルカ展望台から更に、上を目指す変わったケーブル・カーがある。縦長のトウモロコシ形をした二人乗りの世界一、小さなケーブル・カーであり、恋人と二人で乗るなら兎も角、男二人で乗るには、何やら窮屈なケーブル・カーである。これに乗れば、岩山の懐奥深くにあるカパンナ・口レンツィ展望台(3000m)まで行ける。岩山と岩山の狭い鞍部に設けられた展望台は、そこに立つだけでも足が竦む。それなのに、そこから更に山頂を目指して登坂していく山女がいる。その姿を見ていると余計、身が縮こまり足が動かなくなる。「そんなことをしていると、お嫁さんに行けないよ」と、こちらが登れない僻み根性で思わず、そんな声を飲み込む。
余談だが、ここの人たちは老若男女を問わず、山歩きが好きである。しかも、自分の足で登ることに喜びを見出している。杖をついてまで、山歩きに精を出す老人もいる。寝たきり老人の話を聞かないが、これだけ歩いていれば、「然もありなん」と納得できる。話を戻して、カパンナ・ロレンツィ展望台からは、北、東側の眺めが頗るつきである。赤みがかった三角形の山はホーエ・ガイスル(3146m)、その右手の広い台地はプレッツ・ヴィーゼン、その右手に青白く見えるのは神秘な湖デュッレン・ゼー。その遙か彼方には、グロース・グロックナー(3797m)も見える。留めは名山、ドライ・ツィネンで、高原からニョキッと突き出た感じが何とも形容しがたい。
セッラ山塊同様、モンテ・クリスタッロ山塊を一周する周回道路が走っている。その北西の一角は南チ口ルの領域で、そのことを示す標識が立っている。
コルティナ・ダムペッツォは、ドロミテの奥地にあって「行きづらい」と思う向きもあろうが、ベッルーノからは一日、十本のバス便があり、ベッルーノ鉄道線の終着駅カラルツォ・ディ・カドーレから一日、二十本のバス便がある。ヴェネチアからは7時50分、ローマ広場発で一日一便。遙か遠く、ナポリからも、ローマ、フレンツェ、ボ口一ニャを経由して一日一便。ミラノからも一日一便ある。また、コルティナ・ダムペッツォは、東ド口ミテの中心地であり、ここから各観光地へと通じるバス便も多い。ドライ・ツィネンへは、ミズリーナ湖を経由して一日四便。トプラッハへは、一日十便(更にトプラッハ経由でプラクザー・ヴィルト・ゼーへ一日四便)。周遊に便利なバスとしては、コルティナ・ダムペッツォ発ファルツァレゴ峠、ヴァルパ口ーラ峠、コルヴァラ村、グレドナー峠、セッラ峠、ポルドイ峠を経由して出発地に戻る大回遊便がある。詳細は、バスターミナルの案内所に問い合わせれば、時刻表が手に入る。
<ラーゴ・ディ・ミズリーナ=Lago di Misurina>
この湖は、ド口ミテにある数ある湖の中で特に有名である。ソラピス山塊を背景にしたホテルと湖の情景がカレンダーの一ページを飾っているのを見た人もいるだろう。夏ともなれば、観光バスがひっきりなしに訪れ、観光客を大勢、吐き出している。人々は、ドライ・ツィネンを背景にしたり、ソラピス山塊をバックにしたりとあっちへこっちへ忙しい。著名になって歓楽用の湖と化し、そのせいか湖水はそれ程、奇麗ではない。透明度もイマイチであり、観光客が捨てていった缶とか紙くずが湖底に沈んでいるのが見える。自然に親しみたいと思う心が踏み躙られ、興醒めする。
ラーゴ・ディ・ミズリーナに別れを告げ、大ド口ミテ街道を若干、進めば程なく、分岐点に差し掛かる。分岐点から右手に入る道を進めば、行き着いたところに、この大街道最大のお目当てであるドライ・ツィネンが待っている。九十九折りの道が一段落したところに、小さな湖ラーゴ・アントルノがある。この湖に写るドライ・ツィネンは、それは素構らしく、「その美しい形に惹かれて訪れる写真家が後を絶たない」という知る入ぞ知る絶景地である。湖もまた、透明度が高く、山奥の隠れた秘境という風情がぴったりである。人間の思考上の教えである、「聖なるものに触れれば、心は洗われる」と信じるには想橡力が些か欠如する者でも、この湖水に引き込まれれば、「身体だけでなく、心までも清らかに雪がれる」と感じるかも知れない。
<ドライ・ツィネン=Drei Zinnen>
地中から突出した三つの岩。それが鋸の歯に似ていることからドライ・ツィネン(三つの歯)と名付けられ、ドロミテ山塊の代表的な岩山で、これを見なければドロミテに来た甲斐がないと言われる名山である。車道はドライ・ツィネンの麓のアウ口ンゾ・ヒュッテ(2320m)まで通じている。しかし、この辺りは積雪が多いために一年の内、通行できる期間は限られている。アウ口ンゾ・ヒュッテまで登れば、目の前にドライ・ツィネンの雄姿が立ちはだかる。但し、イタリア側から見るドライ・ツィネンは、その名前が示す「三つの鋸の歯状」には見えない。大きな塊が迫り来て圧倒されるが、形そのものはドロミテの他の岩山と変わらず、それほど印象的ではない。
三つの鋸の歯状の頂きを見るためには、南チ口ル側へ行かなければならない。そのための周遊ハイキング道路が作られており、右回りでも左回りでも四時間程で一周できる。右回りコースを取れば、ラヴァレドの山小屋辺りから、ドライ・ツィネンの形はゆっくりと分離し始め、更に登ってラヴァレド峠に辿りつけばはっきり、三つの頂きが現れる。頂きは、東からクライネ・ツィネ(2866m)、グ口ーセ・ツィネ(2998m)そしてヴェスト・ツィネ(2973m)。前者二つの頂きは、岩壁の部分から南チロル。ヴェスト・ツィネは完全に南チロルの領域に入っている。
その岩壁だが、見るからに恐ろしい。ナイフでスパッと切ったように垂直にそそり立っている。どうして、こんな形の山ができたのか、自然の造形美に圧倒される。これは、確かに一見の価値がある。ハイキング道路を更に進み時折、ドライ・ツィネンを左手に頂きを見ながら注意深く進むと、足元の石の肌が露出して青自く輝いているのに気づく。ド口ミテは別名「青白い山」と言われている。これは、月の王女が郷愁にかられて月に帰りたがったとき、月の光から糸を紡いでいた「こびと」が王女を説得して地球に留まらせ、ドロミテに住まわせたという民話に由来する。
炭酸マグネシウムの表面は、時には褐色に、時には黄色く、時には白く見える。それは恰も、月の光から紡いだ糸のようなロマンティックな色合いである。情緒に浸りながら道を更に行けば、左手に池が見えてくる。一つ、二つ、三つ・・それ程、大きくない池だが、遠方の山々を水面に映し、高原の景色に彩りを添えてくれる。池を過ぎれば、アウ口ンゾ・ヒュッテまではもうすぐ。但し、ここからは難所である。右手は深い谷が落ち込んでおり、足を踏み外せば真っ逆さまに地獄行き。その道とて急斜面に作られた幅一メートル程の頼りないもの。振り返れば、良くあんな道を歩いてきたものだと感心する。なのに、その道をランニングしている男がいる。思わず、「おっ、おい。よせよっ!」と叫びたくなる。