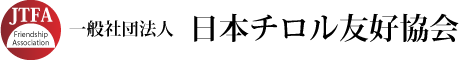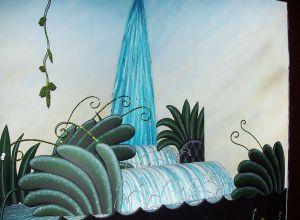チロルとは?
チロルとは、どんなところ?
チロルと言えば、チロリアン・ハットにチロルチョコレート。我々、日本人には身近な言葉であり、その場所がどこにあるのかは兎も角、頭に思い浮かべるのはヨーロッパ・アルプスの高原地帯。「なだらかな丘陵がどこまでも広がり、小川には澄んだ水が流れてマスが泳ぎ、草原には牧牛がのどかに寝そべり、どこからか、ハイジが飛び出してきてペーターと戯れる」そんな光景がイメージされるに違いない。
この牧歌的な情景は、多くの人々を魅了してやまない。観光時代の訪れともに、如何に多くの著名人がこの地方を訪れたことか。童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンも「絵のない絵本」第23話でチロルの素晴らしさを謳っている程である。
冬ともなれば、良質の雪に恵まれて、世界中からスキーヤーがやってくる。夏は酷暑を逃れる人々が、ハイキングやトレッキングにとやってくる。チロルは一年中、観光客を呼び寄せており、今日まで、多くの人々が訪れては感激に胸を震わせてきたところである。
そんなに素晴らしいところなのか・・・
そんな夢の世界が広がっているのか・・・
この世に伽噺のような世界があったのか・・・
答えは「然り」である。が勿論、それはチロルの一面である。ものごと全てがそうであるように、チロルは、優しい面を持っている一方で、厳しい自然をちらつかせる。チロルには、切り立った渓谷もあれば、大地に悠然と居座った氷河もある。冬ともなれば交通は閉ざされて、人が容易に飛び込んでいけないところが多い。荒々しい自然が剥き出しのところが大半であり、自然がそうならば、人間社会だって平穏だった訳ではない。のどかな風景からは信じられない、血なまぐさい戦いの歴史が数多く残されている。実際、チロルの地には、多くの民族がやって来た。語られるところによれば、初めに定住したのはイリュリア人であり、次いでケルト人、ローマ人、ゲルマン人たちがやって来た。彼らが侵入した際には、先住民族との戦いが避けられず、流血の惨事は、一つや二つではなかった。近年になってでさえ、スイスの軍隊をはじめ、ナポレオンの軍隊が軍靴の音高らかにこの地を蹂躙し、更には、バイエルンとの壮絶な戦いを経験した。また、第一次世界大戦では、イタリア軍との間で、寒冷下の山岳戦が繰り広げられた。
そんな歴史を持つチロル。
それでは、チロルは一体、どこにあるのだろうか。そして実際、チロルとは、どんなところなのだろうか。
チロルは、良く誤解されるが、スイスにある訳ではない。由緒あるチロルの名前を冠した州は、チロル州(東チロルを含む)であり、それはオーストリアにある。チロル州の州都がインスブルックであり、インスブルックは、チロルのシンボルと言われている。しかし、インスブルックがチロルの中心となったのは、かれこれ500年ほど前に過ぎない。それ以前はメラーンが中心であり、そこは現在、イタリアにある。
<地図はWikipediaより引用>
「現在はイタリアにあるメラーンがチロルの中心だった」この事実には、衝撃を受ける人は多いかも知れない。メラーンがチロルの中心だったということになると、チロルはオーストリアだけではなく、イタリアにまで及んでいることになり、そうなると一体、どこまでがチロルなのか混乱するに違いない。
歴史を紐解けば明らかなように、チロルの領域は、現在の国境を越えて広がっている。それでは、どの範囲をもってチロルと呼ぶのだろうか。この問いに答えるにはまず、チロルがどのように形成されて今日に至ったのかを検証しなければならない。それが同時に「チロルとは、どんなところか」との問いに対する答えにもなるので、ここで簡単にチロルの形成過程を見てみよう。
チロル小史
この地域は、1271年の古文書にも「山の国チロル」と記された如く、全チロルの85パーセントが山岳地帯である。チロルの歴史は、この地理的な状況抜きにしては考えられない。いつ頃から人々が住み始めたのかを振り返ってみれば、この地域一帯の山々の高さ、長く続いた氷河期など、人間や動物、植物などが育成するには地理的にも気候的にも不利な環境が作用して、人間のチロルへの定住は比較的、遅かったと考えられている。
それでも、クーフシュタイン付近の遺跡からは、3万年前のものと思われる石鏃が発掘されており、また近年、氷河に閉じ込められていた状態で発見され一躍、有名になった5200年前のミイラは、人間がその時代にアルプスを越えて活動していたことを窺わせ、その頃から既にチロル地域に人間が定住していたことの証左となっている。
歴史に現れるこの地の最初の住民は、イリュリア人である。彼らの痕跡は、初期ハルシュタット文明として残され、青銅器次いで鉄器を使用する文化を興した。紀元前400年頃、ケルト人が押し寄せてきた。彼らはこの地一帯に勢力を張り、後期ハルシュタット文明の担い手となった。彼らの一部は、アルプスを越えてローマの領土にまで侵略し、紀元前387年にはローマを占領するまでに至った。彼らは、紀元前2世紀頃に東アルプス地方一帯にノリクム王国を興した。
ケルト人が隆盛だったのはこの頃までで、引き続く世紀には北からはゲルマン族、南からはローマの圧力を受けるようになった。勇猛果敢なゲルマン族と組織的軍事力に秀でたローマとの間にあって、ケルト人は、両者の鼻息を窺いながら生活するようになった。当初はゲルマン族が優勢で、その一派、キンブリ一族、テウトニ一族に蹂躙されたが、ローマが徐々に力を蓄え、紀元前15年、将軍ドルススとティベリウスがアルプスを越えてチロル地域を占領し、ケルト人の王国ノリクムを粉砕してローマの範図に組み入れ、今日の北チロルの大半を「レティア」に帰属させ、東チロル以東を「ノリオイム」と定めた。東チロルの州都リエンツ郊外に、チロルで唯一のローマ都市遺跡として、ノリオイムの「アグントゥム」がある。都市の規模はまだ不明であるが、城壁や保養施設、初期のバジリカ様式の建築土台などが発見されている<詳細、後述>。
ローマの治世400年の間は比較的、平和な時代であった。レティアのケルト人たちはローマ化され、「ラディニシュ語(スイスではレート・ロマニッシュ語という。以下、同じ)」と呼ばれる言語を話すようになったが、この言語は、 19世紀までオーバー・イン・タールで使われ、今日なお、南チロルのグレドナー・タール、ファッサ・タール、スイスのグラウビュンデン地方などで使用されている。この地域に変化をもたらしたのは、ゲルマン民族の大移動である。ローマの帝国崩壊の原因ともなったその移動に伴い、この地には、その一部族である東ゴート族が侵入して東ゴート王国を建て、6世紀中頃にはフランケン族が侵入してきた。続いてやってきたのは、バユヴァーレン族(バイエルン族)である。このバユヴァーレン族の素性は、と言うと明らかではない。フランク族、ゴート族といった部族集団のゲルマン民族ではなく、ゲルマン民族の寄せ集めではないか、あるいはゲルマン諸民族とケルト民族との混血ではないか、また一説には、ローマの征服者とゲルマン民族との混血ではないかとも言われているが、ともあれ、この頃になってボヘミア辺りから姿を見せて歴史上に現れ、ドナウ川とアルプス山塊との間に根を下ろした。その指導者として歴史上、最初にでてくる名前がグリバルト一世である。
7世紀の中頃になって、バユヴァーレン族は、徐々に支配地域を拡大してブレンナー峠を越え、原住民たちを吸収して680年頃には、ボーツェン辺りまで支配下においた。このバユヴァーレン族が、その後のチロルの民族構成の根幹を形成し、チロルの各地域は、7世紀の終わり頃までにはバユヴァーレン風の呼称に定められた。この頃、勃興したカロリング朝カール一世は、領土拡大政策を積極的に押し進め、ゲルマン部族の支配地域は、徐々にフランク王国の範図に組み入れられ、この地も領主タシロ三世が廃されて、788年に同じ運命を辿った。因みに、このカール一世は800年、ローマで戴冠してカール大帝となり、キリスト教帝国を樹立した。カール大帝の死後、フランク王国は相続により三カ国に分轄され、この地域は東フランク王国の一部となり、東フランク王国地域は、後に神聖ローマ帝国を形成した。
この頃には、この地域の骨格が朧気ながら具体化し、イン川の上流地域は「オーバー・イン・タール伯領」、下流は「ウンター・イン・タール伯領」の各領域が形成された。また、インスブルックから分かれて南下するイン川支流のジル川に沿い、ブレンナー峠を越えてアイサック・タールのクラウゼン辺りまでの領域は「ノリタール伯領」、その南は「ボーツェン伯領」と「エッパン伯領」、フィンシュガウ・タールの領域は「フィンシュガウ伯領」、プスター・タール領域は「プスター伯領」が形成され、プスター・タールの東方のリエンツ辺りは「ルルン伯領」の一部となった。これらの伯領が形成される一方で、協会勢力も確実に勢力を伸ばしていった。
ところで、東フランク王国たちは、神聖ローマ帝国の皇帝としての戴冠を受けるためにアルプスを越えてローマに赴くことを余儀なくされていたが、道中、必ずしも無事であった訳ではなかった。国王に反対する勢力があり、バイエルンとシュヴァーベンの領主たちは屡々、戴冠を邪魔する挙動に出た。そこで1027年、皇帝コンタート二世は、ローマ教皇による戴冠を受けるに際して、アルプスを越えてローマへ至る幹線道路の確保を信用のおける司教に委ねるため、トリエントの司教にボーツェン伯領とフィンシュガウ伯領を与え、ブリクセンの司教にはノリタール伯領とウンター・イン・タール伯領を与えた。更に1091年、皇帝ハインリッヒ四世は、ブリクセンの司教にプスター伯領を与えた。しかしながら、このような皇帝の措置は、望ましい結果を伴わなかった。
与えられた領土は元々、バイエルンの領主たちが支配していたところであり、その権力が完全に奪われた訳ではなかった。また、司教たちは、教会の権威を守るという配慮により、自ら領主権を行使することを好まず、結局、与えられた土地は、バイエルンの貴族たちに封土として与えられることとなった。
このようにして、ウンター・イン・タール伯領とプスター伯領を任されたのは、アンデクス。また、フィンシュガウ伯領を与えられた豪族アルベルト一世は「フィンシュガウ伯」を名乗った。この代官たちが次第に力を持ち始め、フィンシュガウ伯は1141年、「チロル伯」と改め、代々のチロル伯は、以後、ボーツェン伯領およびエッパン伯領を吸収して次々に領土を拡大し、アンデクス伯家が断絶した1248年には、イン・タールからプスター・タールまで併合して、今日の原型をなすチロル伯領を形成した。このことをもって、チロル生誕の年は、1248年と定められている。
1253年。アルベルト一世の家系が途絶え、チロル伯領は、ルルン伯領を支配していた娘婿のゲルツ伯爵の手に落ちた。その子で「チロルの父」と呼ばれているのがマインハルト二世(1258-1295)であり、彼は、シュタムスにシトー派の修道院<ツィステルツィーエンサー修道院>を建立させ、その修道院は、後にチロルの領主たちの陵墓をなった。また、彼はひたすら領土を拡張し、通商、交通を促進させ、統治のためのチロル法を起案させた。
マインハルト二世の孫のマルガレーテ・マウルタッシュ(1335-1363)は、事実上、ゲルツ家最後の領主となる。彼女は息子の死後、1363年にチロル伯領をハプスブルグ家に譲り渡し、これにより、チロルの大部分は、オーストリアに帰属することになった。
チロルは、ハプスブルグ家レオポルト三世(1365-1386)の家系に引き継がれた。レオポルトの息子のフルードリッヒ四世(1406-1439)は、領土の居城をメーランからハプスブルグ家東西線上の重要地点であるインスブルックに移し、また巧みな財政政策、優れた統治により富国に努める一方、鉱山業を興して銀の産出を促進した。その結果、彼自身は「空の財布持ちのフリードル」と呼ばれたが、彼の息子のジグムント(1446-1490)は、「富豪」と呼ばれる程に、大いなる財産を残した。
この鉱山業の発展を鑑みて、多くの研究家は「ハプスブルグ家の繁栄は、チロル抜きにしては考えられない」としている。チロルの豊かな鉱山資源がハプスブルグ家の財政を潤しからで、チロルは当時、「オーストリアの金庫」とさえ言われた。事実、チロルにおける銀の産出は、鰻登りに高まり、ハルには貨幣鋳造所が建設された。市民の生活も豊かになり、家々を結ぶアーケードや家の張り出し窓、凸状の切り妻などの特徴を備え、それらの構造物は今日もなお、インスブルック、ハル、ラッテンベルグなどで見ることができる。その中でも世界的に有名な建物は、ハルの市役所、ハーゼック城及び貨幣塔、インスブルックの市塔である。
しかしながら、ジグムントは浪費的な生活を送り、ヴェネチアに戦いを挑んで破れ、結局、退位を迫られた。1490年。彼の後を継いだのがマクシミリアン一世(1490-1519)である。彼は、インスブルックの居所を好み、黄金の小屋根や宮廷教会を作らせる一方、バイエルンとの戦いで、クーフシュタイン、ラッテンベルグ、キッツビュールを獲得した。マクシミリアンは、更に、プスター・タール、東チロルを相続し、後にツィラー・タールが追加され、彼の時代になって今日のチロルの境界がほぼ定まった。その後、この地方はドイツ各地方に起こった農民戦争(1525-1526)、ドイツを舞台にヨーロッパの列強が入り乱れて争った30年戦争(1618-1648)に巻き込まれたが、さしたる領域の変動はなかった。
1665年。チロルのハプスブルグ家の血統が途絶えた後、特に18世紀に入ってからは、ヴィーンのハプスブルグ家による中央集権化の波がチロルにも押し寄せてきた。その典型的な例が、マリア・テレジア(1740-1780)によるインスブルックの居城のロココ様式化である。一方、マクシミリアンの時代から、チロルは、軍事面で特別な地位に置かれていた。チロル人は、外国での戦いに駆り出されただけでなく、彼ら自身のチロルを自分たちの手で守らなければならなかった。このため、チロルの農民には武器の所有が許され、防衛能力を持った農民軍は、バイエルンの度重なる攻撃からチロルを守った。
チロル農民軍の特筆すべき活動は、ナポレオン軍の侵略に対して果敢に反抗を試み、故郷を守ったことである。1805年、チロルとフォア・アルベルクとの連合軍は、ナポレオンとバイエルンの連合軍を蹴散らした。1809年、オーストリアがフランス及びバイエルン両国に宣戦布告をすると同時に、チロルにおいても抵抗運動が勃発した。
軽装備のチロル農民軍が連戦連勝のフランス軍を叩いたのは、それ自体が信じられないことであるが、何と言っても、チロル人の誇りは、農民軍を率いた民族の英雄アンドレアス・ホーファーである。彼の威風堂々とした指導者姿、マントゥアで銃殺された際の物怖じじない態度は、人々の胸を強く打つ出来事であり、チロル人は今日でも、この伝説を思い出しては楽しんでいる。19世紀後半に入り、チロルはヨーロッパの鉄道網に組み入れられた。この時代にまた人々は山の魅力を発見し、アルプスは保養、リェクリェーションの場として開発され、多数の観光客が往来することとなって、チロルに新たな収入をもたらすことになった。
第一次世界大戦の勃発により、チロル人は故郷の防衛に立ち上がり、イタリア軍の数十度にわたる攻撃を悉く凌ぎ、一歩たりとも侵略を許さなかった。しかしながら、大戦そのものは、オーストリアが敗北し、1919年、サン・ジェルマンの講和により、チロルの南半分(南チロル)は、イタリアに割譲されることとなった。
<地図はWikipediaより引用>
ここに、今日の姿であるチロルの領土及び民族の分断という不幸な現実が生まれた。この状況は、ヒットラーとムッソリーニの蜜月時代になっても変わることはなかった。むしろ、住民の意思は無視されて、南チロル住民のドイツへの移住が促進され、民族分断の状況は、今日に至るまで痼りとなって続いていたが、国家の枠を越えたEUの発展とともに、次第に解消に向かっている趣である。
第二次世界大戦後、イン・タールを東西に走る高速道路及びブレンナー峠越えの高速道路が開通した。これにより、チロルへの観光客は不断に増加し、チロルの住民は、オーストリアの平均的水準以上の高い所得に恵まれて、ヨーロッパの中でも比較的裕福な地域になった。
チロルの地域及び区分
今日、チロルと呼ばれる地域は、人為的な国境とは無関係に、マクシミリアン一世の時代にチロルの範図となった領域(ラント・チロル)全体を指している。従って、イタリアに割譲されたままの南チロルもチロルであるし、チロルでありながらドイツ領バイエルンを経由しなければ入れないチロル<リース・タールのエング>もまたチロルである。
ラント・チロルの総面積は、約2万平方キロ(オーストリア・チロル州約1.27万平方キロ、南チロル0.74万平方キロ)、長野県と岐阜県を合わせた程の広さである。チロル全域の人口は97万人余(オーストリア・チロル州55万人余、南チロル42万人余)。この地域の産業としては、森林を生かした林業、高原地帯を利用した牧畜業、乳製品製造業、南チロルの温暖な地形を利用した果樹園栽培、ワイン製造業などがあげられ、工業関係では、ガラス工業、木綿製造業、衣料品製造などが有名である。しかし、なんと言っても、中心となるのは観光業である。幹線を走る鉄道網、地域を縦横に結ぶ高速道路網、国道網は、観光客を主要な観光地のみならず、自然の景観が残されている谷の奥まで導いてくれる。尚かつ、廉価な宿泊代は、多くの観光客を引き寄せており、それがチロルの魅力をより高めている。
チロル州の紹介
クーフシュタイン〈Kufstein〉
クフーシュタインは、ドイツ・バイエルンとの国境及びイン川に架かる橋渡しの市として、チロルの北の入り口に位置している。草原と森林と湖水とに囲まれ、どっしりとしたカイザー山塊の懐に抱かれた市は、「チロルの真珠」と詠われている。
この市の歴史は古い。遡れば、この町は既に788年に「Caofstein」として、ザルツブルク大司教の財産目録の中に記録され、1257年には交易市として位置づけられ、1339年には都市権を有するまでになった。市は1342年、バイエルンのヴィッテルスバッハ家ルードウィッヒ・フォン・ブランデンブルグから、チロルの女伯爵マルガレーテ・マウルタッシュへの婚姻の引き出物として彼女に与えられた。後継者が途絶えて、彼女がチロルをハプスブルク家に譲り渡したことから、この地を巡って戦いとなり、その結果1369年、市は再びバイエルンに属することとなり、1393年、バイエルン大公シュテファン三世によって都市の周囲に防御壁が積み上げられ、その遺物は今日、〈Wasserbastei〉、〈Wasserturm〉として残っている。
市の所属が最終的に決着したのは1504年。ハブスブルク家の皇帝マクシミリアン一世がバイエルンのハンス・フォン・ピエンツェナウを打倒したことにより、クーフシュタインは再び、チロルに編入されることとなった。市は、その後も1703年及び1809年に両国間の争いの種にはなったが、その戦後処理で、バイエルンの旧所有者が再びクーフシュタインを獲得することはなかった。
駅からイン川の橋へ向かうと、まず真っ先に目に付くのは、川向こうの小高い丘の上に建っている堅固な要塞である。この要塞は1205年頃に建造され、バイエルンとチロルとの何度にも渉る戦いの最中で防衛線としての役目を担っていたことから次第に強固にされ、戦いの技術の進歩によって厚い城壁が完全に不必要と化すまで、常に新しい要塞建築技法が採用されて再建され続けてきた。市にとって唯一の歴史的建造物といえる要塞は、チロルでは特異なものである。このような強固で完璧な要塞は、他のチロル地方では見ることができない。
円形の塔は、皇帝マクシミリアン一世によって1504年の相続戦争の際に付け加えられ、時代のある時期には牢獄としても使用された。囚人のなかには貴族もおり、その名簿が房の横に掲げられている。要塞の中には、軍の施設に相応して装甲防弾室や秘密の深井戸、岩を刳り貫いた通路などがある。また、郷土博物館があり、この地方の風俗や地理を伝える展示品のほか、考古学的に重要な遺物が展示されている。
1931年に製造された世界最大のパイプ・オルガンは、要塞の市民塔にある。パイプの総数は4307本である。オルガンの演奏は毎日12時から行われるが、この演奏は、二つの世界大戦の犠牲者を慰霊し、その冥福を祈るためである。城壁上からの眺めは素晴らしい。イン川の緩やかな流れが見渡せる。
要塞には、パノラマ・ケーブルで簡単に上がれる。ケーブルは市を見下ろしながら上がり、観光客をものの数十秒で要塞の中庭にあげてくれる。要塞見学を終えたら、童話の世界そのもののレーマーホーフ・ガッセへ。アッと言う間に通り抜けてしまうが「何だ、これだけ」と思ってはいけない。酒蔵として有名なアウラッハー・レッヒェル、バッツェンホイスルなどが、美しい街並みの一角を構成しており、じっくり散策する人の目を楽しませてくれる。
その他の見どころは、ウンター・シュタッツ・プラッツ広場に面している。その中でも一際、目立つチロル風の建物は市役所である。市役所手前の階段を登れば地区教会があるが、歴史のある由緒正しい教会は、その奥にある三位一体教会である。その祭壇には聖母子の絵が描かれており、「黒帯のマリア」として有名である。広場には、金色に輝く「マリアの泉」像が鎮座している。
広場から北東方向に約三百メートル行ったところに丘陵公園がある。そこには、チロルの英雄アンドレアス・ホーファーの彫像が、市を見下ろすように建っている。度重なるバイエルンとの戦いを振り返り、バイエルンと接するこの地に、チロルを守るために戦った英雄の彫像を建てて、守りとしたのであろうか。
市の外れには、1756年創業のリーデル硝子工業が設けた博物館がある。各種の硝子製品が陳列され、更に製品生成過程を見学でき、販売所も付設されている。夏には、ここからイン川を航行する遊覧船が出ている。また、クーフシュタインからブレンテン・ヨッホへ登るリフトがあり、終着駅からは、自然保護地域のカイザー山塊が見渡せる。
マリアシュタイン〈Mariastein〉
マリアシュタインは、チロルの山々に囲まれた静かな村である。巡礼教会マリアシュタインは、この村に君臨するように建てられているが、抑もは、この地を通るローマ街道の安全を守る城があったことに由来する。1360年頃、望楼を備えた白亜の教会が建てられ、それが15世紀に巡礼教会に格上げされ、今日に至っており、都会の雑踏から逃れ、長閑な自然の懐の中で楽しみ、文化に近づこうとする人々や家族連れが好んで訪れる教会であり、あるいは救いを乞い、生きる希望を求める人たちがひっそりと尋ねる場所でもある。
正面入り口には、二人の騎士が門番として描かれている。この建物が城であった当時の名残である。中庭に入ると、第一次世界大戦の犠牲者を祀った祈念碑がある。丁重に礼をし、「神の家への入り口兼天国への門」と書かれたドアを畏れながら開けて、塔の上を目指し、139段の螺旋階段を上っていく。
まず、ケルツェン・カペレ(礼拝堂)に行き当たる。その昔は城のカペレだったところで、ピエタ(嘆きの聖母像)が置かれている。また、この部屋には、マリアへの奉納画や死者の冥福を祈るカードが、ところ狭しと貼り付けられている。更に階段を登っていくと、次はクロイツ・カぺレである。祭壇には、ガラス・ケースに納められた幼いキリスト像と、そのケースの上に立っているマリアの像がある。
このカペレの上の階が、巡礼教会である。ここで、人々はゴシック様式の素朴なマリア像に出会う。何ごとか諭すような慈悲深き姿は、見る人々の目を和ませる。対話を試みたい人は対話し、悩める人は縋りつき、人生に疲れた人は憩いを求め、そして、罪深き人は目を逸らす。マリアは、如何ようにも対応してくれる。
このキリストを抱いたマリア像は、15世紀の中頃に作られ、1971年、新たに彩色が施されて以前の輝きを取り戻した。左手に持った林檎を裸のキリストに指し示しているのは、マリアがイブで、キリストがアダムの生まれ変わりを意味しているとか。
階段脇のガラス・ケースには、チロル大公の冠と鍚が収められている。1602年、チロル大公マクシミリアン三世からの寄贈と記されている。ここは巡礼教会として人気があり、木製の階段は聖地巡礼者たちの靴跡で擦れ、歴史を感じさせる。ここへは、ヴェルグル駅とクーフシュタイン駅からバス便がある。
マリアシュタインの村は、ザルフェ高地〈Hohe Salve〉にあり、この村を起点として散策の道が広がっている。ザルフェ高地には、様々なテーマパーク〈悪魔の塩泉〉とか、〈エミールの魔法の世界〉とかがあり、特に後者は子供たちに人気がある。
グシュレス〈Gschloess〉
グシュレスは、リエンツから北へと伸びるタウエルン・タールがフェネディガー山塊にぶつかるところから西に折れ、谷奥へと入って漸く辿り着く村である。ザルツブルク州に抜けるフェルバータウエルン・トンネル=Felbertauern T.が完成するまでは、グシュレスは、タウエルン・タールの行き止まりであった。ここから先は、越すに越せぬ標高3000m級の山々が連なり、グシュレスは正しく、僻地中の僻地であった。
今でも、交通の便が良いとは言い難い。観光客は、マイカーかレンタカーで来るしかない。それも、グシュレスの入り口のマトライアー・タウエルン・ハウスまでである。ここから、アウサー・グシュレサー・アルムの村を通り抜けて5キロの道のりを標高差約200m登っていったところの谷奥に、インナー・グシュレスの村がある。
そこまでは、とても歩いて行けないという人には、マトライアー・タウエルン・ハウスに乗り合いタクシー(4.50ユーロ)か馬車(6ユーロ)が用意されている。が歩くだけの価値がある道である。インナー・グシュレスの村までの小道には「恋人たちの滝」や「女性の泉」、岩を刳り貫いて造った「フェルゼン・カぺレ」や数々の木橋が点在しており、散策にアクセントを添えてくれる。車で過ぎ去るには惜しい光景が次々に展開され、歩く人々を和ませてくれる。
インナー・グシュレスの村は、アルプスでも最も美しい谷の懐。
見上げて、正面の尖った頂きは、カイノア・ホルン。そこから左手に続く峰々は、クリスタル・ヴァント(クリスタルの壁)。右手の奥に見えるのは、グロース・フェネディガー=Grossvenediger。そこから落ちる雄大なシュラーテン・ケース氷河が白く輝き、目に眩しい。
唯、ここにはリフトもなければ、ロープウェイもない。氷河は目前にあるが、近寄りたかったら、歩いて登るしかない。勇壮な滝が遠望できるが、遙か彼方である。近くにレーベン湖、ヴィルデン湖という美しい湖があるが、そこへも歩いて行く以外にない。
住む人々同様、旅行者とて、ここでは頼れるものは自分しかない。それだけに、アルプスにあってまだ手つかずの自然が残されている秘境というに相応しい貴重な場所で、踏み入る者は、己だけのアルプスを見つけ出す喜びがある。
ヴァッテンス〈Wattens〉
インスブルックから東へ15キロ。イン川沿いの商業の町は、20世紀に入り、近代的工業団地として生まれ変わった。その中でも観光客に特に有名なのが、スヴァロフスキーである。
大抵の人は、スヴァロフスキーの名前を聞いたことがあるに違いない。その名を知らなくても、空港の免税品店を覗き歩きしたことのある人は、光輝くクリスタルの硝子工芸品が展示されているのを目にしたことがある筈である。駱駝、犬、猫、鹿などの小さな硝子細工から、汽車や車、あるいは女性の首や腕を飾る、首輪や腕輪、時計など、はたまたビキニの下着まで。
ヴァッテンスのこぢんまりした何の変哲もない町を有名にしたのは、ボヘミア出身のスヴァロフスキー。この町に対する彼の功績は絶大で、メイン通りを歩けば、ヴァッテンス高校の正面にスヴァロフスキーの銅像が建っているのが目に入る。
スヴァロフスキーの工場は町の外れにあり、ヴァッテンスの駅から西に向かい、トウモロコシ畑の間をくぐり抜け約20分歩けば、クリスタル・ワールドが待っている。駐車場には、大型バスが何台も連ねており、毎日、大勢の人が押し掛けてくる。巨大な人の顔をもじった正面入り口には、噴水の水が躍り上がって、観光客を歓迎してくれる。入り口から中へ、巨人の地下世界に招かれて進んでいけば、暗闇の中に輝くクリスタル、クリスタル、そしてまた、クリスタル。地下世界は各部屋に分けられていて、部屋ごとに名前が付けられており、最初の部屋は「青のホール」。そして、圧巻の「クリスタルドーム」。そこは、クリスタルの内部に侵入した場合に、どのように見えるのかを実体験できるエリア。更に、部屋は次々に続き、クリスタルで着飾った馬や女性、お伽噺の世界の再現もあればスフィンクスの姿。しれらを見物しながらコースを辿って歩いていくと、最後は販売コーナーへと出て来る仕組みになっている。
そこには、女心を擽るクリスタルの数々が財布の紐を解こうと躍起になっている。宝石よりは安く、硝子玉よりは煌びやかなクリスタルに魅了され、静かに溜め息をつく人もいれば、買い物バッグに次々と詰め込む人もいる。勿論、見学には入場料が徴収され、19ユーロと安くはないが、インスブルック・カードを購入しておけば、インスブルック駅前からの連絡バスに無料で乗れる上に、入場料はタダとなる。連絡バスは、一日6本ほど出ている。
インスブルック〈Innsbruck〉
チロル州の州都インスブルック。この地に魅せられて訪れた著名人は多い。旧市街にあるホテル兼レストラン、ゴルデナー・アドラーの入り口横には、彼らの名前が刻まれている。あまたの王侯貴族に混じり、1773年にモーツァルト、1786年にはゲーテ、1832年にはハイネの名前が見える。芸術家たちをかくも魅了したインスブルック。一体、どんな町なのであろうか。また、どのようにして発展してきたのであろうか。チロルの歴史を踏まえ、インスブルックの特徴を鑑みて、市の発展の様相を簡単に振り返ってみれば・・・
インスブルックは、イン・タールのほぼ中央に位置し、「イン川に架かる橋」というその名前の由来通り、イン川を挟むようにして発展してきた町である。イタリアからドイツ、また、その逆を移動する人々は、イン川を渡らなければなかった。それ故に、イン川に架かる橋は昔から南北交通の要所であった。
ローマ時代には既に、インスブルックへの植民が始まっていた。ブレンナー峠を越えるローマの道はイン川まで達し、3世紀には行路上にヴェルディデナ駅(今日の市の南部ヴィルテンの辺り)が建設され、4、5世紀にはヴィルテン地区教会が建てられた。教会に保存されている文書にも、このことが言及されており、この地域は当時から裕福であったと記されている。
6世紀になってバユヴァーレン族が侵入して定住し、この地はバイエルンの貴族が支配するところとなり、1180年、領主アンデックス伯爵の名前が歴史上、明らかになった。古文書によれば、1187年。この地は「Innsprucke」と名付けられ、中でもイン川沿いの風光明媚な所(現在のオットーブルクの近く)は、伯爵が確保し、十数年後にはそこに城が建設された。
インスブルックは交易、商工業などの発展で栄えたが、裕福な町は、それ故に屡々、略奪や攻撃を受け、それらから町を守るために強固な城壁が作られた。1239年。アンデックス伯爵の子孫、オットー・フォン・アンデクス公爵はインスブルックに都市権を与えた。その後、彼には相続人がいなかったためアンデクス家の支配は終わり、インスブルックはチロル伯爵に帰属することになった。その間にも町は更に発展し、城壁の内部が手狭になったため、今日のマリア・テレジア通りへ通じる地域が「ノイシュタット」として建設され、アンブラス城方向へ拡張された地域は「ジルバーガッセ」と名付けられた。
1363年。ハプスブルグ家がチロル伯領を獲得し、これによりインスブルックの発展は同家に委ねられることになった。「空の財布持ちのフリードル」と呼ばれたフリードリッヒ四世(1406-1439)は、領主の居住場所をメラーンのチロル城からインスブルックに移し、1429年、ここをチロルの首都とした。
15、6世紀に、インスブルックは文化的に輝かしい時代を迎える。チロルわけてもインスブルックに特別な関心を持ったマクシミリアン一世(1490-1519)がチロル伯を継いで領主となり、彼は、1486年にはドイツ王、1508年には神聖ローマ帝国皇帝となったが、可能な限りチロルに留まり、インスブルックを行政の中心としてだけではなく、文化的に価値ある都市へと変貌させた。
彼に芸術的センスを吹き込んだのは、最初の妃、マリア・フォン・ブルグントと言われている。ブルグント(ブルゴーニュ)は当時、文化の最先端をいく地方であった。ちなみに、彼の二番目の妃はビアンカ・マリア・スフォルツァ(ミラノ公女)であり、黄金の小屋根には、二人の妃が並んで描かれている。マクシミリアン一世の隣りがビアンカ・マリアで、その隣りがマリア・フォン・ブルグントである。その黄金の小屋根は彼の時代に作られ、その宮廷建築主任の二クラス・テューリングとその一族及びグムプ一族が、当時から18世紀に至るまでの間に、今日あるようなインスブルックの町を作り上げた。
マクシミリアン一世がチロルを走り回り、女から女へと遊び更けている間、インスブルックに留まっている妃への慰めとして、彼は王宮を豪華に仕上げさせた。マクシミリアン一世の曾孫のフェルディナンド二世(1564-1595)の治世の間は更に、文化的に光輝く時代であった。彼は全関心と全能力をアンブラス城に傾け、城をルネッサンス様式に建て替え、世界各国からの収集品で満たした。
1665年にチロルのハプスブルグ家が途絶え、この時からインスブルックはウィーン宮廷の直接的な支配下に置かれることになった。皇帝レオポルド一世(1665-1705)は、1669年、インスブルック大学を設立させ、女帝マリア・テレジア(1740-1780)は王宮を拡張し、凱旋門を作らせてインスブルックに新しい輝きを与えた。
1805年12月。オーストリアがナポレオンに降伏した際、チロルはフォア・アルべルクなどと伴にバイエルン王国に割譲された。バイエルン王国は、インスブルックに駐留軍事務所を設置し、チロルの名前は「南バイエルン」に置き換えられた。1809年、バイエルンの占領に対してチロルの農民たちが蜂起した。チロルは、アンドレアス・ホーファー(1767-1810)の指揮の下、ベルク・イーゼル(インスブルック南部)においてバイエルン軍と戦い、勝利を収めたものの肝心のウィーンが降伏してしまい、チロルは取り残されて、最終的には蜂起は失敗に終わった。チロルは結局、1813年のナポレオン没落までバイエルン王国の支配下に置かれることとなった。
19世紀中頃までに、インスブルックは学術都市及び行政府として著しい発展を遂げ、また、ブレンナー峠を越えるブレンナー鉄道線、ザンクト・アントンを通るアルベルク鉄道線の開通により、ヨーロッパの南北のみならず東西の交通の要所となった。このことにより、商業、工業、観光産業などが飛躍的に発展し、インスブルックの人口は急激に増加した。
第二次世界大戦で、市は度重なる空爆を受け、多大な被害を被ったが戦後、急速に再建された。1964年、1976年の二度にわたり、冬季オリンピックがインスブルックで開催され、ウィンター・スポーツのメッカとしての評価が高まった。今日、インスブルックは、大学で学ぶ3万人の学生を含む13万の人口を抱え、世界各国から毎年、2百ないし3百万人の観光客が訪れる著名な都市となっている。ちなみに、インスブルックは、動物園どうしの動物交流が縁で、長野県大町市との姉妹都市関係にある。
マッツェン城〈Schioss Matzen〉
マッツェン城Schloss Matzenがある小高い丘には、青銅器時代から人が居住していた形跡があり、ローマの時代になって、ここに要塞らしきものが建設され、城が建築されたのは1167年頃というから、かなり古い歴史を持つ。1468年まで、フロイデンスベルク家の騎士領に属していたが、その後は、頻繁に所有者が変わっている。特記すべきは、1873年に所有者なったアイルランド女性の息子、登山家に作家のウィリアム・グル―マンで、彼は熱狂的なチロル愛好者となり、1876年に「チロルとチロレーゼ」なる書物を著し、「イギリスやアメリカの旅行者にチロルへの扉を開いた人」として記憶されている。また、彼の友人である元米国大統領テオドール・ルーズベルトも度々、彼に招待されてこの城を訪問し、狩りの拠点として休暇を楽しんだとか。
また、第二次世界大戦中、インスブルックにあるチロル民俗文化博物館に貯蔵されていた宝物及びチロルに関する書物が、戦火を逃れるために、この城内に隠された由。そんな由来を有するマッツェン城。何度か改築、増築が繰り返され、大火に見舞われたこともあったが、今日、歴史的に重要なのは、北ウィングである。そこにあるゴシック様式のカペレは、1470年当時の文書にそれが記されており、チロル州立博物館に指定されている。
と記したものの、城は現在、ホテル業者に貸与されていて、宿泊でなければ、城の建物に立ち入ることができない。「そんな・・・思いやりがないのか」と嘆き、大枚を支払って宿泊者となった。一般見学者は中庭に屯していおり、彼らの羨望の眼差しを感じながら北ウィングに通じる扉へと案内される。中に入って見れば、入り口から階段が続き、登って出た踊り場の脇に「騎士の間」がある。総勢、16,7名が座れるテーブル席で、戦いの相談とか狩りの獲物の話とかに興じたであろうこの部屋は、今もまだ、ちょっとした宴会場になっている。騎士の間から、部屋続きの階段を数段、上がったところが、前述のカペレである。
となれば、咄嗟に頭に浮かぶのは、古城結婚式。カペレで結婚式を挙げ、「騎士の間」で披露宴を行い、更にそのまま領主の部屋に泊まれるのだから、これ程のロマンチックな場所はない。もし、うん十年前にこの城を知っていたら・・・騎士の間を出て、東側の扉を開けたところからは、格式に応じてグレードが異なる部屋が、二階から三階、四階へと続いている。それぞれの部屋は、張り出し廊下で結ばれている。因みに、最上級のスイート・ルームは「グランド・ロマンティック・デラックス・スィート」と名付けられ、その豪華な部屋に泊まれば、一晩だけとは言え、王侯貴族の気分に浸れること請け合いである。
三階からは、塔へ通じている。この塔は、外見はいかめしいが、内部はサウナになっている。塔の内部に入って階段を上っていけば、近代的なサウナやその関連施設、フィットネス等が続き、最上階にはバーがある。この最上階から見るマッツェン公園及びそれに続くイン・タールの眺めは圧巻である。この景観は宿泊客だけが味わえる特典で、城に泊まる価値を認識させてくれる。
更に、城内には宿泊客だけが立ち入れる付設の庭園がある。結婚式の後でのんびりと散策しつつ被写体になり、疲れたら東屋で休む。ここから見る城と塔の眺めは、宿泊客だけのもの。しかも、カレンダーの絵になる光景に、間違いなく愛は深まる・・・ハネムーンの二人だけでなく、日がな一日、こんなところでゆったりと過ごしたら、天国にいるような気分に浸れるのではないだろうか。
ちなみに、城の下に名前を頂いたレストラン「グート・マッツェン」があり、ホテルと提携している。高級そうなレストランで、結婚披露宴も、行われるとか。味は、舌の肥えた日本人にも充分、堪えられる。夕食を摂るため、城の裏口を開けてレストランに通じる階段を下り、ホテル客専用の扉を開けて入ったところ、店内は正しく、披露宴の真っ最中。新婦によるケーキカットで盛り上がっていた。こちらは一人では盛り上がれず、飛び入り参加で新郎新婦にカメラを向けたら、ちゃんとポーズを取ってくれた。
城の周囲は、マッツェン公園と名付けられた広大な緑地が広がっており、住民の憩いの場所となっている。緑の木々が溢れる公園には、二頭のライオンが並んだライオンの池とか、ニムフェウムと名付けられた噴水とかがあり、こちらは、城内とは異なって、誰でも好きな時間に立ち入ることができる。
ツィラー・タール〈Ziller Tal〉
イェンバッハからツィラー・タールに入るには、マイヤーホーフェンまで約32kmの行程を時速35kmで走る蒸気機関車が余りにも有名である。有名過ぎて、ツィラー・タールにはそれしかないようである。勿論、渓谷をのんびりと走る汽車に乗って、車窓から眺める景色も素晴らしいが、しかし、渓谷見物の醍醐味は、谷底を走っていては分からない。渓谷を見下ろす場所から鳥瞰するのが一番である。
ツィラー・タールには、ちゃんと、その道が用意されている。国道169号線のリートから表示に従って右折すれば、その道はツィラーターラー・ヘーエンファール・ヴェーク。正に、高所を走る高原道路である。道は、何度もヘアピン・カーヴを続けて登り、途中には豪快な滝などもあり、木々の切れ目からは次第に小さくなる谷底の町々が見え隠れし、やがて広々とした稜線に出る。視界が広くなれば、そこには休憩所がある。休憩所からは、渓谷の向こうに雪を頂いたアホルン・シュピッツェ(2976m)が望め、眼下にはツィラー・タールが一望の下に見渡せる。正に絶景である。ここではまた、パラグライダーを楽しむ人たちが次々に踏み出し、風を受けて空中高く舞い上がっていく。
ツィラー・タールには、ゲルロースとは、マイヤーホーフェン、トゥークスなどの保養地がある。
<フェーゲン村=Fuegen>
ツィラー・タールの入り口からすぐのところに、この渓谷最大の村フェーゲンがある。青銅器時代から既に、この辺りには人々が住み着いており、12世紀には、村の名前が文書に記載されて残っている。15世紀に入り、この地は、渓谷の産業の中心となり、大砲の砲弾とか、鎧の加工品、鉄の加工品などを製造する拠点として栄えた。今日では、ヨーロッパ最大の製剤所がある一方で、観光産業にもどっぷり浸かっている。
村の丁度、真ん中あたりに、白亜のどっしりしたフェーゲン城=Schloss Fuegenが建っている。2014年以降、フェーゲン村が所有するところとなり、文化的な催事に使用され、近いうちに、城内全てが一般公開される予定となっている。この城を有名ならしめている歴史的な出来事がある。1822年のこと、この城で、オーストリアのフランツ・ヨーゼフ一世とロシアのニコラウス一世が会談した際に、ツィラー・タールの民謡「きよしこの夜=Stille Nacht heilige Nacht」が初めて公に演奏された。その後、この民謡は周知の通り、クリスマスの合唱歌として世界中に広まった。
<ウデルンス=Uderns>
ツィラー・タールの入り口から入ったところに、ウデルンス村がある。ここには、かつてはオイルの蒸留所があり、16世紀から19世紀にかけては、製鉄工業が盛んで、村の住民たちの多くが製鉄所で働いていた。今は静かな村であるが、この村もまた、他の村々と同様に、観光地として発展してきている。
この村には、渓谷で唯一のゴルフ場<G.C.Zlilertal Uderns>がある。18ホール、バー71の本格的なコースであり、これだけの観光地に、たった一カ所のゴルフ場だからなのだろう、渓谷中からゴルファーがやってくる。付設のホテルの宿泊客は、無条件にプレーできるが、飛び入りの場合は、本人が所属するクラブの在籍証明書と公式ハンディキャップ証明書が必要となる。委細取り揃えて申し込むが、渓谷のいずれかのホテルに宿泊している証明があれば、料金は20%引きとなる。コースは結構、起伏があるので、Eカート使用がお勧め。フェアウェイは広々としているので、豪快に飛ばせる・・プレーヤーもいる。
<ツェル・アム・ツィラー=Zell am Ziller>
ツェル・アム・ツィラーは、ツィラー・タールの中心の村であり、政治や経済、教育関係の重要な施設は、ここに集まっている。ツィラーターラー観光学校も、ここにある。8世紀頃、村の東側にあるゲルロース峠を越えてやってきた修道僧たちは、この地の住民を改宗させ、村に修道僧のための部屋<Zell>を作った。その経緯で、村は「セレス」と呼ばれ、それが今日の村の名前の元となったとか。また、村には1500年頃に基礎を持つチロルで最古のツェラータール・ビールの醸造所がある。
保養地で鳴らしているツィラー・タールの代表的な村だけに、ホテルの設備も整い、訪れる客を飽きさせないよう各種の娯楽施設を備えている。スポーツは勿論のこと、カジノまで用意されている。そして、圧巻なのは、何と、金鉱見学である。「金ですぞ、金!」金と言われて顔が綻ばない人間は、余程の達人。成仏できないあなたには、打ってつけの見学コースではないですか。金鉱見学の集合場所は、町からゲルロース峠に向かう国道165号線を約3キロ程行ったところ。ハイツェンベルクと書かれた茶屋である。そこには、見学者用の汽車、その名もゴールデン・エクスプレスが待っている。
お伽の汽車に乗せられて麓まで降り、坑道の近くでヘルメットと合羽を貸与されて、いざ、鉱内へ。入り口には坑夫の守り神である「聖バルバラ」の像があり、その前で見学の無事を祈って後、坑道に入る。欲に駆られて坑道の中に入って行っても、残念ながら、ここそこに金が落ちている訳ではない。説明によれば、掘り出した岩石500kgに含まれる金の割合は、平均して1gにも満たないとか。と言う訳で、坑道内を歩いていても、金らしきものにはお目にかかれない。岩肌を見ても、金脈らしきものもない。そんなに容易に金が取れるなら、それ程の価値はないのだから、当然と言えば当然だが、欲に釣られて見学した者にはちょっと寂しい。せめて、金製品のお土産とか記念金貨製造といった類があればと辺りを見渡すが、それすらもない。
ここの鉱山は、1506年に試掘され、1609年から本格的稼働に入って村の繁栄に寄与することとなった。最盛期には95名の坑夫が働き、1トン当たり10gの金を採掘できたとか。鉱脈が尽き、1930年には閉山されたが、1996年から一般人見学用に公開されるようになった。
<聖バルバラ>
坑夫の守り神である聖バルバラは、救難聖人の一人で、鉱山のあるところ大抵の坑道の入り口に、坑内作業の安全を祈願して祀られているが、バルバラなる人物及びその生涯については「確かな史実がない」として、カトリック教会暦には記載されていない。伝説によれば、彼女は三世紀頃の人物で、小アジアのニコメディアの富裕な貴族ディオスクルスの一人娘であった。輝くような美しさに優しい心の持ち主で、言い寄る男たちはあとを絶たず、父親は、心配のあまりバルバラを城の塔の中に幽閉した。その時、お付きについていた侍女がキリスト教徒で、バルバラは、侍女の感化を受けてキリスト教に改宗した。
このことを知った父親は激怒し、彼女に棄教を迫った。そこで、バルバラは塔から逃げ出し、洞窟に身を潜めた。しかし、牛飼いに密告されて連れ戻され、それでも信仰を捨てなかったので、父親はやむなく、娘をローマの総督マルキアノスに引き渡した。総督は、偶像を示して神の偉大さを説いたが、バルバラは、「偶像の神々は、口はあれど語らず、目があれど見ず、耳があれど聴かず、鼻があれど嗅がず、手足があれど何もできない無力なもの」と述べたので総督は怒り、彼女の衣服を剥ぎ取って鞭で叩き、燃える松明を乳房に押しつけた。それでも改宗を拒んだバルバラは、見せしめとして大衆の前に引き出され、全裸にされて鞭打たれた。
しかし、バルバラの意思は固く、いかようにしても改宗させられなかったので遂に、父親の手で斬首されることとなった。一般に、キリスト教において聖人と崇められるのは、人々のために善行を施した人を言うのではなく、拷問や虐待にあっても聖書の教えを守り、信仰を捨てなかった人を指すようである。東洋的に考えれば、そのような人が聖人に列せられのは何とも不思議に思えるのだが、これも信仰の違いなのであろう。先のノートブルガならば、己の食を削ってまで貧者に施しをした行いがあり、凡人から見ても聖人に祀られるのは納得できるが、まず信仰ありきの宗教では、聖書の教えを堅く守り、ノートブルガの場合も「安息日の労働を拒否したことで教えを守った」ことが重視され、それで聖人に列せられたのではないかと勘ぐってしまう。
バルバラが坑夫たちの守護聖人になったのは、洞窟に隠れた伝説に由来するもので、今でも信心深い坑夫は、「処女にして殉教者なる聖バルバラの取りなしによって、不慮の事故にあわぬようにお願い致します」と祈って入坑するとか。
<マイヤーホーフェン=Mayrhofen>
マイヤーホーフェンは、ツィラー・タールの谷懐に位置するチロルで三番目に広大な平地にある。ツィラーターラー鉄道の終着駅は、この村である。村には、1200年頃の時代に、マイヤーホーフと呼ばれた司教の住居があり、村の名前は、それに由来している。駅から道路を渡って真っ直ぐ行った突き当りにあるのがオイロ―パ・ハウス。ここは観光案内所も兼ねており、マイヤーホーフェン及びその周辺の情報は全て、入手できる。またホテルの紹介もしており、飛び込み客でも何とか宿が見つかる。
村はチロルで一、二を争う観光保養地で、人口3600人に対して、ホテルのベッド数は、8千人分ある。これだけの観光客が来るのは、それだけの観光施設があるからで、この地域から出るリフト、ケーブル・カーの類は、数え切れない程である。村の四方縦横に、山登り、サイクリング、ハングライダー、川下り、岩登りと多種多様な娯楽を用意して、観光客を待ち受けている。子供連れの場合でも対応できるよう、ペンケン・バーンと呼ばれるケーブル・カーが子供の国まで引き上げてくれる。また、アクティビティを斡旋、仲介する業者は、村の至る所に見かけ、スキー客用にスキー教室もあれば、レンタルスキーの用意もある。スキー客に人気があるのは、冬場のみ設定されるペンケン・バーンの終着駅上から始まるノルディックのコースの途中にあるオーストリア最大の傾斜角78度を誇る通称「ハラキリ・ヒル<切腹の丘>」だとか。
各人好みのアクティビティを満喫したら、村の真ん中辺りにあるニエアレーブニス・バートに浸かってのんびりする。屋外プールと室内プール、サウナ、ジャグジーと用意されているが、バートと名が付いても、ここの湯は温泉ではない。夕食後は、オイロ―パ・ハウスで催されるオペラ、ミュージカル、室内演奏、チロルの夕べなどを見学する。とどのつまり、ここは一、二週間じっくり滞在して自然と文化を楽しむための村なのである。そのようなのんびりとした旅に慣れていない人は、勿論、見るべきものを見たら、ノスタルジックな汽車に乗って折り返すという手もある。
<ヒンター・トゥークス=Hinter Tux>
マイヤーホーフェンから西へ、ポストバスに揺られて渓谷を駆け上がり、ツィラー・タールの枝のように伸びるトウクサー・タールの行き止まりにある村は、高い山々に囲まれたヒンター・トゥークス。ここのパノラマのような景色は、只単に、素晴らしいの一言。農家の家々は、山の斜面にまで広がっており、牧歌的な光景が目の前に広がっている。観光客は、農家のチーズ工房でミルクからチーズを生成する過程を見学し、あるいは、ヨーロッパで最高地点にある温泉で、のんびりと湯に浸かり、日頃の疲れを癒すことができる。ちなみに、この源泉は、1600年には既に、文書の記録に留められている由。
また、ヒンタートゥークサー氷河に展開するスキー場は、ツィラー・タール3000と呼ばれ、オーストリアで唯一、年間を通して、スキーが楽しめる場所である。展望台付近から滑走するスキーヤーがいる一方で、スキー教室に参加した初心者が、コーチから手ほどきを受けている。勿論、スキーヤーでなくても、楽しみ方は満載である。観光客は、村からゴンドラを二回乗り継いで、標高3270mに位置するゲフロルネ・ヴァント・シュピッツェン展望台まで容易に上がることができる。展望台は、夏でも雪に覆われ、目の前に聳え立つピラミッド形のオルぺラー(Olperer3476m)を暫し眺め、雪原に足を踏み入れて夏の雪を楽しみ、雄大な景色を満喫して下山する。
展望台まであがるゴンドラの乗り換え駅前に「氷河満喫公園=Gletscherflohpark」なるものがある。ヨーロッパで最高地点に位置する子供向けの遊園地で、ここでは、一般用のトレッキング・コースに混じりながら、一周40分程度の周回道路をハイキングがてらに回って、子供向けのアトラクションとか、水の力の迫力、山との正しい付き合い方などを学ぶコースが設定されている。
と書くと、大人は立ち寄る必要はないと考えられがちだが、あに図らんや、何と、このコースには、スイスのアイガー、メンヒ、ユングフラウ三連山の大迫力に匹敵する地球の壮大な造形美が、手の届くような臨場感で迫っているのを眺められる絶好の場所がある。しかも、オルぺラーから連なる連山は四つあるから、余分に満喫できるというもの。ここを見ずして唯、単にゴンドラを乗り継いで過ぎては、勿体ない、勿体ない。
<オルパーラー・ヒュッテ=Olperer Huette>
マイヤーホーフェンの南西方向、ホーホファイラー=Hochfeiler(3501m)の麓にシュレガイス堰き止め湖がある。1965年に工事が着工され、1970年に完成を見たこのダムの高さは131mあり、ダム壁を登っていくクライマーが後を絶たない。
このダムが建設されたことで、幾つかの山小屋は水没の憂き目に遭ったが、更なる高台に新たに建設され、人気があるのはオルパーラー小屋<標高2389m>である。堰き止め湖からは、高低差約660m。約1時間半の行程(と書いてあるが、信用して甘く見てはいけない。これは健脚向きの時間であり、素人は2時間半は覚悟した方がいい。下りも1時間とあるが2時間は計算に入れた方がいい)で、コースは、岩場が多くて歩きづらいが、遙か彼方から落ちてくる豪快な滝の流れを慰めに、只ひたすら、登っていく。山小屋はそこに見えるのだが、行けども行けども近づかず、辿り着くまでが一苦労。だが、登り切れば丁度、昼時で、昼食にありつける。そして、山小屋から更に少し登ったところに、このトレッキングの最大のハイライト「吊り橋」がある。吊り橋の真ん中に立てば、堰き止め湖を背景にした絶好の撮影スポットで、登山客は、順番に被写体となっている。
山小屋辺りからの眺めは、壮大と言おうか、何とも筆舌に尽くしがたく、素人と雖も、その腕は兎も角、写真コンテストに出品したいと思わせる被写体が広がっている。問題は言わずもがな、天候である。
エッツ・タール〈Oetz Tal〉
エッツ・タールは、イン・タールから派生する渓谷の中では一番、長く、南チロルとの境のティムメルス・ヨッホまでは、65Kmもある。東のツィラー・タールと並び称される著名な谷である。谷の入り口の村は、エッツ=Oetz。エッツ村は、アルプスの3000m級の山の北限アッヒャー・コーゲルの麓に位置している。チロルで最も水温が高く、湖水浴に適し、自然の宝石と唱われている湖ピブルク・ゼーを抱えたエッツ・タールの中心地であり、観光案内所には、エッツ・タールに関する資料が整っている。村にはまた、ホテルを始め、レストラン、コンビニと観光客の便宜のための施設充実している。
身支度ができたらポストバスに乗って、いざ、谷の奥へ。エッツ・タールの特徴は、エッツターラー川の爆流と奇岩、それに滝。中でも有名なのは、ウムハウゼン=Umhausenの村外れにあるチロル一の規模を誇るシュトゥーイベン・ファール=Stuiben Fallである。滝の一部は既に、国道186号線から見える。車から降り、標識に沿って歩き始めて10分程すると、左手に音が聞こえてくる。更に進めば、流れの一端が見え始め、第一プラットホームに立てば、滝の本性が明らかになる。凄い!轟々たる水流は巨大な岩にぶち当たり、踊り狂って飛び跳ね、一気に駆け下りてくる。その流れは、辺りの木々や岩まで今にも飲み込みそうな勢いである。
麓から登ること約30分で、第二プラットホームに辿り着く。ここからは、159mの高さから豪快に落下する滝の全貌が見える。ここの水量は、まともではない。毎秒2千リットルとかで、辺り一面、岩に砕け散る水しぶきに包まれ、見とれていると、衣服はたちどころに水浸しになる。
更に、上の第三プラットホームへは、滝の右手の吊り橋、釣り階段を登って行く。この吊り橋。見るからに弱々しそうで、滝の勢いに飲まれそうな構造。それに、上に辿り着いたからと言って、滝の眺めがいいとは思えず、滝の全容は、第二プラットホームで充分に満喫できるので、「さほど、無理して登る必要は無い」と天使ならぬ地元の人は言う。滝は、下から見上げてこそ醍醐味が分かるので、全容は見えたのだから、天使の言葉に従い良しとする。この滝は、約8000年前、巨大な岩が川を堰き止め、流れを変えたことによって誕生したものだとか。印象的な自然現象であり、見る者の目を引きつけてやまない。
滝へ登る道の入り口に<エッツィ・ドルフ>がある。氷河に凍り付けにされた5200年前のミイラが生きていた当時を再現した施設である。が、彼がここに住んでいたという確証はない。どこに住んでいたかは不明で、ミイラは、発見された由来からこの谷の名前を取って「エッツィ」と名付けられたが、発見場所は、ほんの僅か南チロルに入っていた関係から、本体は、ボーツェンの考古学博物館に展示されている。ミイラも「あっちが本拠か、いや、こっちか」と楽ではない。
エッツィ・ドルフには、エッツィの家なるものが展示されている。家の中には、発見当時、見つけられた品々から、獣の皮製の防寒具やら狩りの武器などが再現されているが、小屋自体は、なかなか立派な建物で、日本の竪穴式住居を知っている者には、「それよりかなり前の時代の家としては、どうかな」と首を傾げたくなる。また、シャーマンの小屋もあるが、これはもう、発見された品々からの想像を超えたものである。
国道に戻り、更に奥を目指す。張り出すように突き出た絶壁の上には農家が見える。ほんの僅かな空き地を利用して人が住んでいる。渓谷のほぼ、中間あたりにレンゲンフェルトの村=Laengenfeldがある。街道筋の村ではあるが、国道から少し外れたところに、スパとかテルメを備えたホテル、アクア・ドームがある<エッツ・タールカードがあれば、テルメは無料>。
<ゼルデン=Soelden>
更に国道を進み、視線を左右に忙しく動かして辺りの景色を眺め、開けたところに出れば、そこはゼルデン村である。村の名前は「小さな農家が集まった集落」を意味するゼルダに由来するとか。この村は、夏ともなればエッツ・タール界隈の登山基地となり、冬は一大スキーのメッカとなる。この村だけで、毎年、200万人以上の宿泊客が訪れるというから凄い。
新潟県南魚沼市<旧塩沢町>と姉妹関係を結んでおり、その記念碑が建っている。集落としての規模は南魚沼市の方が上だが、自然アクティビティという点では、ゼルデンの方が遙かに勝る。何しろ、夏でも溶けない氷河がすぐ近くにあり、その側まで行けるのが魅力である。それも、氷河道路という豪快な山岳道路があって、車で上がれるし、バス便も、結構、頻繁に運行されている。これは、ヨーロッパで最も高所を走る高原道路である。
広大な谷底を見下ろしながら谷奥に進めば、レッテン・バッハ氷河に行き着く。そこからは、道が二手に分かれ、直進すれば、目の前にシュヴァルツ・シュナイデバーンのケーブル・カー乗り場が見える。その手前で左に折れれば、トンネル<ロジィー・ミッテルマイヤー・トンネル>に入り、行き着くところは、ティーフェン・バッハバーンのケーブル・カー駅である。
夏場もフルに運行しているシュヴァルツ・シュナイデバーンに乗れば、3000m級の山々が見渡せる「ビッグスリー」と呼ばれる展望台の一つ、インネレ・シュヴァルツ・シュナイデの近くまで運び上げて貰える。展望台は、高さ3367mの位置にあり、山駅から展望台までは、約20分の登り。足場も悪く、きつい上り坂だが、ここまで登ってきた疲れは、360度の視界が開けている眺めで癒される。南西方向には、オーストリア一の高山ヴィルト・シュピッツェが見え、その右手には、ピッツ・タールの谷奥深くにあるマンダリエン村とリッフェル湖が見下ろせる。東側に目を向ければ、ツィラー・タールの山々、南側は、晴れていれば遠くに、ラング・コーフェルを始めとするドロミテの山々。円形になっている展望台をゆっくり回り、もう一度、ゆっくり回り、椅子に座ってコーヒーでも飲みながらじっくり眺めたいと思うが、この展望台には、売店はおろか、レストランもない。
ビッグスリーのもう一つの展望台は、前述のロジィー・ミッテルマイヤー・トンネルを走り抜けたところにあるティーフェン・バッハ・バーン駅から、更に、ケーブル・カーに乗って辿り着く。終着駅は、その先がない断崖絶壁。そこから突き出た形の展望台。標高は3249m。前方には、幾つもの氷河が展開されている。際立って美しいのは。南側奥に見えるヴィルト・シュピッツから流れ下る雄大なミッテルべルク氷河。西方を望めば、ピッツ・タールの終着ミッテルベルグから登るヒンター・ブルンネン・コーゲル展望台が肉眼で微かに見える。右手の奥下には、ピッツ・タールのマンダリエン村が見下ろせる。そう。ここは、ヴィルト・シュピッツを頂点に分岐した渓谷の合流点である。一つはエッツ・タール、もう一つはピッツ・タール。しかし、二つの谷の様相は鮮やかに異なる。エッツ・タールは観光地化されているが、ピッツ・タールは鄙びた山間の渓谷という印象である。
ビッグスリーの最後の展望台は、村の外れにあるガイスラッハ・バーンに乗れば、そのまま辿り着く。設備の整った展望台だが、4,5人で一杯になる。眺めは、と言うと、前者の二つの展望台に比べれば、些かと言うか・・はっきり言えば、劣る。だからという訳ではないだろうが、ここには呼び込みのためのアイテムがある。映画007の舞台となったとかで、展望台から降り、南側に延びた尾根の先に向かえば、その途中の崖の上に、映画の撮影で使用されたというランド・クルーザーが置かれている。この尾根道は、岩の瓦礫のなかを進む感じになり、足場は悪いが、辿り着いたところからは、東側下方に、ゼルデン村が見下ろせる。蛇足ながら、ここの展望台には、立派なレストランがある。立派なものだから、価格は言わずもがな、かなり高めで、下界の二倍強は覚悟しなければならない。
<フェント=Vent>
ゼルデンから、更に、エッツ・タールの奥へと入っていけば、本筋から脇にはいるフェンター・タールがあり、この渓谷の突き当りがフェント村である。フェンター・タールは、荒々しさと緑とが見事に調和した様相を見せている。山あり、川あり、滝あり。色彩にも恵まれている。チロルで最も美しい渓谷と言われ、既に18世紀から旅行客がこの地に訪れていた。
ここから山を越せば南チロルであり、フェント村は昔から、あちら側にあるフィンシュガウ・タールとの関係が深かった。南チロルのカステルベルの裁判権に服していた時期もあり、教区で言えば、1938年まではトリエントの司教の管轄下であった。当時の人々は、エッツターラー・アルペン山塊を越えて行き来していたのである。その元祖が「エッツィ」。エッツィと名付けられたミイラは、このフェントの村からジミラウン・ヒュッテに登り、フィナイル・シュピッツ(3516m)へ向かったところで発見された。エッツィの発見は正しく、太古の昔から、人々が3000mを越える山々を登り越えて、南から北へ、北から南へと往来していたことの証左である。
現在でも、毎年6月中旬頃になると、羊飼いに連れられた何千もの羊たちが、シュナルス・タールからハウスラプ峠を越えてエッツ・タールまでやって来て、一夏をここで過ごしていく。羊に肖った訳ではないが、観光客用に、フェントを基点として多くのハイキング・コースが設備されている。その割には、夏場のリフトは、村の中心からシュタブライン<2365m>に登る一本だけである。ハイカーは、そこを基点として、思い思いのコースに歩いて行く。また、登山家は、ヴィルト・シュピッツを目指して踏み出して行く。どちらもしんどいと言う柔な御仁は、レストランで一服して、折り返しのリフトに乗る。
フェントの西側のローフェン高台<2014m>には、こぢんまりした集落というか、ホテルが三軒ある。ここからも、山男たちは、山に好かれて山奥へと姿を消して行く。草原の横には、荒れ狂い流れるローフェン・アッヘの川岸と川岸とを結んだ吊り橋があり、フェントからローフェン高台に向かうハイキング・コースに取り入れられていて、観光の目玉の一つになっている。橋そのものは網目模様の金属製で、下が透けて見えるのは精神的に良くない。足を踏み出す度に揺れるのは更に、良くない。
このハイキング・コースには、奇抜な岩が独特の名前が付けられて配置され、ひとつ一つを見ながら歩いて行くのは楽しい。高台の方のマルティン・ブッシュ小屋に向かうコースには、エッツ神なる作品もある。この高台のコースの先にはホーレ・シュタイン(Hohle Stein)と呼ばれる巨石があり、標識に従ってメイン通りから脇の細道を登っていけば、3分とある。巨石は丁度、雨除けに利用できるような構造になっており、前史時代の人々の一時的な利用の便になっていたのではないかと推測されている。
ローフェンでは、オーストリア国内最高地点で農業を営んでいる世帯があり、また、紀元前8世紀頃と推測されている石器時代の狩り用の洞穴跡なども発見されていて、見所となっているとか。
<オーバー・グーグル=Obergurgl>
エッツ・タールを更に奥へ進み、今度はグーグル・タール=Guegl Talに入る。その突き当りの村は、オーバー・グーグル。ここも、13世紀の半ば頃は、フィンシュガウの領主モンタルバンの支配下にあり、南チロルとの結びつきの濃いところであった。人々は、山懐からグーグル氷河の手前にかけて居住し、それ故に山を越えた南側のパッサイアーの裁判権に服していた。当時は苦労して登ったエッツターラー・アルペン越えの道は現在、ティメルス・ヨッホ=Timmelsjoch(2474m)越えの街道(1969年、完成)が通じて、南チロルとの交通は格段に便利になった。
オーバー・グーグルは、教会がある村としては、オーストリアで最も高所にある。この村が観光地として人々を引きつけるきっかけとなったのは、1931年5月27日、スイスの科学者アウグステ・ピッカートが気球に乗ってこの一帯を上空から視察していたとき、事故でこの地に緊急着陸したという極めて偶然の契機による。その結果、この地の素晴らしさが広まり、景勝地として人々が押し寄せることとなったのであり、その歴史的事件を記す記念碑が村の中心に置かれている。大きな丸い塊は、気球を表しているものだとか。また、その際、ピッカートを救助したマルティヌス・シャイバーの像が、メイン通りの突き当りに建っている。村の発展は、この二人に負うことが大きいという記憶が、記念碑と像により、住民の心に留められている。
オーバーグーグルは元々、エッツターラー・アルプスの麓にあり、スキーのメッカとして栄えた関係からか、夏は比較的、閑散としている。それでも、スキー客用のケーブル・カーが、夏場のハイキング客用に稼働しており、ホーエムート展望台(2670m)まで運んでくれる。登り詰めたところは、台地になっていて360度の視界が楽しめる。南側正面には、ゼーレンコーゲル(=Seelenkogel 3470m)が立ちはだかり、そこから伸びて来るのは、ロートモース氷河。その左手は、ガイスベルク氷河である。この二つの氷河の間は、恐竜の背のように浮き上がって伸びており、なかなか見応えのある光景である。但し、絶景ポイントに立つには、囲われた柵から一歩、外に出なければならない。そこは、自己責任の領域であり、出たとしても誰も注意せず、咎める者もいないが、何かあっても保障されないことは保証できる。
展望台にはレストランが一軒あり、氷河や周りの山々を見ながら、食事もコーヒーも楽しめる。また、辺りは羊の放牧場になっており、子供たちはすぐ羊と仲良しになる。これ程の贅沢な環境は、チロルでも少ない。偶然とは言え、こんな景観があるのだと知らしめた先の二人の功績は大きく、このような自然に囲まれて時間を過ごせる子供たちは、何と幸せなことだろうか。
<ホーホグーグル=Hochgurgl>
ホーホーグーグルは、ヴルムコーゲル=Wurmkogel(3082m)からのなだらかな斜面の麓にある。村には幾つかのホテルがあり、この村から出ているホーホグーグル・バーンから第2トップ・ヴルムコーゲル・バーンに乗り継いで登れば、容易にヴルムコーゲルまで上がることができる。ここからは、全方位の視界が開けており、アルプスの爽やかな空気を胸一杯吸い込みながら、北チロルの山々は勿論のこと、南側の南チロルの名だたる山々をじっくり堪能できる至福の時が、あなたのおいでを待っている。
ヴルムコーゲルは、スキーエリアとしてはチロルの最高地点にあり、冬ともなれば、一大スキー場と化す。<ティムメルス・ヨッホ=Timmelsjoch(2474m)>オーバーグーグルからホーホグーグルを抜けて山岳道路を登っていけば、ティムメルス・ヨッホへと通じている。この峠道は、紀元前300年頃には既に、通行されていた形跡があり、今では雄大なパノラマを体験できるルートとして人気が高く、ドライブとかマウンテンバイクで訪れる人が多い。但し、ちゃんと関所があって、それなりの通行料は徴収される。関所には、レストランとモーターサイクル博物館がある。
峠の頂上、南チロルとの国境付近には、奇妙な形の峠博物館がある。オーストリア一高所にある博物館で、峠越えの道が如何に切実なものであったか、この地域の歴史、自然、文化、経済、そして、人々などを交えて、知ることができるようになっている。
峠の先は南チロルの領域になり、峠道はザンクト・レオンハート村=St.Leonhardに下っていく。が、人並みに恐怖心を有している素人の体験として言えば、南チロルに抜けるトンネルから出ると、そこから下る道路は、崖の縁に無理くり造られた格好になるため、スリルがあるという雰囲気からは程遠く、嫌悪心さえ感じて、気が休まる暇がない運転が要求される。反対車線に大型バスが見えたときは、「どないしよう」と慌ててしまい、身体が竦む。
ピッツ・タール〈Pitz tal〉
ピッツ・タールの入り口にある村は、アルツル=Arzl。この村は、北からの寒風はレヒタール・アルペンに遮られるため、気候温暖な地帯であり、古くから人が住み着き、栄えてきた。高地にも拘わらず、あらゆる穀物、ジャガイモ、多くの果物が収穫され、ワインも製造されている。
この村に立ち寄ったら、是非、足を向けて欲しいのは、アルツルとヴァルトを結ぶ吊り橋ベンニ・ライヒである。この吊り橋は、ピッツェン峡谷の上、94mの高さに張られており、橋から下を覗き込めば、恐怖で足が進まなくなる。唯、吊り橋には板が敷き詰められており、足下から下は見えないので、高所恐怖症の御仁でも何とか渡り切れる。
ピッツ・タールを更に進んでいくと、突き当ったところは、海抜1740mのミッテルべルク=Mittelberg。山々に囲まれて一見、何もないところに見えるが、そこは地中を走る氷河急行の始発駅である。麓駅から乗り込めば、8分で千メートル以上の高低差を一気に駆け上がり、クリスタル・テラス(2860m)の展望台まで引き上げてくれる。一服する向きには、クリスタル・レストランがあり、食事ないしカフェを楽しみながら文字通りクリスタルの眺めを満喫できる。
クリスタル・テラスから更に、ケーブル・カー(ピッツパノラマ・バーン)を乗り継いで、眼下に氷河を見ながら終着駅に到着すれば、そこはオーストリアで最も高いヒンター・ブルンネン・コーゲル展望台(3440m)。アルプスでは、モンブランのエギューイ・デュ・ミディ(3842m)、マッターホルンのクライン・マッターホルン(3820m)、ユングフラウ・ヨッホのスフィンクス・テラス(3573m)に次いで四番目に高く、東アルプスでは一番高所にある展望台である。展望台には、チロル一高所にある喫茶店「パノラマ・ゾンネン・テラッセ」があり、雄大な自然を眺めながら頂くビールの最初の一口の何と美味なことか。
南側を臨めば、間近にヴィルト・シュピッツェ。そこからは、なだらかに傾斜して迫ってくる氷河の世界が広がっている。その右手には、ヒンター・ブロッホ・コーゲル(3635m)。そして、その右手奥の遠方には何と何と、南チロルの名山オルトラー(3905m)とケーニッヒ・シュピッツェ(3851m)が微かに望める。
西側には、遠くにジルヴレッタの山々とレヒターラー・アルペンが見え、北側の眼下にはピッツ・タール。その遠方には、ツーク・シュピッツェ。東側には、シュトゥーバイアー・アルペン、ツィラーターラー・アルペンの山々。その右手遠方には、ドロミテの山々。ここまで記せばお分かりの通り、ここは、チロルの名山が殆ど視界に入るチロル一の展望台である。が、展望台は、そんなに大きくない。多くの人が長時間、ゆったりと眺め入っており、格好の景色を撮るには順番待ちも。
麓駅に戻り、手前のマンダーフェン=Mandarfenへ。ここには十軒程のホテルがある。と言うより、ホテルしかないような集落だが、ここからは、リッフェル・ゼー=Riffelseeへと通じているケーブル・カーが出ている。山頂駅(2300m)に着いて少し登れば、目の前が大きく開け、眼下にリッフェル湖が見える。湖水は、氷河から溶けた水を集めて、どんよりとした蝋燭色に染まっている。湖の正面には、リッフェル湖を包み込むように立ちはだかる山々の雄姿。右手奥には、ビリッグ・シュピッツェから溶け落ちる氷河と、暫し、唖然としながら見入り、自然の雄大な景色に圧倒される。
まずは、のんびりと湖を周回する道に踏み入れる。途中で牛に出会う。別に、牛がハイキングしている訳ではないが、悠然とコースに寝そべって休憩している。起き上がる気配は全くなく、起こしたら反撃を食らいそうで、進退に窮する。そういう訳で、本来は人さま用に作られた散歩道なのに、それを利用できず態々、斜面に立ち入って灌木を避けながら迂回する方法をとる。漸く、散歩道に戻り、恨めしそうに牛を見るが、目も向けてくれな。それにしても、何を食べているのか、チロルの牛の肥えていること。何の悩みもなく、食べては寝て、寝ては食べての怠惰な生活がブクブクとした体形を造っているのでは・・翻って見れば、人間も同じか・・
一周したところで、ケーブル・カー駅に戻らずに、リッフェル・ゼー・ヒュッテまでは、是非、足を伸ばして貰いたい。道はほぼ、平坦で、時間にして20分程。そして、ここに立てば、正面にドンと構えるミッタークス・コーゲル(3159m)、その右手には、ホーホフェルナークト・シュピッツェ(3539m)から下ってくるタッシャッハ渓谷、左手には、ヴァイサー・コーゲル(3409m)から下ってくるミッテルべルク氷河が望めるという光景に恵まれる。正に、ここは地球の雄大な造形美が目の前に開けている贅沢な場所で、これだけの景色を満喫できれば、コーヒーの味が多少、口に合わなくても文句のつけようがない。
山小屋から、更に山懐へと向かって行く一団がいるが、彼らは山男。谷間に下っていく一団はハイカー。ケーブル・カー駅まで戻り、容易な方法で下りる御仁は観光客。マンダリエンの村に一泊して次の日の朝、川の水流が極端に少なくなっているのに気づいた。昼間は、氷河が温められて溶け出して川に流れ込んでいるが、夜は一転して溶け出す量が減り、それが川の流れに影響している。轟々たる流れが嘘のように静かである。
ロイッテ・イン・チロル〈Reutte in Tirol〉
ロイッテは、バイエルンとの国境の町。あの有名なノイシュヴァンシュタイン城があるフュッセンとは、目と鼻の先にある保養地である。周囲に、湖水浴に適した「プラン・ゼー」と「ハイタ―・ヴァンガー・ゼー」を抱え、気候も温暖であり、バイエルンの旅行作家ハインリッヒ・ノエは、この町を称して、「ロイッテほど、人を暖かく迎えてくれる町は他にない。長く滞在していても、毎日が気持ち良く感じられる」と語ったとか。
実際、街を歩いていくと、道路に面した窓枠には華やかな色彩の絵が描かれており、心を和ませてくれる。中でも、ツァイラー・ハウス・ガストホーフ・シュヴァルツァー・アドラーの家々の壁画が有名で、佇んでじっと見ている人を見かける。この町に古くから人が定住していたという痕跡はない。狩人とか牛飼いとか兵士、あるいは商人とかが、行き来はしていただろうが、確たる遺跡はない。ローマ帝国時代になって漸く、アウグスブルクへの交通の要所として認識され、人々が住むようになった。
13世紀の終わり頃、チロルのマインハルト二世は、国境を守る戦略的な要塞として、町の南方にエーレンベルク城=Schloss Ehrenbergを建設させた。城は、本体の他にクラウゼ要塞、シュロスコップ要塞、クラウディア砦ら成り、クラウゼ要塞は、南北の交通の要所として商業的に重要なルート(今日の179号線)を見下ろす格好の位置にあった。この城は同時に、行政及び裁判所としても機能し、アウサーフェルン全域をカバーした。今は、廃墟となった城だが、ここでは歴史を体験するための催し物が行われている。名付けて「騎士の足跡」。博物館内の部屋毎にそれぞれ、騎士の時代の14のテーマが選ばれて展示されている。ペストの部屋では骸骨が揺れてカタカタと音を立てており、錬金術師たちは実験に勤しみ、十字軍の兵士たちについて解説が施され、恰幅のいい騎士が見学者を次から次へと案内している。ここではまた、当時の騎士の鎧を着て、騎士を体験することもできる<但し、有料>。全てのコースをマスターした子供たちには、王妃ならぬ売り子さんが威厳を持って、彼らを騎士に任命している。なかには、騎士に任命される女の子までいる。
城へは、ゆったりとした上り坂を約20分程登って到着する。廃墟ではあるが、監視のための施設であるから当然のこととして、城からの眺めは良い。ロイッテや周辺の村々が眼下に見渡せる。
城を構成する一部のクラウディア砦は、渓谷を挟んで隔てた崖の上にあり、クラウゼ要塞からそこへ行くのに最近、渓谷を渡る「ハイライン179」と名付けられた吊り橋が渡された(通行料8ユーロ)。全長406m(歩行者用の吊り橋としては、世界で二番目。最長はツェルマットにある「ヨーロッパ橋」)、谷底から一番高いところで115m程、橋の幅は1,2m。渡り終えるのに要する時間は15分程度で、余裕のある勇者は途中で立ち止まり、橋から下を見下ろしたりして、比類の無い眺望を堪能している。吊り橋の左右にはフェンスがあるので、自ら乗り越えない限り間違っても落ちる心配はないのだが、足が竦んで歩けなくなる御仁もいる。筆者もその一人で、既に渡橋料金を支払っているのだが、どうにも渡る気がしない。躊躇っているとき、フランスから遙々、ここまで足を伸ばしてきた日本人のご家族と遭遇した。その子供さんたちがやはり、怖がって踏み出そうとしない。幼い子は母親にしがみついて泣きそうになっている。「ここで渡らなければ、あの子供たちと同じか・・」と思い、無理して渡り始めたとき、背後から母親が、「ほら、あのおじちゃんは、ちゃんと渡って行くわよ」と子供たちを鼓舞する声が聞こえた。<えっ?>何やら、渡らないければならない状況になってしまって・・
橋は、一度に1000人が渡っていても安全な設計になっているが、人数が多くなればなる程に、吊り橋の揺れ具合が大きくなり、足下が不安定になった途端、身体のバランスが崩れて進めなくなる。どうにかこうにか渡り終え、ホッとし、息を整える。まずは、お目当てのクラウゼ要塞を見物し、次いで、橋の左手にある展望台へと進む。展望台からは、対岸の丘の上に鎮座するエーレンベルク城の勇姿を見ることができる。「ここまで来て良かった」と思える景観を目にするのだが、城の左手に、か細い一本の糸が張られているのが見えた。それが先ほど渡ってきた吊り橋だと気づいた途端、俄に不安になる。その余りにもの頼りなさげな様子に、「あの橋を渡って帰るなんて正気の沙汰ではない」と思うが、あの橋を渡らなければ帰れない。「来るんじゃなかった」と後悔しても、もう遅い。
この吊り橋、結構、有名になっていて、ロイッテの観光に一役も二役も貢献しているのが窺えた。なお、吊り橋は、強風が吹いた場合は通行禁止となる。交通が盛んになるにつれて、ロイッテは中継地として繁栄した。塩の交易路としては、ハルとボーテン・ゼーを結ぶ拠点にあり、アウグスブルクとヴェネチアを結ぶ交易路の拠点でもあった。このことは逆に、他国から侵略される要因ともなり、1552年にはザクセン、1632年にはスウェーデン、1703年にはフランスの侵略を受けた。18世紀終わりになって、アルベルクを越える交通路が開拓され、ロイッテの地位は次第に低下し、交易路としての重要性は失われた。
代わって台頭したのが観光である。アルゴイアー・アルペンの麓町であり、自然に恵まれて観光スポットには事欠かない。特に、バイエルンのガルミッシュ・パルテンキルヒェンからロイッテとを結ぶ鉄道線は、風光明媚なアルプスの山間部を走る路線として隠れたる人気がある。特に、オーストリアに入ってからの景色は、絶景に次ぐ絶景。乗客は、右の座席に左の座席にと大忙しで、一度は乗ってみたいルートである。と記したところで、お分かりの通り、インスブルックから来る場合には、一度、ゼーフェルトを通ってドイツ領に入り、ガルミッシュ・パルテンキルヒェンでロイッテ行きの電車に乗り換えなければならない。インスブルックとロイッテを結ぶバス便も、あることはあるが、一日数便で、便が良いとは言えない。しかしながら、ロイッテは、フェルン峠越えとか、タンハイマー渓谷、レヒ渓谷への拠点となる町であり、車の往来は、ひっきりなしである。ちなみに、ロイッテは、岩手県奥州市と姉妹関係を結んでいる。
ロイッテの町の外れにロイッテナー・ベルクバーンがあり、ヘフナーアルム展望台(1733m)に登ることができる。ここからロイッテの町やエーレンベルク城、また周囲の山々やツーク・シュピッツェも望めるが、更に徒歩でハーネンカム・ギップフェル(1940m。高低差約200m、所要時間は約45分)まで上がれば、ここば如何なる展望台かを知ることができる。展望台としてはそれ程、高くはないが、西側にはタンハイマー渓谷が続き、ハルデン・ゼーは手の届くところ、南側にはレヒ・タールが遙か彼方まで伸びているのが見え、レヒ川の蛇行の様子も一望の下である。勿論、ロイッテの町も見下ろせる。
頂上は、そんなに広い空間ではなく、また、大部分を鉄塔の足場が占めており、一度に大勢が登った場合には、立ち位置に不便を感じる。また、鉄塔の他にはレストランも何もなく、登り詰めた疲労は、見渡す限りの自然の光景で癒すしかない。
<ブライテンヴァング=Breitenwang>
この村は、ロイッテのすぐ東側に位置し、経済圏としてはロイッテと一体である。古くは、「広々とした草原」を意味する地名で呼ばれ、1094年に、その名が文書に記されている。神聖ローマ帝国皇帝ロタール三世が1137年、旅の途中に、この地で没したことにより、村の名前が歴史に記されることとなった。その事実は、村役場前広場に面して建てられている農家の壁に彫り込まれた碑文に見ることができる。村は、ロイッテ自然公園内にあり、チロルへの入り口として知られている。村の近くには、アッヘン・ゼーに次いでチロル第二の大きさのプラン・ゼー=Planseeがあり、この湖は、運河によってハイターヴアンガー・ゼー=Heiterwangerseeと繋がっている。また、村は、岩手県奥州市と友好関係を結んでいる。
<ミェール=Muehl>
ミェールは、ロイッテの北東に位置する住宅街であるが、村外れにあるシュトゥーベン・フェレ=Stuibenfaelleの存在で知られている。プラン・ゼーから流れてくる小川が何段もの小さな滝を形成しており、所々にある滝壺とか沢とかが格好の遊び場となっている。勿論、川の流れであるから、突然の濁流に襲われる可能性があり、「川辺で遊ぶのは危険である」との警告表示がある。詰まり、遊ぶのは自己の責任においてである。なのに何故か、小さいながらも造形美に優れた場所なので、手軽なツアーの場所として選ばれ、ホテルで支給されるアクティヴ・カードのプログラムに、この滝への散策とか、滝壺へのキャノニングの案内がある。この宣伝に釣られて訪れ、事故に遭遇した場合であっても、責任は釣られた人にあると言うのは・・
<タンハイム=Tannheim>
ロイッテからレヒ・タールに沿って国道198号線を南西に下っていき、ヴァイセンバッハから西に折れる渓谷が、タンハイマー・タールである。タンハイムは、その中心となる村。渓谷の道は、そのまま進めば、バイエルンのゾントーフェン=Sonthofenに通じている。
タンハイマー・タールは、チロルでも非常に恵まれた環境にある渓谷との評価を得ている。抑も、渓谷の水流は、そのまま飲料水として使え、気候的な面では、清浄な空気が台地を包み込んでおり、「人類の生存にとって、他に何が必要であろうか」と言う訳で、子供がいる家庭にとって、この地は、休暇を過ごすのに最適な場所として人気が高い。その環境の良さは、村から南方に延びるフィルス・タール=Vils Talの奥にあるフィルスアルプ・ゼー=Vilsalpseeを訪れれば、一目瞭然である。
この湖は、アルゴイアー・アルプスの自然保護地域の秘宝と呼ばれており、その美しさは、如何とも形容し難い。2000年には、「ナトゥーラ2000」に認定され、ヨーロッパで最も美しい湖との評判を得たが、その評価に嘘偽りはない。岸辺に佇んで湖を見れば、湖水はどこまでも透明で、湖底までもが見通せ、見つめていると、湖に引き込まれそうになる。その神秘的な雰囲気から、今にも女神が金の斧を持って出てきそうな幻想に捕らわれるのは、「欲に目が眩んだ」と言う訳ではないであろう。更に、湖面はガラスのようで、周囲の山々がそのままに映し出されている。
湖は、そぞろ歩きで一周、90分程。周囲には、700を超える貴重な植物が発見されており、珍しいアルプス・サンショウウオとか土蛙などが、湖を住処としている。この湖からの流れは、フィルス川を経て大河ドナウ川に合流し、黒海に注ぎ込んでいるのだが、その地理的な事実は、湖畔に立って湖を見つめていると、現実離れとしか思えない。車は、自然保護のため10時から5時まで入れない。抑も、早めに入らなければ、駐車場の空きが無くなる。10時前に入った人が戻るのは自由である。ちなみに、タンハイムからのバス便もあり、このバスと観光用の馬車、観光トレインは、立ち入り時間の制限はない。
リエンツ〈Lienz〉
東チロルの県都であり、また唯一の都会でもあるリエンツは、「ド口ミテの真珠」と呼ばれ、この地方の政治、経済の中心地であり、インスブルックに次いで、オーストリア・チロル第二の都市でもある。ドラウ川に沿ったプスター・タール=Puster talとイゼル川が交わるところは、古くから交通の要所であり、既に述べたように、ロ一マ時代にはアグントゥムが建設され、その後ゲルマンの一部族ルルン伯爵が現在のリエンツ市北部に小都市を建築し、11世紀頃から城壁が建設され始めて、市の発展の基礎が築かれた。
1200年頃からは、ゲルツ伯爵家の支配の下で発展し、13世紀の前半にはブルック城が建築され、代々の伯爵は、14世紀に至るまで、ここを住居として使用した。この地域がチ口ルに編入されて後、16世紀頃、マクシミリアン一世は、リエンツをヴォルケンシュタイン・口ーデネック男爵に売却した。この間にも市は大きくなり、城壁は強固に固められた。1564年、真鍮工場が設立され、この工場は、その後300年もの間、稼働して地域経済を支えた。男爵家は、更に1608年、ハウプト広場に「リープブルク」を建設させて都市に彩りを添えたが、1609年の大火で、市内の家々は殆ど焼け落ちた。復興作業は捗ったものの、男爵家は多大な負債を追い、リエンツをハプスブルク家に売り渡さなければならなくなった。こうして、リエンツは再び、チロルに編入されることとなった。
市の中心にあるハウプト広場は、市民の憩いの場所であり、6月初頭から9月末までは歩行者天国となって、一般車両は入れない。広場の中央には花壇が設けられ、棕櫚の木々を挟むように、原色も眩しい花々が取り囲んでいる。正に、南国的雰囲気が漂い、道端にはテーブルが張り出されて、人々はのんびりコーヒーを飲んでいる。広場の中央に目立つ白灰色の四角い建物は、「リープブルク=Schloss Liebburg」である。17世紀の初めに建てられた城であり、1609年の大火の後、復旧されたときに、今日、見られる玉葱頭の丸屋根が付け加えられた。1988年に、大がかりな内装工事が施されて、その後は市役所として使用されている。
リープブルクの前の広場は「ハウプト・プラッツ」。ここでは、クリスマスのシーズンともなれば、「クリスト・キンドル」と呼ばれている大がかりなクリスマスの冬のマーケットが開催されることで世に知られている。この広場に建っているのは、聖フ口リアンの像。防火の守護聖人であり、1723年の二度目の大火に見舞われた後、二度と大火に逢わぬようにとの祈りを込めて、市民の献金により建てられたものである。
聖フロリアン=Florian von Lorchは、紀元300年頃のローマ帝国軍人で、バイエルン東部の帝国軍司令官であった。帝国軍司令官の役目は、軍務だけでなく、消防の任務も負っていた。この当時のローマの政策はキリスト教徒の撲滅にあり、皇帝の命により総督アヴィリヌスが派遣され、ラウリアクム一帯で40名の教徒を摘発し、拷問の上、収監した。この知らせを受けたフロリアンは、教徒を救助するために現地に急行した。しかし、彼はそこで、彼自身が教徒であることを告白したため、帝国軍司令官の職を剥奪され、逮捕された。総督は、フロリアンに棄教を強いたが、彼は断固として拒んだ。よって、総督は、フロリアンに死刑の判決を下した。フロリアンは、生きながら火炙りの刑に処せられるところ、彼が「炎に乗って天に昇る」と言ったために兵士達は恐れて、誰も火を点けられなかった。そこで、総督は、フロリアンの首に挽き臼を括り付けて川に突き落とすように命じ、304年5月4日に死刑が執行された。
フロリアンが、職務として消防の役目を負っていたことから、消火の守護聖人として奉られるようになり、彼の命日は、今日「国際消防の日」となっている。蛇足ながら、フロリアンへの祈りとして、「おお、聖なるフロリアンさま。私の家には何もしないで下さい。他の家々に火を点けて下さい=0,Heilliger St. Florian verschon mein Haus,zuenden andere an」という言葉があるそうな。イゼル川の縁に建てられているのは「イゼル塔」。丸い塔は、16世紀に市の周囲に張り巡らされた城壁の一部であり、現在は個人の住宅、事務所となっている。
<ブルック城=Schloss Bruck>
市の北方、イゼル川の入り口に建つのは、ブルック城である。12世紀から13世紀にかけて建築されたゲルツ伯爵の居城であり、現在は、郷土博物館及び美術館として使用されている。郷土博物館としては、この地域の宗教文化を伝える独特の絵画が集められている。見慣れている宗教画とは趣が異なる素朴な印象を受け、キリストの生涯を描く絵画は、悲劇の割には実感が感じられない。どこか幼稚ですらある。そのためか、幼子に授乳している〈ように見える〉マリアに出会える幸運にも恵まれる。
美術館は、城の三階、四階部分であり、「椅子に座った少女」の絵で有名な東チロル出身の表現主義派の画家アルビン・エッガー・リエンツ(1868ー1926)の作品「ハスピンガー」なども展示されている。また、ヒューゴ・エングルの「危険」は、小羊を抱いて崖の縁を伝い歩く少年の姿を描いたもので、見ていてもハラハラする程の現実惑がある。その他、フランツ・フォン・デフレッガーの「ツィター弾き」などの著名な絵画が展示されている。
<アグントゥム=Aguntum>
市内の見所が終わったら、次は、アグントゥム。リエンツ西方4キ口のデルザッハにあるチ口ル全域では唯一の口一マ時代の都市遺跡である。この辺りには、その昔、ケルト人の要塞があったが、ローマの占領とともに町が築かれた。皇帝クラウディウス(41-54)の時代に都市権を与えられ、交易の中継点として重きをなし、紀元1、2世紀頃に繁栄を見た。275年頃、アレマン族の侵入とともに荒廃が始まり、400年頃にはフン族から逃げてきたゲルマン族によって略奪され、5世紀の中頃にはフン族によって破壊され、最終的には610年頃に始まったバユヴァーレン族とスラヴ族との戦いの中で崩壊した。住民は、度重なる侵略から、更なる高台ラヴァントやその周辺に逃れたものと推測されている。
見学用の高見台から見下ろせば、市の門、住居跡や職場跡、公衆浴場などの土台が残っているのが見え、当時の繁栄ぶりを窺い知ることができる。この中でも特に重要なのは、現在、博物館として使用されているアトリウム・ハウスである。床には大理石を張り巡らせた贅沢な造りになっている。また、浴場の広さも目を見張る程であり、どっしりとした市の門は、当時のメインストリート(デクマヌス・マクシムス)の入り口であった。この市の門に連なる壁は、まだ両端まで全容が発掘されておらず、管理人兼発掘責任者ハネス・ローラーヒァー氏の話では、「かなり大きな都市であったことは間違いないが、全体の広さはどの程度だったのか分からない」とのこと。今までに発掘された出土品は、付設の博物舘に収められている。等身大の彫刻、大理石の文字盤などの他に珍しいガラス製品の数々、宝石類、金貨、銀貨の類などが展示されている。
<ラヴァント=Lavant>
リエンツから西方8キ口、山の中腹にある口一マ時代の遺跡。アグントゥムを継ぐ形で建てられたが、こちらはまだ十分な発掘がなされておらず、質素なもの。残っている数本の円柱が、寂しげにローマの遺跡らしさを感じさせるのみで、古の栄華を知る縁もない。折角、ここまで来たのだから、「この付近に見所は」と尋ねれば、間髪入れずに「巡礼教会マリア・ラヴァント」と返ってくる。1770年に建造されたもので、フレスコ画とか天井画、そして、安座するマリアなど、目を見張るものがある。
ラヴァントの近くに、東チロルで唯一の本絡的なゴルフ・コース G.C.Dolomitenがある。リエンツァー・ドロミテの麓にあり、ほぽ、平坦で、周囲の山々を見ながらのプレーは、爽快な気分に浸れること間違いない。ゴルフで疲れたら、リエンツに戻って、ドロミーテン・バートに浸かる。水の温度は29度で、木造のサウナも付設されている。屋外lこは、プールもある。
<リエンツァー・ドロミーテン=Lienzer Dolomiten>
「リエンツァー・ドロミーテン」と「ドロミーテン」を付けて呼ぶのは正確ではない。リエンツを囲む山々は、ドロミテとは生成が異なっている。しかしながら、ドロミテの山塊と接している関係から、リエンツァー・ドロミーテンの名が行き渡っている。そして、その名に恥じない、あまたの風光明媚な自然が広がってる。
<ノイアルプ・ゼーン=Neualpseen>
リエンツから手軽に行けるハイキング・コースとして、タウエルン自然公園内にあるノイアルプ湖群 (2450m)を目指すルートがある。出発地は、リエンツの北にあるシュタインナ―マンドル登山駅。リフトに乗り、山駅に着いたところから始まるのが、このコース。高低差は約300mで、周回コースを行って帰る所要時間は、約2時間半である。アルプスの絶景が至るところで楽しめるお勧めルートである。
<ラーザー・ゼー=Lasersee>
リエンツからラヴァントへ向かう途中で右折し、山道に入って行き止まりは、ドロミテン・ヒュッテ。この山小屋は、岩壁の突き出たところに建てられていて、よくぞ、こんなところに建てたものだと感心させられる。ラーザー・ゼーへのハイキングは、ここから始まり、暫くは、道は広く、なだらかで歩きやすい。更に進むと、道は二手に分かれる。片方は、登山路12で、些か急な坂道になり、途中は階段状になっているところもある。「何で、ここまで来て、態々、急坂を登らなければならぬ」正常な思考の持ち主は、もう一方の楽々コースを選択する。行き着く先は、どちらもカルスバッハ小屋である。この山小屋もまた、突き出た岩壁の上に建っている。そんな場所であるから、当然、眺めは抜群で言うことなし。ここまでの所要時間は約2時間とあるが、それは若者の健脚が基準となっている。些か、お歳を召した御仁は、プラス30分。帰路も2時間は計算しておいたほうが良い。それでも、リエンツァー・ドロミーテンを体験できたという歓びは、半端ではない。